
新NISAのおすすめ銘柄ランキング!初心者がつみたて投資枠で買うべき投資信託は?
最終更新日:
このページにはPRリンクが含まれています
また当サイトで得た収益は、サイトを訪れる皆様により役立つコンテンツを提供するために、情報の品質向上・ランキング精度の向上等に還元しております。※提携機関一覧
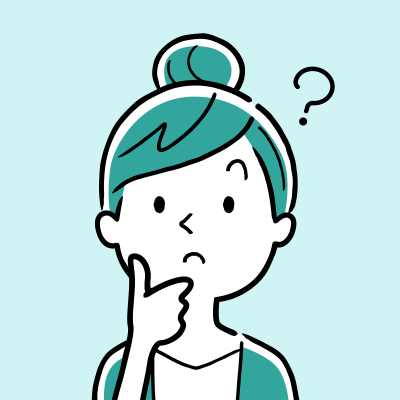
- 新NISAのおすすめ銘柄ってどれなの?
- 新NISAの証券口座はどこがいいの?
新NISAで購入できるおすすめ銘柄は、次のとおりです。
| 投資信託名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
迷ったらコレ! | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | ||||
| 運用タイプ | インデックス | インデックス | インデックス | インデックス | インデックス |
| 新NISA対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 年間の信託報酬 | 0.0814% | 0.162% | 0.05775% | 0.179% | 0.09889% |
| 詳細 | かんたん積立 シミュレーション | かんたん積立 シミュレーション | かんたん積立 シミュレーション | かんたん積立 シミュレーション | かんたん積立 シミュレーション |
新NISAは、投資で得た利益に税金がかからないお得な制度です。
しかし、投資する商品をうまく選べないと、思ったように利益が上げられず、非課税の恩恵を活かせなくなってしまいます。
また、NISA口座は1人1口座という決まりがあるため、NISA口座をどこで作るかも重要です。
この記事では、新NISAでおすすめの銘柄や口座、銘柄選びで失敗しないためのポイントを紹介します。
【掲載情報について】
※2025年5月2日時点の情報を掲載しています。
※最新の情報は、各証券会社の公式サイトなどからご確認ください。

株式会社400F 執行役員CGO(Chief Growth Officer) / 株式会社400F
監修者林 和樹
京都大学卒業後、2007年トヨタFS証券(現:東海東京証券)入社。2012年エイチームへ入社し、翌年に金融メディア事業を立ち上げ。最盛期には売上高72億円の事業に育てる。2019年エイチームフィナジーを設立し、代表取締役社長に就任。保険代理店業務を開始する。2022年5月より現職。個人理念は『お金の不安が意思決定の制約にならない世界を創る』。趣味はボディメイク。

イーデス編集部 / 株式会社エイチームライフデザイン
編集者板橋 辰汰郎
1998年生まれ、兵庫県川西市出身。
大学卒業後、2021年に新卒として株式会社エイチームフィナジーに入社し、ナビナビ証券、イーデスの編集者に就任。
▼書籍
初心者でもわかる!お金に関するアレコレの選び方BOOK
気になる内容をタップ
新NISAで購入する銘柄(投資信託)の選び方
新NISAで投資信託を選ぶ時は、以下の5つのポイントを確認しましょう。
新NISAの投資信託選びのポイント
インデックスファンド・アクティブファンドどっちにするか
投資信託は、ベンチマークする指標に基づいて運用を行います。
「指標に対して、何を目指すか」はファンドによって異なり、大きく分けると「インデックスファンド」と「アクティブファンド」の2種類に分けられます。


投資初心者はインデックスファンドがおすすめ
投資初心者はインデックスファンドを選ぶとよいでしょう。
アクティブファンドと比べると、ベンチマークとなる指標に連動するので値動きが分かりやすく、信託報酬も安いので運用しやすいといえます。
経験者であっても「低コストで効率よく運用したい」という人は、インデックスファンドをメインに投資すると良いでしょう。

投資対象はどこにするか

投資信託の投資対象は、4種類に分けることができ、期待リターンとリスクが比例します。
| 投資信託の種類 | 国内株式型 | 先進国株式型 | 新興国株式型 | 複合資産型(バランス型) |
|---|---|---|---|---|
| 期待リターン・リスク | 低い | やや高い | 高い | 内容による |
| 参照元 | TOPIX、日経平均株価など | MSCI World Indexなど | MSCI Emerging、Markets Index FTSE、Emerging Indexなど | 複数の指数、債券、REITなど |
| ファンド数 | やや少ない | やや多い | 少ない | 多い |
投資初心者は「国内株式型」「複合資産型」がおすすめ
投資初心者には、リスクを抑えられる「国内株式型」や「複合資産型」がおすすめです。
国内株式型は、リスク商品に該当する株に投資しますが、為替変動の影響を受けないため比較的リスクは低いと言えます。
また、複合資産型(バランス型)は、株式・債券・REITなど、様々な資産にバランスよく投資するのが特徴で、リスク分散されています。
一方の先進国株式型や新興国株式型は、為替変動の影響を受けたり、大きな利益獲得を狙い政治・経済が不安定な国に投資したりと、国内株式型や先進国型よりもリスクが高くなっています。
ファンドによっては高い収益が期待できますが、基本的には安定収益の獲得を目指すと考えた方が良いでしょう。

信託報酬はどれくらいかかるか
つみたて投資枠の商品は、全てノーロード(販売手数料が0円のもの)に限られるため、販売手数料を気にする必要がありません。
しかし、保有額に応じて運用会社に対して日々支払う「信託報酬」を考慮する必要があります。

なお、つみたて投資枠の信託報酬率の上限は、告示によって以下のとおり定められています。
| 指定インデックス投信 | アクティブ運用投信等 | ||
|---|---|---|---|
| 株式型 | 国内 | 0.5% | 1.0% |
| 海外 | 0.75% | 1.5% | |
| 内外 | 0.75% | 1.5% | |
| 資産複合型 | 国内 | 0.5% | 1.0% |
| 海外 | 0.75% | 1.5% | |
| 内外 | 0.75% | 1.5% | |
※引用元:積立NISAについて|金融庁、つみたて投資枠対象商品の分類(2025年4月28日時点)
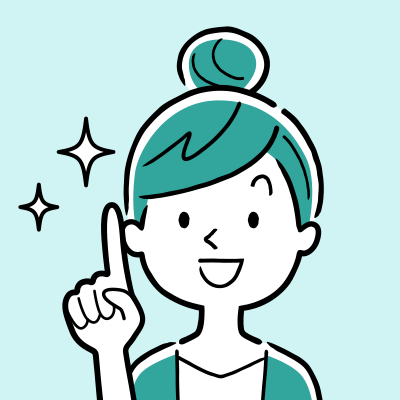
インデックスファンドのほうが信託報酬が低そうですね!
そうですね!
ただし中にはアクティブファンドよりも高いものもあるのでしっかり確認しましょう。

トータルリターンはどれくらいになるか

トータルリターンは、投資信託に投資した際のリターンをすべてまとめたもののことです。
計算方法
解約時までの分配金累計 - 解約代金 - 保有評価額
=トータルリターン
手数料や分配金を反映して、利益がどれだけ出たかを明確に示すため、投資信託ではトータルリターンが重視されています。
また、複数の期間ごとにトータルリターンをチェックすれば、一定期間でどれだけ資産が変動したかを把握できます。
今後伸びそうな国が入っているか
昨今では新興国ファンドもおすすめです。
新興国とは日本や欧米をはじめとした先進国ほど経済水準が高くないものの、これから高い成長性が見込まれると判断された国のことを指します。
具体的には中南米や東南アジア、中東、東欧などの国を指すケースが大半です。
たとえば、「たわらノーロード 新興国株式」では中国と台湾の組入比率が全体の約30%を占めるほか、インドなど経済成長に注目が集まる国も組み込まれています。
投資する際は各国のGDP成長率などにも着目しつつ、銘柄を決めると良いでしょう。
【投資家が選ぶ】新NISA(つみたて投資枠)おすすめ銘柄ランキング ❘ インデックスファンド
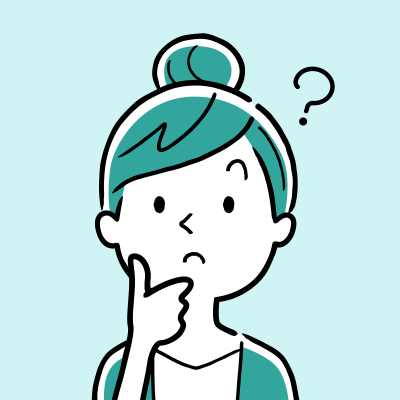
実際にNISAをしている人はどの投資信託を選んでいるの?
投資家552人に聞いたおすすめの投資信託ランキングを見てみましょう!

※2022/6/6-7にFastaskでアンケート実施
新NISAの人気銘柄(つみたて投資枠)を買うなら!
※1 日本証券業協会「NISA口座の開設・利用状況」および各社公表資料より算出(2024年9月末時点)(公式サイトにて確認)
※2 2023年3月期 通期(2022年4月~2023年3月)の委託個人売買代金シェアです。SBIの数値は、SBIネオトレード証券の数値を含みます。(出所:東証統計資料、各社WEBサイトの公表資料より当社集計、各社委託個人(信用)売買代金÷{株式委託個人(信用)売買代金(二市場1,2部等)+ETF/REIT売買代金}にて算出)。(公式サイトにて確認)
1位:eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
| 運用種別 | 米国株式 |
| 運用方針による種別 | インデックスファンド |
| 対象投資枠 | つみたて投資枠・成長投資枠 |
| 年間の信託報酬 | 0.0814% |
| 純資産 | 63,718.29億円 |
※2025年5月2日時点
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)は、S&P500インデックスマザーファンドを通じて、S&P500指数に連動した投資成果を目指している投資信託です。
投資対象は米国株式のみとなるため、米国株式市場、特にS&P500指数に採用されている米国企業の成長による恩恵を受けられます。
また、純資産額が6兆円を超えているビッグファンドでもあります。
過去の運用成績をみると、2025年3月末時点の最大上昇率で3年間は+108.04%、ここ5年間は+210.95%と、非常に好調だといえます。
米国市場の成長に期待したい方や、ドル高の恩恵を享受したい方におすすめです。
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 23.89%)の運用結果
- 最終運用結果
- 2億円
- 運用コスト
- 63万円
- 手元に残る金額
- 約2億円(+2億円)
2位:楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
| 運用会社 | 楽天投信投資顧問 |
| 運用種別 | 米国株式 |
| 運用方針による種別 | インデックスファンド |
| 対象投資枠 | つみたて投資枠・成長投資枠 |
| 年間の信託報酬 | 0.162% |
| 純資産 | 16,104.13億円 |
※2025年5月2日時点
楽天・全米株式インデックス・ファンドは「楽天・VTI」の愛称で親しまれている投資信託です。
VTI(バンガード・トータル・ストック・マーケット・ETF)といえば、経費率が非常に低く、米国市場の約4,000銘柄の成長を享受できるファンドとして人気を博しています。
この投資信託もVTIと同じく、CRSP USトータル・マーケット・インデックス (円換算ベース)に連動する投資成果を目指しており、直近5年間の運用成績は+203.75%と好調です。※2025年3月末時点
コストの低い投資信託で運用したい方や、米国市場の成長を捉えたい方に向いている銘柄です。
楽天・全米株式インデックス・ファンドの積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 22.98%)の運用結果
- 最終運用結果
- 1億円
- 運用コスト
- 112万円
- 手元に残る金額
- 約1億円(+1億円)
3位:eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
| 運用種別 | 先進国・新興国株式(広域) |
| 運用方針による種別 | インデックスファンド |
| 対象投資枠 | つみたて投資枠・成長投資枠 |
| 年間の信託報酬 | 0.05775% |
| 純資産 | 54,181.62億円 |
※2025年5月2日時点
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)は、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、日本株式インデックスマザーファンドという3つのファンドを通じ、日本を含む全世界の株式などに投資しています。
その特徴は「オールカントリー」の名の通り、全世界の株式に分散投資できる点です。直近5年間の運用成績は+178.94%と、上記のeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)には劣るものの、高いパフォーマンスを発揮しています。※2025年3月末時点
より広い範囲で分散投資したい方におすすめできる銘柄です。
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)の積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 20.19%)の運用結果
- 最終運用結果
- 9,600万円
- 運用コスト
- 28万円
- 手元に残る金額
- 約9,571万円(+8,851万円)
4位:楽天・全世界株式インデックス・ファンド
運用会社 | 楽天投信投資顧問 |
| 運用種別 | 先進国・新興国株式(広域) |
| 運用方針による種別 | インデックスファンド |
| 対象投資枠 | つみたて投資枠・成長投資枠 |
| 年間の信託報酬 | 0.179% |
| 純資産 | 5,301.76億円 |
※2025年5月2日時点
楽天・全世界株式インデックス・ファンドは、日本を含め全世界の株式に投資するファンドです。
FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)と連動した成果を目指して運用されています。
全世界の幅広い銘柄にまとめて投資ができるので、世界的な経済成長の恩恵を受けたい人に向いているファンドです。
楽天・全世界株式インデックス・ファンドの積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 19.53%)の運用結果
- 最終運用結果
- 8,693万円
- 運用コスト
- 82万円
- 手元に残る金額
- 約8,612万円(+7,892万円)
5位:eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
| 運用種別 | 先進国株式(日本を除く/広域) |
| 運用方針による種別 | インデックスファンド |
| 対象投資枠 | つみたて投資枠・成長投資枠 |
| 年間の信託報酬 | 0.09889% |
| 純資産 | 8,139.81億円 |
※2025年5月2日時点
eMAXIS Slim 先進国株式インデックスは、日本以外の世界先進・主要国の株式で運用されているインデックスファンドです。
MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動した投資成果して運用されています。
運用成績も好調で、2025年3月末時点で直近5年で+197.09%というかなりの好成績を出しています。
長期的に資産形成を行いたい方や、日本以外のグローバル企業に投資したい方におすすめできる商品です。
eMAXIS Slim 先進国株式インデックスの積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 21.87%)の運用結果
- 最終運用結果
- 1億円
- 運用コスト
- 60万円
- 手元に残る金額
- 約1億円(+1億円)
新NISA(つみたて投資枠)おすすめ銘柄4選 ❘ アクティブファンド
①純資産総額が比較的多い
②直近3年間の運用成績が優れている
1.ひふみプラス
| 運用会社 | レオス・キャピタルワークス |
| 運用種別 | 国内株式 |
| 運用方針による種別 | アクティブファンド |
| 対象投資枠 | つみたて投資枠・成長投資枠 |
| 年間の信託報酬 | 1.078% |
| 純資産 | 5,413.58億円 |
※2025年5月2日時点
ひふみプラスは、ひふみ投信マザーファンドを通して、主に国内の上場株式に投資している投資信託です。
より高い成果を目指すアクティブファンドのため、経済循環や経済構造の変化などから総合的に判断し、長期的なリバランス(ポートフォリオを組み替えること)や新規銘柄への投資を行っています。
インデックスファンドに比べてパフォーマンスが安定しにくいアクティブファンドのなかでは継続して成果を出しており、人気があるファンドです。
インデックスファンドと分散投資するなら、このファンドを選定してみてはいかがでしょうか。
ひふみプラスの積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 9.35%)の運用結果
- 最終運用結果
- 2,095万円
- 運用コスト
- 171万円
- 手元に残る金額
- 約1,924万円(+1,204万円)
2.コモンズ30ファンド
| 運用会社 | コモンズ投信 |
| 運用種別 | 国内株式 |
| 運用方針による種別 | アクティブファンド |
| 対象投資枠 | つみたて投資枠・成長投資枠 |
| 年間の信託報酬 | 1.078% |
| 純資産 | 641.14億円 |
※2025年5月2日時点
コモンズ30ファンドは、主にコモンズ30マザーファンドへの投資を通じて、実質的には国内外の株式に投資しています。
ファンドの方針は、世代を超えて進化を続ける“強い企業”、ベンチマークではなく厳選した約30社に対する長期的な集中投資です。
現在は、KADOKAWA、任天堂、味の素、セブン&アイ・ホールディングス、三菱商事、コマツ、日立製作所などの株式で運用しています。
※2025年3月31日作成のコモンズレターより
ここ数年間も、コロナ禍でのダメージを感じさせないパフォーマンスを出しています。
純資産額がかなり少ない点は気になりますが、投資信託を通じて国内株式へ投資したい方や、コモンズ投信ならではの運用による利益を得たい方は、この投資信託を検討してみてください。
コモンズ30ファンドの積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 12.65%)の運用結果
- 最終運用結果
- 3,241万円
- 運用コスト
- 234万円
- 手元に残る金額
- 約3,007万円(+2,287万円)
3.日経平均高配当利回り株ファンド
| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
| 運用種別 | 国内株式 |
| 運用方針による種別 | アクティブファンド |
| 対象投資枠 | つみたて投資枠・成長投資枠 |
| 年間の信託報酬 | 0.693% |
| 純資産 | 1,782.88億円 |
※2025年5月2日時点
この投資信託は、日本へ100%の投資を行う投資信託です。
とにかく配当にこだわったファンドで、日経平均株価に採用されている銘柄の中から、予想配当利回りの上位30銘柄を選んで、銘柄毎の組入比率を決定しています。
原則6・12月に組入銘柄の入替えと組入比率の調整を行っており、年2回分配が行われます。
NISAのつみたて投資枠・成長投資枠ともに対象銘柄ですので、非課税で投資することが可能です。
投資初心者の方や日本株式や配当にこだわり高配当を狙っている方はチェックしておきたいファンドです。
日経平均高配当利回り株ファンドの積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 23.01%)の運用結果
- 最終運用結果
- 1億円
- 運用コスト
- 481万円
- 手元に残る金額
- 約1億円(+1億円)
4.ニッセイ日本株ファンド
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
| 運用種別 | 国内株式 |
| 運用方針による種別 | アクティブファンド |
| 対象投資枠 | つみたて投資枠・成長投資枠 |
| 年間の信託報酬 | 0.88% |
| 純資産 | 1,660.00億円 |
※2025年5月2日時点
ニッセイ日本株ファンドは、ニッセイ日本株マザーファンドを主な投資対象として、国内の株式などに投資しています。
TOPIX(配当込み)をベンチマークとし、中長期的にTOPIX以上のパフォーマンスを目指している点が特徴です。
現在の組み入れ銘柄は、トヨタ自動車、三菱UFJフィナンシャル・グループ、キーエンス、リクルートホールディングス、ソニーグループなどです
※2025年1月末現在(2025年2月7日末更新分)のマンスリーレポートより
過去の運用成績も、比較的安定した成果を残しています。
日本株式の成長に期待したい方や、日本株式のインデックスファンドを上回る成果を望む方は検討してはいかがでしょうか。
ニッセイ日本株ファンドの積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 14.36%)の運用結果
- 最終運用結果
- 4,105万円
- 運用コスト
- 227万円
- 手元に残る金額
- 約3,877万円(+3,157万円)
新NISAおすすめ人気銘柄(成長投資枠)5選
①経営が安定していて、キャピタルゲインが狙える銘柄
②配当金や株主優待も狙える可能性がある
2024年から始まった新NISAは、一度売却したらその分の非課税枠を翌年以降に再利用できるようになりました。
そのため、非課税枠が復活しなかった従来のNISAに比べて、短・中期でのキャピタルゲイン(売買益)を狙った取引がやりやすくなったといえます。
ただし、短・中期で利益を上げる投資スタイルは、その分難易度やリスクが高く、投資初心者のうちはおすすめできません。
そのため、今回が5年~10年後まで保有していても値上がりが期待できる銘柄を選んでいます。
また、長期保有でも不安のないように、経営基盤がしっかりしている銘柄であるかも踏まえて厳選しています。
保有中には配当金や株主優待も得られることも勘案しているので、ぜひ銘柄選びの参考にしてください。
新NISAの人気銘柄(成長投資枠)を買うなら!
※1 日本証券業協会「NISA口座の開設・利用状況」および各社公表資料より算出(2024年9月末時点)
※2 2023年3月期 通期(2022年4月~2023年3月)の委託個人売買代金シェアです。SBIの数値は、SBIネオトレード証券の数値を含みます。(出所:東証統計資料、各社WEBサイトの公表資料より当社集計、各社委託個人(信用)売買代金÷{株式委託個人(信用)売買代金(二市場1,2部等)+ETF/REIT売買代金}にて算出)。
1. コラントッテ(7792)
コラントッテ
| 銘柄コード | 7792 |
|---|---|
| 上場市場 | 東証グロース |
| 株主優待 | 自社ECサイト割引クーポンなど3種類 |
| 予想配当利回り | 3.17% (2025年5月) |
専門家おすすめポイント
- 増収増益が続いている
- 増配が続いている
- デザイン性が高い製品を、割引価格で購入できる
コラントッテは磁気ネックレスなどの家庭用磁気治療器の開発・販売を行う会社で、2021年9月期以降配当を実施し、増配が続いています。
また、株主優待は100株以上から実施し、ECサイトで利用できる割引クーポン、カタログ掲載商品(ECサイトを利用できない株主向け)の割引購入、社会貢献活動への寄付の3つから1つを選べます。
製品の1つであるの磁気ネックレスは医療機器として認められているだけでなく、普段使いできるおしゃれなデザインが特徴です。
株主優待の割引クーポンは保有期間によって優待内容が異なりますが、3年未満の場合でも、100株以上保有で5,000円相当(3年以上保有の場合10,000円分)、500株以上保有で15,000円相当(3年以上保有の場合20,000円分)、1,000株以上保有で20,000円相当(3年以上保有の場合30,000円分)の特典を受けることができます。
※株主優待の内容については適宜変更される場合があるため、公式サイトなどでご確認ください。

佐藤 真奈美/証券外務員1種
ベンチャーキャピタルをはじめとした投資会社での経験あり。現在は投資会社にてファンド運用を行いながら、金融関連記事の執筆中。
コラントッテの2023年9月期は3期連続となる増収増益の見通しです。
厚生労働省の調査では、病気やけが等で自覚症状のある者(有訴者)は人口千人当たり302.5で、腰痛と肩こりが上位5症状の1位と2位となっていることから、家庭用磁気治療器のニーズは高いと考えられます。
これまで男性向け商品を中心に展開していましたが、2022年4月からは女性に特化した新ブランドも展開しています。
前述の厚生労働省の調査では、有訴者の割合は女性の方が男性より高く、女性の上位5症状は肩こりが1位、腰痛が2位であるため、女性用新ブランドの潜在ニーズは高いでしょう。
今後は、ワークマンとのコラボレーションや、市場拡大が見込まれるECでの売上の成長にも期待できます。
他にもスポーツ時のリカバリーや睡眠にフォーカスした商品開発等の取り組みを行う計画で、これらが奏功すれば、今後も増収増益基調が続く可能性は高いと考えられます。
2.第一工業製薬(4461)
第一工業製薬
| 銘柄コード | 4461 |
|---|---|
| 上場市場 | 東証プライム |
| 株主優待 | 自社製品 |
| 予想配当利回り | 3.87%(2025年5月) |
専門家おすすめポイント
- ゆるやかな増配傾向となっている
- 長期保有により、配当と株主優待のインカムゲインだけでなく、キャピタルゲインの獲得にも期待できる
第一工業製薬は界面活性剤などの化学製品のメーカーで、化粧品や食品、IT・電子材料などに活用する化学製品を製造しています。
ゆるやかな増配傾向が続いており、2008年3月期以降無配はなく、2025年3月期は年間90円の配当予想です。
株主優待は、ライフサイエンス関連商品の株主優待特別販売クーポンと、保有株式数に応じて株主優待ポイントがもらえます。
- 100 株 〜299 株:1,000ポイント
- 300 株 〜 499 株:3,000ポイント
- 500 株 〜 999 株 :5,000ポイント
- 1,000 株以上: 6,000ポイント
※参考:第一工業製薬公式サイト(2025年5月2日時点)
獲得した株主優待ポイントは、「第一工業製薬プレミアム優待倶楽部(株主限定の特設サイト)」で、自社製品(消臭・除菌スプレー「NIOCAN」 スプレーボトルや、機能性表示食品「快脳冬虫夏草」など)のほか、お米やブランド牛などのグルメ、スイーツや飲料類、選べる体験ギフトなど4,000種類以上の商品から選ぶことができます。
※株主優待の内容については適宜変更される場合があるため、公式サイトなどでご確認ください。

佐藤 真奈美/証券外務員1種
第一工業製薬の2023年2月期は減収減益となり、減損損失の計上によって四半期純利益は赤字となりました。
2022年3月期までを不採算事業見直しによる事業再編の前半2年と位置付け、経営改善に努める方針です。
原油価格やナフサ価格の高騰も一服し、2023年3月期以降は取り組みの効果が出てくると考えられます。
なお、第一工業製薬はLiB(高容量リチウムイオン二次電池)の負極用水系複合接着剤の開発を2022年12月に発表しています。
LiBは黒鉛が主流で、高容量実現のためにシリコン系材料を添加しますが、放電で収縮すると電池を劣化させます。
第一工業製薬が開発した接着剤はこの問題をクリアし、電池の長寿命化を実現しています。
民生向けに市場投入した後に車載用に投入する方針で、需要の大幅増加が見込まれることから、業績拡大を牽引する可能性が考えられます。
長期で保有し、インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を狙いたい銘柄です。
3.エスイー(3423)
エスイー
| 銘柄コード | 3423 |
|---|---|
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 株主優待 | 防災用品 |
| 予想配当利回り | 4.87%(2025年5月) |
専門家おすすめポイント
- インカムゲインだけでなく、長期的な株価上昇によるキャピタルゲインの獲得に期待できる
- 災害への備えができる
エスイーは建設・建築用の資材機の製造・販売を行う会社です。
株主優待では防災用品で、非常食や非常用持ち出し袋、携帯用トイレなど、万が一の時に役立つラインナップとなっています。
なお、株主優待は2,000株以上保有の株主に対し実施されることに注意が必要です。
1株あたりの株価が2025年5月2日前日終値の株価は267円ですので、20単元の購入に必要な資金は53万円程度となります。
保有期間が3年未満で1,000円相当、3年以上で3,000円相当の優待品を贈呈しています。
※株主優待の内容については適宜変更される場合があるため、公式サイトなどでご確認ください。

佐藤 真奈美/証券外務員1種
エスイーはアンカーやKIT受圧板など建設用資材の製造・販売を行う会社です。
売上高は概ね増収が続いているものの、前年の大型・高収益案件の剥落に加え、足元では原材料価格の高騰や人件費増加などにより利益面では苦戦しています。
エスイーは今後、市場規模の大きいESCONスラブ(道路橋床版)等大規模修繕等を中心とした橋梁補修関連に開発資源を集中する方針です。
日本の公共工事関係費の合計額はピーク時には程遠い状況ですが、防災・減災・老朽化対策など国土強靭化計画関連については、予算概算要求額以上の予算が確保されていることから、この分野の需要は堅調に推移するでしょう。
国土交通省は、全国にある約72万の橋梁のうち、2019年時点で3割弱が建設から50年が経過し、2029年には5割を超えるとの見通しを立てています。
エスイーが注力する方針の橋梁補修関連の堅調な需要が続くとみられるため、中長期的な成長に期待したい銘柄です。
4.ニッスイ(1332)
ニッスイ
| 銘柄コード | 1332 |
|---|---|
| 上場市場 | 東証プライム |
| 株主優待 | 自社商品 |
| 予想配当利回り | 3.24%(2025年5月) |
専門家おすすめポイント
- 家計が助かる優待内容
- 配当目的の人にも向いた銘柄
食料品でおなじみのニッスイの株主優待は自社製品で、缶詰やレトルト食品などを贈呈しています。
なお、株主優待は500株以上から実施している点に注意が必要です。
1株あたりの株価が2025年5月2日前日終値の株価は863.4円なので、500株の購入に必要な資金は43万円以上となります。
保有株数が500株以上1,000株未満で3,000円相当、1,000株以上で5,000円相当の優待品を贈呈しています。
長期保存ができる食品なので、一人暮らしの人も家族と同居している人も、非常に助かる優待内容でしょう。
※株主優待の内容については適宜変更される場合があるため、公式サイトなどでご確認ください。

佐藤 真奈美/証券外務員1種
ニッスイの2023年3月期2Qは、増収減益となりました。
水産市況高や漁獲量の増加といった一過性の要因で減益になりましたが、市場予想を大幅に上回りました。
一方で、ニッスイのファインケミカル事業や食品事業は苦戦しています。
ファインケミカル事業は顧客の在庫調整の長期化が予想されているため、来期は食品事業が追加値上げの影響をどの程度受けるかが焦点となるでしょう。
ニッスイは今後、養殖事業やファインケミカル事業等の成長と差別化を加速させる方針です。
代替タンパク質や水産養殖など、注力する分野は長期的な需要拡大が見込まれます。
また、ファインケミカル事業の苦戦の一因となった米国向け高純度EPA医薬品原料は、同国のDHA・EPAの市場拡大が続いているため、輸出が再開すれば業績拡大に貢献するとみられます。
現在準備を進める欧州への輸出も実現すれば、同エリアの売上も積み増しされ、長期的な成長が見込めるでしょう。
5.森下仁丹(4524)
森下仁丹
| 銘柄コード | 4524 |
|---|---|
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 株主優待 | 自社製品詰め合わせ |
| 予想配当利回り | 2.66%(2025年5月) |
専門家おすすめポイント
- 優待内容が充実している
- 配当目的の人にも向いた銘柄
ロングセラー商品の口中清涼品「仁丹」で知られる森下仁丹の株主優待は、仁丹やサプリメントなどです。
100株以上で株主優待が実施され、100株以上は税抜3,500円相当の自社製品、200株以上保有することで税抜7,000円相当にグレードアップし、3種類の詰め合わせの中から1つを選択するか、社会貢献団体への寄付を選ぶことができます。
さらに、400株以上保有すると200株以上保有の優待内容に加え、税抜3,000円相当の自社製品が贈呈されます。
健康に気をつかいたい人はもちろん、優待内容も配当も実施しているので、インカムゲイン目的で保有したい人におすすめの銘柄です。
※株主優待の内容については適宜変更される場合があるため、公式サイトなどでご確認ください。

佐藤 真奈美/証券外務員1種
森下仁丹は、ジェネリック医薬品分野で高脂血症用剤の販売を2022年6月に開始したことなどから、2023年3月期2Qは増収増益となり、営業利益以下の利益は全て通期会社計画を超過しています。
しかし森下仁丹は会社計画を据え置いています。
今期は会社計画を上回る見通しですが、原材料や燃料の高騰によってどの程度の上振れになるのか注目したいところです。
森下仁丹はシームレスカプセル技術に強みがあり、産業用カプセルへの応用も進め、レアメタルイオンの含まれる産業排水などの中からレアメタルを高効率で回収する技術を研究しています。
日本はレアメタルを輸入に頼っていますが、レアメタルはEVやIT製品、省エネ化に欠かせず、将来的に需要が供給を上回る見通しのものもあります。
産業用カプセルが開発された場合、レアメタルのリサイクルにつながるため、大きな需要があると考えられるのです。
長期的な業績成長に期待できる銘柄と言えます。
新NISAの始め方
新NISAを始めるために必要な手順は、以下の通りです。

口座開設を行う際には、本人確認書類やマイナンバーカードの提出が必要となるため、手元に用意した状態で申し込みを行うとスムーズです。
また、開設する口座を決めていない方は、新NISAのおすすめ証券会社を参考にしてください。
新NISAのおすすめ証券会社
新NISAに利用できる金融機関は、一人あたりひとつに限られます。
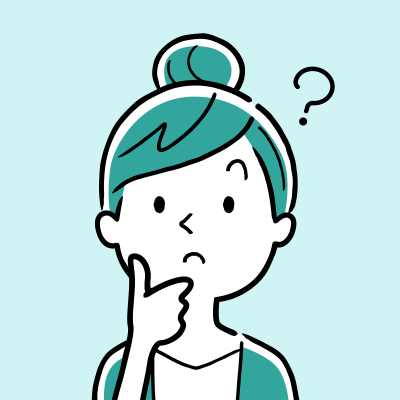
いろいろな金融機関で新NISAができるけど、どこを選べばいいの?
選べる商品数やサービスが充実している「ネット証券」がおすすめです。
特におすすめできるネット証券を3社紹介します。

※当記事で紹介するおすすめ証券会社は「証券会社ランキングの算定基準」をもとに選定しています。
SBI証券
※画像引用元:【SBI証券】NISA口座開設|ネット証券のリーディングカンパニー
SBI証券は国内大手ネット証券の一角で、投資できる商品ラインナップが非常に豊富です。
手数料面も充実しており、NISA口座での国内・米国株(海外ETF含む)、投資信託の売買手数料を無料に設定されています。
投資信託の保有でVポイント、dポイント、Pontaポイント、JALマイル、PayPayポイントの中から貯まるポイントを選べる点もSBI証券の魅力です。
※2025年5月時点
また、投資信託の積立買付にクレジットカード決済(クレカ積立)にも対応しており、積立金額に応じたVポイントが貯まります。
総合力に優れた証券会社なので、どこにするか迷ったらSBI証券を選ぶと良いでしょう。

楽天証券

国内大手ネット証券のひとつである楽天証券は、証券会社単体で国内最多となる1,200万超(※)の証券総合口座数を有しています。
※2025年1月時点(2025年5月公式サイトにて確認)
また、NISA口座開設数は第1位(※)といわれています。
※日本証券業協会「NISA口座の開設・利用状況」および各社公表資料より算出(2024年9月末時点)(楽天証券公式サイトより)

多くのユーザーに選ばれている理由として、早期から安価な取引手数料を実現したことや、投資信託や外国株式の取扱銘柄数の多さ、ポイント投資などによって手軽な投資をサポートしていることなどが挙げられます。
楽天サービスを普段使いする人は、楽天証券を選ぶとより効率よく楽天ポイントを貯めて、使うことができるでしょう。

現金1,000円もらえるキャンペーンも実施中
松井証券
※画像引用元:スマホ0円で日本株 手数料0円から | 松井証券
松井証券は、大手ネット証券の中でも最も長い歴史を持つネット証券です。
松井証券は投資信託の保有に対するポイント還元に定評があり、実際に投資信託の信託報酬の一部を現金またはポイントで還元する業界初のサービスも扱っています。
※還元されるのは松井証券受け取り分の信託報酬のうち0.3%を超過した分
投資信託の保有残高に対して還元されるポイント倍率も業界最高水準に設定されています。
※参照元:【業界最高還元率!】「最大1%貯まる投信残高ポイントサービス」開始のお知らせ | 松井証券
さらに、2025年5月からクレカ積立サービスの提供が始まり、JCBオリジナルシリーズの各券種の利用で、最大1.0%のOki Dokiポイントの還元が受けられます。
※参照元:クレカ積立プレデビューキャンペーン | 松井証券
なお、クレカ積立のサービス開始を記念して、条件を達成するとポイント還元率が最大7.0%になるキャンペーンも開催(終日未定)しています。
※2025年5月現在(参照元:松井証券公式サイト)
他の大手ネット証券と同じく、NISA口座による国内・米国株や投資信託の取引手数料は無料です。
アクティブファンドなど、信託報酬が比較的高いファンドを購入したい人におすすめの証券会社です!

よくある質問
NISA口座は証券会社・銀行のどちらで作るのが良い?
おすすめは証券会社です。
NISA口座は証券会社以外にも、銀行や郵便局などでも作ることができますが、利便性を考えると証券会社が最もおすすめです。
特に、ネット証券は取扱商品数も豊富で、100円という少額から投資を始められるため、初心者にもおすすめできます。
※1 日本証券業協会「NISA口座の開設・利用状況」および各社公表資料より算出(2024年9月末時点)
※2 2023年3月期 通期(2022年4月~2023年3月)の委託個人売買代金シェアです。SBIの数値は、SBIネオトレード証券の数値を含みます。(出所:東証統計資料、各社WEBサイトの公表資料より当社集計、各社委託個人(信用)売買代金÷{株式委託個人(信用)売買代金(二市場1,2部等)+ETF/REIT売買代金}にて算出)。
成長投資枠・つみたて投資枠の違いは?
成長投資枠とつみたて投資枠の主な違いは以下の通りです。
| 成長投資枠 | つみたて投資枠 | |
|---|---|---|
| 年間投資上限額 | 240万円 | 120万円 |
| 対象商品 | 株式 ETF 投資信託 | 投資信託 |
成長投資枠とつみたて投資枠は併用可能なので、特徴を踏まえてうまく利用していきましょう。

まとめ
2024年1月からNISA制度は一新されより使い勝手のよい制度となったことで、NISA口座数は増加傾向にあります。
成長投資枠(以前の一般NISA)とつみたて投資枠(以前のつみたてNISA)の併用が可能になったり、非課税期間が撤廃されたりと、投資を行うならぜひとも利用したい制度です。
本記事で紹介した内容をもとに、ぜひ利用してみてください。

※1 日本証券業協会「NISA口座の開設・利用状況」および各社公表資料より算出(2024年9月末時点)
※2 2023年3月期 通期(2022年4月~2023年3月)の委託個人売買代金シェアです。SBIの数値は、SBIネオトレード証券の数値を含みます。(出所:東証統計資料、各社WEBサイトの公表資料より当社集計、各社委託個人(信用)売買代金÷{株式委託個人(信用)売買代金(二市場1,2部等)+ETF/REIT売買代金}にて算出)。






























