
新NISA(つみたて投資枠)の分配金は再投資と受取のどっちがおすすめ?いつもらえるかや非課税かも解説
最終更新日:
このページにはPRリンクが含まれています
また当サイトで得た収益は、サイトを訪れる皆様により役立つコンテンツを提供するために、情報の品質向上・ランキング精度の向上等に還元しております。※提携機関一覧
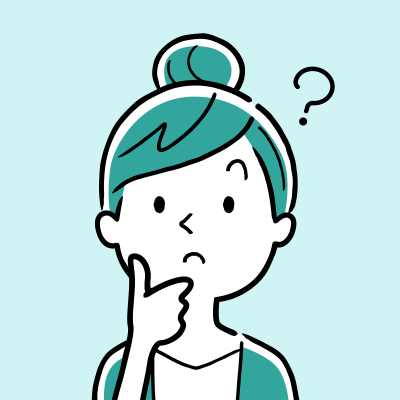
- 新NISA(つみたて投資枠)の分配金はどうすればいいの?
- 分配金を再投資した場合と受け取った場合とでは何が違うの?
新NISA(つみたて投資枠)で投信積立を行う場合、分配金について上記の疑問を抱く人もいるのではないでしょうか?
長期的な運用を考えた場合には、分配金は再投資したほうがいいでしょう。
しかし、場合によっては受け取ったほうがいいケースもあります。
再投資と受取について、それぞれのメリットとデメリットを知らずにいると、「分配金がもらえると思っていたのにもらえない」「思ったほど運用益が出ない」など、想定外の事態が起こるかもしれません。

本記事を読むことで、自分の運用方針と照らし合わせたうえで、分配金を再投資するのか、あるいは受け取るのか、適切な判断を下せるようになります。ぜひ最後までお読みください。
\NISAのおすすめ口座/
【掲載情報について】
2024年5月8日時点の情報を掲載しています。

スキラージャパン株式会社 代表取締役 / スキラージャパン株式会社
監修者伊藤亮太
伊藤亮太は「スキラージャパン株式会社」の取締役を務めるFP(ファイナンシャル・プランナー)。
慶應義塾大学大学院商学研究科経営学・会計学専攻を修了しており、在学中にCFP®を取得。
その後、証券会社にて営業・経営企画・社長秘書・投資銀行業務に携わる。
現在は富裕層個人の資産設計を中心としたマネー・ライフプランの提案・策定・サポート等を行う傍ら、資産運用に関連するセミナー講師や講演を多数行う。
▼書籍
7日でマスターNISA&iDeCoがおもしろいくらいわかる本
図解即戦力 金融のしくみがこれ1冊でしっかりわかる教科書
ゼロからはじめる! お金のしくみ見るだけノート
株で勝ち続けるための 上がる銘柄選び黄金ルール87
など
株式会社エイチームライフデザイン
編集者イーデス編集部
「ユーザーが信頼して利用できるWEBメディア」を目指す編集部チーム。実際のユーザーの声や業界知識の豊富な専門家の協力を得ながら、コンテンツポリシーに沿ったコンテンツを制作しています。暮らしに関するトピックを中心に、読者の「まよい」を解消し、最適な選択を支援するためのコンテンツを制作中です。
■書籍
初心者でもわかる!お金に関するアレコレの選び方BOOK
■保有資格
KTAA団体シルバー認証マーク(2023.12.20~)
■許認可
有料職業紹介事業(厚生労働大臣許可・許可番号:23-ユ-302788)
気になる内容をタップ
新NISA(つみたて投資枠)の分配金とは?
新NISA(つみたて投資枠)で運用する投資信託の中には分配金が出るものがあります。
一見すると、預貯金の利息や株式の配当金と同じようなものに思えるかもしれませんが、少々異なります。
預貯金の利息は予め決められた利率に応じて支払われるのに対し、分配金の特徴は運用成績に応じて金額が変化する点です。
また、株の配当金は企業が稼いだ利益を株主に還元するもので、分配金と似ています。
ただ、配当金は投資先企業が株主に支払うのに対し、分配金は販売会社から購入者に支払う、という点に違いがあります。
また、分配金の場合には、収益ではなく運用資産の一部を取り崩して支払うケースがある、という点も配当金とは異なるのです。
なお、分配金はどの投資信託でも必ず出るというわけではなく、投資信託ごとに異なります。
定番の投資信託では分配金がないものが多い
前述したとおり、新NISA(つみたて投資枠)口座で運用できる投資信託の中には、分配金が出るものと出ないものとがあります。
実は、新NISA(つみたて投資枠)で購入されている王道の投資信託は、分配金が出ないものが多いのです。
例えば、楽天証券の「NISAランキング(積立件数)」のトップ10は、すべて分配金の出ない投資信託です。
したがって、楽天証券で「新NISA(つみたて投資枠)でよく購入されている投資信託を選びたい」という場合には、いずれを選択しても分配金は出ないということになります。
また、SBI証券の投信パワーサーチを利用して新NISA(つみたて投資枠)で運用できる投資信託を探した場合も、新NISA(つみたて投資枠)対象銘柄225件のうち、221件が設定以来分配金を出していない投資信託となっています(2024年4月27日現在)。
このように、新NISA(つみたて投資枠)で運用できる投資信託の大多数が、分配金が出ません。
その理由として、新NISA(つみたて投資枠)で運用可能な投資信託については、資産形成が可能なように、分配金の支払い頻度が低いものを金融庁が選定していることが挙げられます。
具体的な新NISAのおすすめ銘柄は、以下の記事で紹介しています。
つみたて投資枠は個別株式に投資できない
新NISA(つみたて投資枠)の投資先は、金融庁が指定している「長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託」に限られます。そのため、個別株式には投資できません。
新NISAには、つみたて投資枠の他に「成長投資枠」があり、そちらであれば個別株式にも投資できます。
しかし、成長投資枠では非課税保有限度額が1,200万円と、つみたて投資枠の1,800万円よりも600万円少ない点には注意が必要です。
成長投資枠でも毎月分配型の投資信託は購入できない
投資信託には、以下の2種類があります。
- 毎月分配型:毎月分配金がもらえる
- 隔月分配型:2ヶ月に1回分配金がもらえる
旧NISAはどちらの投資信託も購入できました。しかし、新NISAは、つみたて投資枠だけでなく成長投資枠でも、毎月分配型の投資信託は購入できません。
先述したように、新NISAの投資先は金融庁が指定しているものに限られますが、毎月分配型はその中に含まれていないのです。
隔月分配型の投資信託は引き続き購入可能です。
新NISA(つみたて投資枠)の分配金は非課税
旧つみたてNISAと同様、新NISA(つみたて投資枠)の分配金も非課税です。
NISA口座以外の投資信託や株式投資で得られた利益は、譲渡益だけでなく配当金や分配金にも20.315%の税金が課されます。
例えば、100万円の利益を得た場合でも、約20万円が税金として引かれ、手元に残るのは約80万円です。
しかし、新NISA(つみたて投資枠)であれば、譲渡益・配当金・分配金が非課税となり、100万円すべてを自分の資産として受け取れます。投資する立場から見ると大きなメリットと言えるでしょう。
注意点として、配当金の受け取り方には以下のように複数ありますが、非課税にするためには「株式数比例配分方式」を選択しなければなりません。
配当金の受け取り方
- 株式数比例配分方式
- 配当金領収証方式
- 登録配当金受領口座方式 など
参照:NISA口座における上場株式の配当金等受取方式に関する注意事項 | 日本証券業協会
現在利用している証券口座の受け取り方が「株式数比例配分方式」以外であれば、分配金が非課税にならないため、新NISA(つみたて投資枠)への投資を始める前に変更しておきましょう。
金融機関によっても異なりますが、ホームページから変更できることが多いので、確認してみてください。
新NISA(つみたて投資枠)の分配金コースは「再投資」がおすすめ!
新NISA(つみたて投資枠)で投資信託を運用する場合には、新NISA(つみたて投資枠)の分配金コースを「再投資」にすることをおすすめします。
なぜなら、複利効果が期待できるからです。
分配金を受け取らずにそのまま再投資に回せば、運用する元手が増加し、「利益が利益を生む」という複利効果の恩恵を受けられます。
ただし、長期投資をする場合には、「分配金なし」の投資信託が最適です。
分配金なしの場合には「特別分配金」がないため、自身の運用資産を取り崩す心配がありません。
また、分配金の支払いがないため、投資信託の純資産総額を減らすことがなく、投資効率が低下しない点もメリットです。
さらに、途中で分配金受け取りに変更してしまう心配がないこともメリットといえるでしょう。
分配金を受け取るようになったために運用資産を増やせず、利益が思ったほど出ない、という事態を回避できます。
新NISA(つみたて投資枠)の分配金コースの再投資と受取の違いを徹底比較
新NISA(つみたて投資枠)で長期的な資産形成を目指すのであれば、分配金コースは「再投資コース」を選ぶことをおすすめします。
一方投資から受け取れる収入を重視したい、という場合には「受取コース」を選ぶといいでしょう。
それぞれの詳細を説明します。
複利を活かすなら【再投資コース】
最低でも10年以上かけて資産形成をしたい、と考えている場合には、「再投資コース」を選びましょう。
なぜなら、複利効果の恩恵が受けられるからです。
既述したとおり、分配金を受け取らずに再投資に回すことで、投資元本に分配金が加わるため運用資産が増えます。
運用がうまくいけば、投資元本だけでなく分配金も利益を生むことになるため、受け取る利益が大きくなるのです。
たとえ1回あたりの分配金額が少なくても、コツコツと再投資に回すことで、分配金は積みあがっていきます。
長い時間が経った時には、結構な金額の分配金を再投資に回したことになり、それらが利益を生むのです。
したがって、10年以上の長期にわたり資産形成をしたい場合には、分配金は受け取らずに再投資に回し、時間を味方につけて「利益が利益を生む」という複利効果を享受するといいでしょう。
長期の資産形成より投資からの収入重視なら【受取コース】
定期的な副収入を得るために投資信託を運用したい、という場合には、「受取コース」を選ぶことをおすすめします。
なぜなら、「再投資コース」を選んでしまうと、投資信託を売却しない限り分配金がもらえないからです。
投資からの収入を得ることを目的に投資信託を運用する場合には、「受取コース」を選びましょう。
新NISA(つみたて投資枠)の分配金受取・再投資のメリット・デメリット
新NISA(つみたて投資枠)の分配金受取・再投資のメリット・デメリットと、向いている人の特徴は以下の通りです。
| 分配金受取 | 分配金の再投資 | |
|---|---|---|
| メリット | 定期的な収入が期待できる | 複利効果を得られる |
| デメリット | 複利効果がなく長期の資産形成に不利 | 売却しない限り資産所得を得られない |
向いている人 | ●資産運用によって短期・中期的な収入を得たい人 ●退職間近の人や退職した人 | ●10年以上の長期運用をしたいと考えている人 ●若い世代や現役世代の人 |
以下ではそれぞれ詳しく解説します。
分配金受取のメリット・デメリット
分配金受取にはどのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。
それぞれの詳細を解説します。
分配金受取のメリット
分配金受取のデメリット
メリット:定期的な収入が期待できる
分配金受取のメリットとして、運用を続けながら定期的な収入を得られることが挙げられます。
分配金を受け取るためには、決算日の前営業日時点で、その投資信託を約定していなければなりません。
上記条件をクリアしている場合は、決算後に分配金を受け取ることが可能です。
株の配当や株主優待のような定期収入を得られることになり、毎月の生活費に上乗せができる点がメリットです。
デメリット:複利効果がなく長期の資産形成に不利
分配金受取のデメリットとして、複利効果が得られないことが挙げられます。
すでに書いたとおり、複利効果とは利益が利益を生み、雪だるま式に増えていくことをいいます。
分配金を再投資に回さずに受け取ってしまうと、投資元本は増えません。
その分、投資効率が下がってしまい、長期的な資産形成には不利になります。
分配金受取が向いている人
既述したとおり、分配金受取のメリットは定期収入が得られることです。
したがって、長期での資産形成よりも、資産運用によって短期・中期的な収入を得たい、という人に向いています。
また、資産形成に時間をかけたくない、あるいはかけられないという人は、分配金受取を選択することを考えてもいいでしょう。
分配金受取は、ライフプランの変化に備えて資産形成をしなければならない若い世代よりも、退職間近の人や退職した人のほうが向いているといえます。
分配金を再投資するメリット・デメリット
分配金を再投資するメリットとデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。
それぞれの詳細を説明します。
分配金受取のメリット
分配金受取のデメリット
メリット:複利効果を得られる
分配金を再投資する一番のメリットは、複利効果を得られることです。
分配金を再投資することによって運用資産が増え、利益が利益を生みます。
再投資の期間が長ければ長いほど、再投資した場合としなかった場合とでは、得られる利益に大きな差が生じるのです。
下表は、100万円を年利5%で運用し、再投資しなかった場合と再投資をした場合とで、運用年数によって利益にどのくらいの差が出るのか示したものです。
運用期間が長期になるほど、複利効果によって単利よりもリターンが大きくなることが分かります。
| 銘柄名 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 |
|---|---|---|---|---|
単利 | 1,250,000円 | 1,500,000円 | 1,750,000円 | 2,000,000円 |
複利 | 1,276,000円 | 1,628,895円 | 2,078,928円 | 2,653,298円 |
利益の差 | 26,282円 | 128,895円 | 328,928円 | 653,298円 |
デメリット:売却しない限り資産所得を得られない
分配金を再投資するデメリットとして、売却をしない限り利益が受け取れないことが挙げられます。
運用がうまくいき、資産が増加していても、運用期間中は現金化されません。
ゆえに、資産が増加していることを頭では理解していても、実生活において、「運用がうまくいったおかげで、資産が増えて生活が豊かになっている」と感じる機会はほとんどないでしょう。
実感するのは、売却して運用を終え、資産所得を得た時です。
それまではなかなか実感しづらい点が短所といえます。
再投資が向いている人
分配金の再投資が向いている人は、途中で資産を取り崩すことをせず、10年以上の長期運用をしたいと考えている人です。
具体的には、若い世代や現役世代の人が向いています。
なぜなら、リタイアするまでに十分な時間が残されているからです。
定期預金や保険など元本保証された金融商品で、結婚や子どもの誕生等さまざまなライフプランの変化に備えておき、それにプラスする形で新NISA(つみたて投資枠)で投信積立を行うことをおすすめします。
万が一の場合や老後に備えて十分な資産を用意するためにも、分配金を再投資して、長期的な資産形成を目指しましょう。
複利効果をさらに高めるなら分配金がない投資信託一択!
複利効果を活かし、時間をかけて資産形成をしていきたいのであれば、「分配金なし」の投資信託がおすすめです。
なお、「分配金なし」とは分配金が絶対に出ないことを意味しているのかというと、決してそうではありません。
実は、完全な無分配の投資信託は、運用期間があらかじめ定められ、かつ設定前の募集期間のみ購入可能な投資信託のうち、一部のものにしか認められていません。
「分配金なし」の投資信託はいつでも購入可能であり、運用期間が定められていない無期限のものもあります。
したがって、完全な無分配ではなく、年に何回も決算を行う投資信託よりも分配金が支払われる可能性が低い、ということでしかないのです。
「分配金なし」の投資信託で、もしも分配金が出た場合には、分配金を払い出す前に再投資を自動で行ってくれます。
ファンド内で自動的に再投資してくれるため、投資枠を使って再投資することがなく高効率である点がメリットです。
また、信託報酬も安い傾向にあります。
実際に「分配金なし」の投資信託を選ぶ際には、新NISA(つみたて投資枠)でよく購入されているものを参考にするといいでしょう。
すでに書いたとおり、新NISA(つみたて投資枠)でよく購入されている投資信託は「分配金なし」のものが多いのです。
楽天証券のように、証券会社によっては、新NISA(つみたて投資枠)で人気の投資信託人気ランキングをHPに掲載しているところもあるので、選ぶ際に参考にするといいでしょう。
>>NISAランキング(積立件数)|楽天証券
公式サイトはこちら
【ここで差がつく!】新NISA(つみたて投資枠)をさらに効率的に運用する方法
新NISA(つみたて投資枠)で投資信託を購入する際に注意したいのが、買い方によってお得さの度合いが変わる、という点です。
同じ口座で同じ商品を同じタイミングで購入した場合、買い方次第でよりお得になるケースがあります。
楽天証券の場合 | マネーブリッジと楽天カード決済を使う

楽天証券の新NISA(つみたて投資枠)口座で投信積立をする場合の支払い方法の中には、楽天カードによるカード決済があります。
カード決済は毎月購入するたびに楽天ポイントが付与されるため、証券口座からの引き落としによって購入代金を支払うよりもポイントを効率よく貯められます。
また、楽天証券には、楽天証券口座と楽天銀行口座を連携するマネーブリッジというサービスがあり、楽天カードによるカード決済を併用すると、よりお得に投資信託を購入可能です。
投資信託を購入する際にカード決済を利用すると、2023年6月買付分から、これまで0.2%だったポイント還元率が0.5%に引き上げられます。
貯めた楽天ポイントは投資信託の購入に使用可能です。
さらに、楽天銀行の普通預金の金利は年0.02%です。
大手都市銀行の普通預金の金利は年0.001%であるため、楽天銀行の金利は20倍も高いことが分かります。
したがって、楽天銀行に預金しておくだけでも、金利面でお得といえるでしょう。
なお、楽天銀行口座を楽天カードの引き落とし口座に設定すると、普通預金の金利は年0.04%に、マネーブリッジを利用すると金利は年0.1%までアップするので、併せて利用するといっそうお得に利用できます。
楽天証券の公式サイトはこちら
SBI証券の場合 | 三井住友カードで決済を行う

SBI証券で新NISA(つみたて投資枠)口座を開設して投信積立を行う場合には、毎日・毎週・毎月の中から積立頻度を決められます。
できるだけ時間分散をさせて投信積立を行いたい、という場合の選択肢が広い点がメリットです。
また、SBI証券では三井住友カードと提携して、投資信託や国内株式などの取引に応じてVポイントが貯まる「SBI証券Vポイントサービス」というサービスを提供しています。
三井住友カードを使用すれば、投信積立の購入代金をクレジットカードで決済することができます。
一般NISAや新NISA(つみたて投資枠)で投信積立を行う場合にも、三井住友カードによるクレジットカード決済が可能です。
貯まったVポイントは、1ポイント1円分として、投資信託の購入に使用できます。
さらに、クレジットカード決済で投信積立を行う「クレカ積立」の場合、VポイントだけでなくPontaポイントやdポイントをもらうことも可能です。
購入額に応じてVポイントが付与され、投資信託の保有残高に応じた「マイレージサービス」において、選べるポイントが付与されます。
※メインポイントに設定しているポイントが付与されます
公式サイトはこちら
新NISA(つみたて投資枠)の分配金についてよくある質問
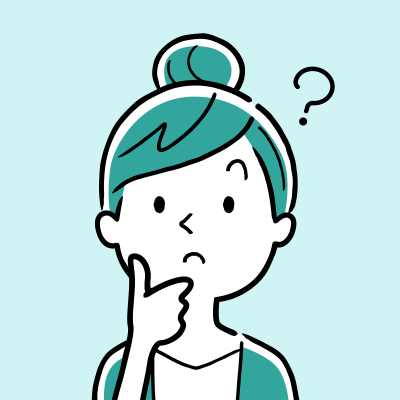
新NISA(つみたて投資枠)の分配金に対し、どのような疑問を持つ人が多いのでしょうか?
新NISA(つみたて投資枠)の分配金に関するよくある質問とその回答を紹介します。

分配金の再投資で投資枠120万円を超えるとどうなる?
新NISA(つみたて投資枠)には年間120万円という非課税投資枠が決められていますが、分配金の再投資などが原因で、非課税投資枠を超えてしまうケースもあります。
上記の場合には、課税口座で再投資を行うことになります。
新NISA(つみたて投資枠)の分配金はいつもらえる?
新NISA(つみたて投資枠)の分配金がもらえるタイミングは、証券会社によって異なります。
例えば、SBI証券の場合は、決算日の翌日に受け取り可能で、買付余力に反映されます。
楽天証券の場合には受け取りは決算日の5営業日後です。
以上のように証券会社によって異なるため、分配金の受け取りタイミングを知りたい場合には、利用している証券会社に確認しましょう。
新NISA(つみたて投資枠)の分配金はどのくらいもらえる?
分配金額は決算ごとに決定するため、決算の回数が年にどれくらいあるかによって、もらえる頻度と金額が変わります。
なお、新NISA(つみたて投資枠)で運用できる投資信託の場合、決算が年1回、年2回など頻度の低いものを金融庁が選定しています。
支払われる分配金の額は投資信託ごとに異なるため、トータルでどのくらいもらえるのかは、各投資信託の詳細を確認して計算しましょう。
まとめ
新NISA(つみたて投資枠)で投資信託の運用をし、分配金が出た場合に、どうすればいいのか悩む人もいるかもしれません。
「できるだけ投資効率を上げて長期的な運用をしたい」「リタイアした時に、まとまった資産が受け取れるようにしたい」という人は、複利効果を得られる再投資を選びましょう。
特に、若い世代はリタイアするまでに十分な時間があるため、時間を味方につけて複利効果の恩恵を得られます。
反対に、「資産形成よりも定期的な収入がほしい」という場合には、受取を選ぶことをおすすめします。
すでにある程度の資産を形成したリタイア世代などは、受取を選んでも問題ないでしょう。
なお、楽天証券やSBI証券で新NISA(つみたて投資枠)を行う場合には、よりお得に運用できるカード決済を利用することをおすすめします。
























