
資産運用おすすめランキング|初心者向け・年代・投資金額別の投資方法を紹介!
最終更新日:
このページにはPRリンクが含まれています
また当サイトで得た収益は、サイトを訪れる皆様により役立つコンテンツを提供するために、情報の品質向上・ランキング精度の向上等に還元しております。※提携機関一覧
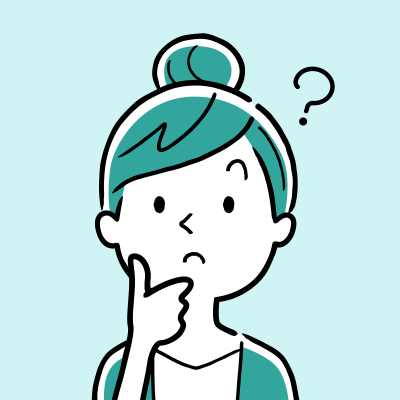
- おすすめの資産運用方法ってなに?
- 資産運用初心者は何から始めればいいの?
初心者におすすめの資産運用方法は以下のとおりです。
初心者におすすめの資産運用
記事内では年代別、投資金額別、目的別にもおすすめの資産運用を紹介しています!

ただし、考えなしに資産運用を始めても思った結果は得られません。
始める前に、資産運用に資金をいくら回せるか、どれぐらいの利益を狙いたいかなど整理して、それに合った方法を選ぶようにしましょう。
この記事では、初心者向けのおすすめ資産運用ランキングやタイプ別のおすすめ資産運用方法も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
【掲載情報について】
2024年5月1日時点の情報を掲載しています。

スキラージャパン株式会社 代表取締役 / スキラージャパン株式会社
監修者伊藤亮太
伊藤亮太は「スキラージャパン株式会社」の取締役を務めるFP(ファイナンシャル・プランナー)。
慶應義塾大学大学院商学研究科経営学・会計学専攻を修了しており、在学中にCFP®を取得。
その後、証券会社にて営業・経営企画・社長秘書・投資銀行業務に携わる。
現在は富裕層個人の資産設計を中心としたマネー・ライフプランの提案・策定・サポート等を行う傍ら、資産運用に関連するセミナー講師や講演を多数行う。
▼書籍
7日でマスターNISA&iDeCoがおもしろいくらいわかる本
図解即戦力 金融のしくみがこれ1冊でしっかりわかる教科書
ゼロからはじめる! お金のしくみ見るだけノート
株で勝ち続けるための 上がる銘柄選び黄金ルール87
など
イーデス編集部 / 株式会社エイチームライフデザイン
編集者板橋 辰汰郎
1998年生まれ、兵庫県川西市出身。
大学卒業後、2021年に新卒として株式会社エイチームフィナジーに入社し、ナビナビ証券、イーデスの編集者に就任。
▼書籍
初心者でもわかる!お金に関するアレコレの選び方BOOK
気になる内容をタップ
資産運用とは?
資産運用とは、自身の持つ資産を預貯金や投資により増やすことを指します。
例として、以下のようなものが挙げられます。

資産運用方法の一例
- 株式
- 投資信託
- 債券
- 不動産円預金
- 外貨預金
- 保険
株式や不動産の場合はまとまった資金が必要なので、資金額によっては投資先の選択肢に入らないケースもあるでしょう。
一方、投資信託や保険のように、毎月積立をしながら資産運用できるものもあります。
円預金は多くの人にとってなじみ深い資産運用方法ですが、日本は超低金利であるため、資産を大きく増やしにくいという問題があります。
資産運用を行う際は、資金額や運用目的、運用方法など多角的に検討し、自分の希望に近いものを選びましょう。

初心者におすすめの資産運用ランキング8選
これから資産運用を始めることを考えている初心者向けに、おすすめの資産運用方法をランキングで紹介します。
初心者におすすめの資産運用
①投資信託
投資信託とは、多くの投資家から集めた資金をひとまとめにし、運用のプロフェッショナルが株式や債券などを運用する投資商品です。
投資信託ごとに定められた運用方針に基づき複数の銘柄を運用するため、ひとつの商品を購入するだけで、数十~数千種類の銘柄に分散投資が可能です。
投資信託は、組入れられているひとつの銘柄が大きく値下がりしたとしても、他の銘柄の運用でカバーできるため、安定した運用が期待できます。
一方で、大きな値上がりもしにくいため、長い時間をかけてじっくりと値上がりを待つ投資方法に向いています。
②新NISA(つみたて投資枠)
NISAとは、長期・積立・分散投資を通じた資産形成を促すために創設された少額投資非課税制度です。
特定の金額・期間で得た利益にかかる税金が0円になるのがNISAの最大の魅力です。

運用できる商品は、金融庁が厳選した長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託やETFです。
2024年からスタートした新NISAの「つみたて投資枠」では年間120万円まで投資枠が設けられています。
まずはつみたて投資枠で投資を行い、さらに金額を増やせる場合は成長投資枠を利用しましょう。
③新NISA(成長投資枠)
2024年に開始した新NISAの成長投資枠は、つみたて投資枠と同じく特定金額・期間で得た利益に税金がかかりません。
投資方法はスポット投資のほかに積立投資も可能で、国内外の上場株式や投資信託、ETFやREITなどの幅広い金融商品に投資可能です。
つみたて投資枠を超えて投資を行いたい場合は、成長投資枠を活用しましょう。
④iDeCo
iDeCo(個人型確定拠出年金)とは、私的年金制度であり、国の年金とは別に自分で老後資金を作ることを目的としています。
加入が必須の公的年金とは異なり、加入するかは自分で決められ、原則65歳未満であれば加入が可能です。
iDeCoで運用できる金融商品は「投資信託」「定期預金」「保険商品」の3種類で、運用は自分で行い、得た利息や運用益は非課税になります。
毎月掛金を積み立てて運用し、積み立てた資金や運用益は60歳以降に受け取りが可能であり、受け取り時には所得控除が受けられます。
⑤ミニ株投資
ミニ株とは、株式を1株や10株単位で購入する投資方法です。
株式は単元(通常は一単元=100株)で取引されますので、1株1,000円の株式を購入するには、100株分である100,000円が必要です。
しかし、ミニ株であれば1株や10株といった単位で購入できるため、少額から株式投資を始められます。
ただし多くの場合、ミニ株では株主優待を受け取れない点に注意が必要です。

とはいえ、本来はまとまった資金が必要な株式の購入を少額から行える点は大きなメリットといえます。
⑥ポイント投資
ポイント投資は、クレジットカードやサービスを利用して貯めたポイントで投資を行うサービスです。
証券会社の口座とポイントサービスを連携させることで、ポイントで投資信託や株式を購入できます。
ポイントを購入代金に充てられるため、元手を抑えて始められる魅力があります。
運用した投資商品から得た売買益や配当金を現金で受け取れるのも大きなメリットです。

ただし、証券会社ごとに利用できるポイントは異なるため、ポイント投資をする際は、どのポイントがどの証券会社で使えるのかを確認しましょう。
⑦ロボアドバイザー
ロボアドバイザーは、AIが資産形成に関するアドバイスや投資商品の運用を行うサービスです。
対応内容で「アドバイス型」と「投資一任型」に分類されています。
アドバイス型の特徴
- 適切な資産バランスについてアドバイスをする
- 多くのサービスは無料であり、質問に対する利用者の回答に応じてポートフォリオを提案し、その通りに運用されているかチェックしてくれる
- 商品の選択や売買は利用者自身で行わなければならない
投資一任型の特徴
- 利用者の設定に応じて投資商品の運用を自動的に行う
- ほったらかしにしていても、運用開始時の商品選定から運用中のリバランスまで自動で行う
- 利用には預けている金融資産の約1%分程度の手数料が必要
- すべての取引を自動的に行うため、投資初心者が投資を学ぶ機会には結びつきにくい面もある
自分で運用を覚えたい人はアドバイス型、ほったらかしで運用したい人は投資一任型を選ぶといいでしょう。

⑧株式投資
株式投資は、企業が発行した株式と呼ばれる有価証券を購入する投資方法です。
株式は株式市場で売買でき、購入時よりも値上がりした状態で売却すれば利益を得られます。
また、売買益の他にも保有しているだけで受け取れる株主優待や配当金などの利益もある点が特徴的です。
まずは売買で利益を得ようと思わず、株主優待を目当てに購入するのもおすすめです。

株式投資に慣れ、勢いがある業界や伸びている銘柄などがわかるようになったなら、売買で利益を出すのを目標にするとよいでしょう。
なお、株式の売買は通常100株単位でしかできません。
銘柄によっては最低でも数十万円の資金が必要になりますので、まずは一株あたり数百円といった少額投資できる銘柄から始めるとよいでしょう。
前述のミニ株からスタートするのもおすすめです。

【年代別】おすすめの資産運用方法
年代によって投資の方針も変わりますので、選ぶ商品も変わってきます。
ここでは、年代別におすすめできる資産運用の方法をご紹介します。
【年代別】おすすめの資産運用方法
20代におすすめの資産運用
20代の投資には「新NISA」「iDeCo」といった非課税制度を利用した投資がおすすめです。
20代は他の年代に比べて大きな資金が動かせない一方、時間は豊富にある年代です。
時間を味方につけた長期投資で、少額からじっくりと資産を育てましょう。
非課税制度を利用して運用すれば、得られた利益に対する税金が免除されますので、長期間運用するほど受けられる恩恵は大きくなります。
30代におすすめの資産運用
30代はさまざまな人生の選択を迫られる年代です。
結婚や出産の有無、これから進む人生の方向によって、投資のスタイルも変わってきます。
独身や夫婦だけの家庭など、資産に余裕がある方は株式投資を中心とした積極投資がおすすめです。
また、子育て世帯や両親との同居世帯など、家族のために安定した生活を重視する方は運用益が非課税となるNISA制度を利用した投資信託の積立投資がおすすめです。
40代におすすめの資産運用
40代は、スキルの向上や役職付きに伴い収入がアップする一方、住宅や車のローン返済や子どもの学費、両親の介護費用など、家族にまつわる出費が増える年代です。
近い将来に必要な出費をある程度試算できているようなら、投資信託の積立やロボアドバイザーの活用でコツコツと資産を増やしていくのがおすすめです。
ある程度資金に余裕がある方は、株式投資による積極運用を視野に入れてもよいでしょう。
自分の老後資金確保も見据えながら、家族が安心して暮らせるだけの資金確保を目指しましょう。

50代におすすめの資産運用
50代は子どもに関わる出費がなくなるため、資金面で余裕が出てくる年代です。
10年後に迎える定年退職を見据え、老後に向けた資金の確保を強く意識する時期でもあります。
50代から資産形成を考えるなら、iDeCoの活用がおすすめです。
iDeCoは60歳以降に受け取る年金や退職一時金を運用で増やすだけでなく、掛金が所得控除の対象となるため、毎年の税金を低く抑えられます。
収入が上がり納税額が増えている人ほど大きな恩恵を受けられるでしょう。
資金面で余裕があるなら、投資信託や債券投資といった低リスクの投資も視野に入れつつ、株式投資やアクティブ型の投資信託で大きなリターンを狙うのも選択肢のひとつです。
【投資金額別】おすすめの資産運用
資産運用を検討している人の中には、まとまったお金での運用を考えている人もいるでしょう。
投資金額別におすすめできる資産運用の方法は、次のとおりです。
【投資金額別】おすすめの資産運用
10万円のおすすめ資産運用
約10万円を元手に投資を始めるなら、新NISA(つみたて投資枠)やiDeCoで投資信託を購入し、長期の積立投資を始めましょう。
ネット証券の投資信託なら最低100円から始められるので、仕組みを学びながら徐々に増額していきましょう。
株式を購入できる単元は100株単位であるため、高額の株式は購入できません。
しかし投資を学ぶ上で株式を知るのは重要であるため、一株数百円の銘柄を狙うか、ミニ株から株式投資に触れるのもよいでしょう。
100万円のおすすめ資産運用
投資に回せるお金が100万円あれば、幅広い投資先を選択できます。
しかしやみくもに投資先を選ぶのではなく、投資に求める成果に合った投資方法を選びましょう。
①100万円を確実に増やしたい人
リターンは大きくなくとも確実に増やしたい方には債券投資がおすすめです。
債券は会社や自治体が発行する有価証券の一種で、会社や自治体にお金を貸していることを証明するものです。
お金が返済される償還期限までの間に支払われる利息が利益となります。
②100万円をほったらかしで運用したい人
運用を任せてほったらかしにしたい方は、投資信託の積立やロボアドバイザーがおすすめです。
どちらも投資の方針を最初に設定すれば、その後は特に手を掛ける必要なく積み立てを続けてくれます。
特にロボアドバイザーは自動でリバランスも行ってくれるため、安心してほったらかしにできるでしょう。
③100万円でハイリターンを狙いたい人
積極的に運用し、ハイリターンを望む方には株式投資がおすすめです。
市場の動きに応じて短期間で数十パーセントの利益を生むことも考えられます。
しかし大きな値下がりをするリスクもありますので、ほったらかしにしない積極的な運用が求められます。
1,000万円のおすすめ資産運用
1,000万円は投資資金として大きな金額で、大きなリターンが期待できる一方、値下がりによるダメージも深刻です。
ひとつの投資先の下落が致命的なダメージにならないよう、期待するリターン別の分散投資を前提に、ポートフォリオを構成しましょう。
①1,000万円を低リスクで運用したい人
低リスクの安定運用を目指すなら、債券投資やインデックス型の投資信託がよいでしょう。
ひとつの銘柄に集中せず、国内債券と海外投資信託などに分散するのが理想的です。
②1,000万円をミドルリスク・ミドルリターンで運用したい人
ミドルリターンを目指すならアクティブ型の投資信託やロボアドバイザーといった、ほったらかしと積極運用が両立できる手段がよいでしょう。
ロボアドバイザーへの指示の調整など、ある程度の手を掛ける必要はありますが、元手が大きい分一定金額以上のリターンが期待できます。
③1,000万円でハイリターンを狙いたい人
ハイリターンを望むなら株式やETFへの投資がおすすめです。
分散投資先の選択肢のひとつとして、ハイレバレッジ型のETFを選ぶなど、100万円では選ばなかった投資先も選択肢に入ります。
また、単元株の価格が数百万におよぶ国内株式も選べますので、より積極的な投資が行えるようになるでしょう。
【目的別】おすすめの資産運用方法
資産運用の方法は、年齢や金額だけでなく目的によっても変わります。
ここでは特に老後を中心とした資産運用の方法を紹介します。
【目的別】おすすめの資産運用方法
若い間に資産を増やしたい方におすすめ運用方法
若いうちに資産を増やしたい場合には、次の方法をおすすめします。
若い間に資産を増やしたい方におすすめ運用方法
- 余裕資金が少ない場合:新NISA(つみたて投資枠)やiDeCo
- 多くの余裕資金がある場合:株式投資
余裕資金が少ない場合には、少額から始めることができる新NISA(つみたて投資枠)やiDeCoがおすすめです。
新NISAは証券会社によっては月100円から、iDeCoは月5,000円から投資が可能です。
ただし、iDeCoに関しては資金を引き出せるのは原則60歳と決まっているため、老後資金を目的とした資産運用の場合に利用するようにしましょう。
一方、多くの余裕資金がある場合は、株式投資による資産運用がおすすめです。
事業に将来性があり、高配当や増配が期待できる銘柄を長期運用し、キャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指しましょう。
老後資金のおすすめ運用方法
ゆとりのある老後を目指した資金の確保を目指すなら、比較的安全に運用できる新NISAやiDeCoを利用した投資信託での運用がよいでしょう。
新NISAやiDeCoは運用益に係る税金が非課税となるほか、iDeCoの積立額は所得控除の対象となり、毎年の税金が減額されます。
どちらも通常の資産運用にはない税制面のメリットが大きいため、積極的に活用しましょう。
老後資金は定年退職後の生活資金であるため、リスクを伴う積極的な運用は避けた方が無難です。

退職金のおすすめ運用方法
退職金の運用には投資信託やロボアドバイザー、ETFといった投資商品から、金利が優遇された退職金専用の定期預金など、さまざまな選択肢があります。
どの選択肢を選ぶとしても、60代になると若い頃に比べて新たに収入を得にくくなるため、大きな損失に繋がるハイリスクな投資は避け、安定運用を第一に投資先を選ぶとよいでしょう。
定年退職時に退職金をもらえる60歳前後は、人生100年時代と言われる現代においてまだまだ現役といえる世代でしょう。

失敗を防ぐ!初心者が資産運用を上手に始めるポイント
資産運用に初期段階からつまずかないためには、以下の点に注意しましょう。
資産運用を上手に始めるポイント
ポイント①資産運用に使う金額を決める
投資初心者にありがちな失敗のひとつが、全資産を投資につぎ込んだ後の値下がりです。
生活資金や将来のための貯金もすべて投資に回した結果、大暴落で資産を大幅に減らすケースは珍しくありません。
投資は元本保証がありませんので、いつ目減りするかわかりません。
直近の生活や将来の目標に影響を出さないよう、資産運用に使う金額は余剰資産の範囲で決めるようにしましょう。
ポイント②資産運用に期待するリターン(利益額、利益幅)を決める
投資による資産運用は、投資先によっては大きなリターンが望めます。
値上がりしている株を持っていると、いつまでも上がり続けるような錯覚に陥りがちですが、ずっと上がり続けるとは限りません。
さらなる値上がりを期待して投資商品を持ち続けた結果、暴落により元本割れしてしまったというケースも珍しくありません。
過度な期待をしすぎず、確定する利益の額はあらかじめ決めておき、到達したら手放して利益を確定させるようにしましょう。
ポイント③資産運用にかけられる時間を考える
資産運用において強い味方になるのが時間です。
投資信託のような長期投資に向いた商品は、短期的な利益は大きくありません。
しかし長期保有すれば複利効果により、元本の何倍もの利益を得られるでしょう。
一方で値動きが激しい株式への投資は、短期間で大きな利益を生む可能性があります。
投資商品によって利益の出し方はさまざまですので、資産運用に掛けられる時間に応じた投資方法を選ぶように心掛けましょう。
ポイント④投資方法を組み合わせる
ひとつの投資商品のみを購入する集中投資は、大きなリターンが期待できる一方で、損失が大きくなるリスクもあります。
特定の銘柄の値下がりで資産を大きく損なわないよう、投資先は複数の銘柄に分散するとよいでしょう。
分散方法は購入する銘柄を分けるだけでなく、投資信託のような複数の銘柄で構成されている商品を組み入れるのも有効です。
すべての資産が同時に大幅な下落をしないよう、投資先の国や商品種類、投資時期を分散するように心掛けましょう。
ポイント⑤「ポジポジ病」にならない
ポジポジ病とは、株式やFXの投資において常に商品を持っていたいと考える心理状態を指す俗語です。
売買によって利益を上げる株式取引においては、利益を上げやすい局面が訪れるまで何も持たずに待つことも重要とされています。
しかし、ポジポジ病は自分が持っている商品の値動きへの一喜一憂が病みつきになってしまっている状態です。
そのため、十分な検討を行わないまま勝ち目の薄い商品を購入してしまい、損害が出るまで持ち続けてしまうのです。
ポジポジ病は高揚感を味わいやすい初心者ほど陥りやすいといわれています。
無理な取引で損失を生まないよう、時には何の株も持たない時間を確保しつつ、冷静な判断ができるだけの知識を身につけましょう。
資産運用におすすめの証券会社
資産運用をする際は、証券会社やそのサービスを取り扱う会社で、口座開設や登録を行う必要があります。
ここでは複数の資産運用が行えるおすすめの証券会社を紹介します。

資産運用におすすめの証券会社
おすすめの証券会社①SBI証券

※参照元:投資は、もっと自由になれる。“ゼロ革命“売買手数料が0円!|SBI証券
| 投資信託 | |
|---|---|
| 新NISA | |
| iDeCo | |
| ミニ株投資 | |
| ポイント投資 | |
| ロボアドバイザー |
SBI証券は取り扱う投資信託の本数が多く、2,600本近くの投資信託の取引が可能です。(※2024年5月1日時点)
新NISAのつみたて投資枠で取引可能な投資信託は218本、成長投資枠対象ファンドは1,155本とネット証券の中でも多く、幅広い選択肢の中から探せます。
iDeCoについても、投資信託と定期預金、保険商品の中から選択可能です。
ポイント投資は、Vポイントをはじめとする5種類のポイントとJALマイレージを、投資信託や日本株の購入に使用できます。
ロボアドバイザーはSBIラップのみで、2つのコースから選択が可能です。
取り扱い商品の種類が多く、株式投資やミニ株投資の手数料が無料となるコースもあり、総合的なサービスが充実したネット証券といえるでしょう。
おすすめの証券会社②楽天証券

※参照元:みなさまに選ばれてNo.1 | 楽天証券
| 投資信託 | |
|---|---|
| 新NISA | |
| iDeCo | |
| ミニ株投資 | |
| ポイント投資 | |
| ロボアドバイザー |
楽天証券で取り扱う投資信託の本数は約2,553本であり、そのうち新NISAのつみたて投資枠向けは223本と選択肢が多い点がメリットです。(※2024年5月1日時点)
iDeCoは保険商品の取り扱いがなく、定期預金も1種類しかありませんが、投資信託を運用したい場合には十分な商品数を取り揃えています。
楽天ポイントによるポイント投資が可能で、日本株や米国株、投資信託、バイナリーオプションに投資できます。
ロボアドバイザーは「楽ラップ」の1種類だけと少ない一方、ミニ株はほかの大手ネット証券とは違い、リアルタイムでの取引が可能です。
株式投資、ミニ株投資の取引手数料が無料の「ゼロコース」もあるなど、使い勝手のよい証券会社といえるでしょう。
資産運用に関するよくある質問
30代の投資額の平均はいくら?
30代の平均投資額は200~300万円ほどです。
金融広報中央委員会によれば、30代の投資額の平均は230万円ほどで、中でも株式への投資が約170万円と多い傾向にあります。
資産のうち投資に回すのは25%強と総資産の4分の1程度で、残りは預貯金や保険、財形貯蓄などが占めています。
このデータから、30代は資産を増やすよりも、資産を守る運用をしているといえるでしょう。
一番簡単な資産運用の方法は?
初心者には、少額から投資できる新NISAがおすすめです。
SBI証券や楽天証券などのネット証券の場合、新NISAは100円からの積立が可能です。
ごく少額から積立投資ができるため、資金に余裕がない場合でも無理のない資産運用ができます。
新NISAのつみたて投資枠で毎月積立する場合には、最大10万円まで積立金額を増やせます。
資金に余裕が出てきたときに、余裕資金に応じて積立額を増やすといいでしょう。
新NISAを利用すると20年後いくらになる?
年率3%、5%で20年間毎月3万円積み立てて運用した場合、資産額は下記のとおりになります。
- 年率3%:984.9万円(利益264.9万円)
- 年率5%:1,233.1万円(利益513.1万円)
※シミュレーションは金融庁の「資産運用シミュレーション」をもとに作成
得た利益にも利子がついてさらに利益が増える複利効果により、20年後には利益が拡大しています。
新NISAでの非課税運用期間は無制限であるため、できる限り長期間運用するとよいでしょう。
貯金がいくらあったら投資して大丈夫?
生活費や将来必要になる金額を確保したうえで、余剰資金で投資してください。
まずは、生活費や自身のライフプランに必要な資金、万が一の事態に備えるための資金を計算してみてください。
半年分ほどの生活費があれば、万が一のときにも対応できると考えられます。
以上の資金を確保したうえで、捻出可能な余剰資金を投資に回しましょう。
資産運用をしないほうがいいケースってあるの?
生活や将来のために必要なお金を投資資金に充てるのは避けましょう。
投資は大きな利益を得るチャンスがある一方、元本を損なうリスクもあります。
生活に必要なお金や子どもの教育資金を投資資金に充てた結果、大切なお金を失ってしまうかもしれません。
投資は必要なお金を確保した上で、余剰資金を使って行いましょう。
資産運用の勉強におすすめの本は?
『世界一やさしい株の教科書一年生』(ソーテック社)、『今さら聞けない投資の超基本』(朝日新聞社)がおすすめです。
投資の基本である株式を初めて学ぶ方におすすめの一冊が「世界一やさしい株の教科書一年生(ソーテック社)」です。
株式取引を行う上で知っておきたいルールをわかりやすく学べます。
投資全般を学ぶなら「今さら聞けない投資の超基本(朝日新聞社)」がよいでしょう。
株式や投資信託といった商品知識から、iDeCoやNISAといった制度の仕組みまで幅広い知識を身につけられます。
元本保証のある資産運用方法は?
国債、地方債、定期預金、貯蓄型保険商品は元本が保証されます。
安定性の高い債券の中でも、国が発行する「国債」と地方自治体が発行する「地方債」は、元本保証型の商品といえます。
金利は低めですが、国や自治体がなくならない限り償還される商品です。ただし1年未満での中途解約はできない点にご注意ください。
銀行などの金融機関に預け入れる期間が定められている「定期預金」、契約期間満了後に元本が戻る「貯蓄型保険」は、民間企業による元本保証型の商品です。
ただし貯蓄型保険は条件によっては元本割れする可能性がありますので、契約前に条件をよく確認しておきましょう。
まとめ
国が主導した資産運用の制度が生まれるほど、近年は資産形成に対する意識が高まっています。
投資はどんな方法でも必ず利益が出るとは限りません。
投資に充てられるお金や期間を踏まえ、自分にあった投資方法を選びましょう。
























