
<これで安心>住宅ローンの返済イメージが湧く!お得に返済するコツも紹介
最終更新日:
このページにはPRリンクが含まれています
また当サイトで得た収益は、サイトを訪れる皆様により役立つコンテンツを提供するために、情報の品質向上・ランキング精度の向上等に還元しております。※提携機関一覧
住宅ローンを検討する際に気になるのが、今後の返済についてですよね。
実は、住宅ローンでは同じ金額を借りた場合でも、「返済期間」や「返済方法」などによって返済イメージが変わります。
住宅ローン借り入れシミュレーションを利用すれば、月々の返済額を試算できますので、参考にしてみてください。
金利タイプや借入先で
返済額が変わる!
たった
1分
まずはシミュレーションで
住宅ローンを一括比較
とはいえ、
- シミュレーションだけでは、いまいち返済のイメージが湧かない
- どうすれば自分に合う返済をイメージできるのか知りたい
と感じる人もいるかもしれません。
そこでこの記事では、住宅ローンの返済イメージに関する以下の疑問について解説します。
- 住宅ローンを借りると、どれくらいの期間をかけて毎月いくら返済する必要があるの?
- 「元利均等返済」と「元金均等返済」では、返済イメージはどう変わる?
- 「ボーナス払い」や「繰り上げ返済」をした場合の返済イメージは?
ぜひ、住宅ローンを検討する際の参考にしてください。

オフィス千日合同会社 代表社員 公認会計士 / 公認会計士中村岳広事務所
監修者千日太郎
公認会計士として、本名である中村岳広の名を掲げた公認会計士 中村岳広事務所を設立・運営。
独自のノウハウと公認会計士としての金融商品の分析力を生かし、
2014年から「千日太郎」として住宅ローンの情報をブログ「千日のブログ 家と住宅ローンのはてな?に答える」で発信。
「千日の住宅ローン無料相談ドットコム」では一般の人からの匿名相談に無料で乗り、コンサル内容をネットに公開している。
住宅ローンの金利動向やリスク対策について著した『住宅ローンで「絶対に損したくない人」が読む本』など、複数の著書を出版。
▼書籍一覧
住宅ローンで「絶対に損したくない人」が読む本
家を買うときに「お金で損したくない人」が読む本
初めて買う人・住み替える人 独身からファミリーまで 50歳からの賢い住宅購入
住宅破産
株式会社エイチームライフデザイン
編集者イーデス編集部
「ユーザーが信頼して利用できるWEBメディア」を目指す編集部チーム。実際のユーザーの声や業界知識の豊富な専門家の協力を得ながら、コンテンツポリシーに沿ったコンテンツを制作しています。暮らしに関するトピックを中心に、読者の「まよい」を解消し、最適な選択を支援するためのコンテンツを制作中です。
■書籍
初心者でもわかる!お金に関するアレコレの選び方BOOK
■保有資格
KTAA団体シルバー認証マーク(2023.12.20~)
■許認可
有料職業紹介事業(厚生労働大臣許可・許可番号:23-ユ-302788)
気になる内容をタップ
住宅ローンの返済をイメージする際のポイント
「住宅ローンの返済をイメージする」と言っても、どのような観点から考えればよいのかわからない人もいるでしょう。
住宅ローンの返済イメージする際にポイントとなるのが、以下の4つの要素です。
- 返済方法
「元利均等返済」と「元金均等返済」のどちらにするのか - 借入額
住宅ローンでいくら借りるのか - 返済期間
どれくらいの期間をかけて返済するのか - 金利
「変動金利」と「固定金利」のどちらにするのか
住宅ローンでは、上記の4つの要素によって返済イメージが変わります。
そのため、同じ金額を借り入れたとしても、返済方法や返済期間などが違えば、総返済額が同一になることはありません。
また、金利の利率は、借入先となる金融機関や金利タイプにより異なります。
イーデスのサイト内にある「住宅ローン比較シミュレーション」では、借入希望額・返済期間・返済方法・金利タイプの4項目を入力するだけで、毎月の返済額や総返済額を試算することができます。
2025年最新版
おすすめ住宅ローン
金利比較
最新金利や
住宅ローンの選び方まで!
たった
1分
まずはシミュレーションで
住宅ローンを一括比較
元利均等返済と元金均等返済とは
住宅ローンの返済を調べている際、「元利均等返済」と「元金均等返済」という単語を目にした人も多いでしょう。
一見似ている単語ですが、それぞれ明確な違いがあります。
元利均等返済とは
借り入れした金額と利子の合計金額を均等にする返済方法
元金均等返済とは
借り入れした金額を均等にし、残高分の利子を上乗せする返済方法
元利均等返済と元金均等返済は、「何を均等にして返済するか」という点が異なります。

「元利均等返済」は、金利が一定であれば、毎月の返済額が同一の金額となります。
「元金均等返済」は、住宅ローンの残高によって上乗せされる利子の金額が変わるため、返済が進むにつれて毎月の返済額も減ることが元金均等返済の特徴です。
元利均等返済と元金均等返済には、それぞれメリット・デメリットがあります。

| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 元利均等返済 | 返済計画を 立てやすい | 総返済額が 高くなる |
| 元金均等返済 | 総返済額を 抑えられる | 借り入れ当初の 返済負担が重い |
元利均等返済と元金均等返済については、下記の記事でわかりやすく解説していますので、ぜひ見てみてください。
「元利均等返済」と「元金均等返済」の返済イメージ
前述した通り、元利均等返済は毎月の返済額が一定になり、元金均等返済は徐々に返済額が減ります。
では、返済方法によって、どれくらい返済額は変わるのでしょうか。
下記は、元利均等返済を選んだ場合と元金均等返済を選んだ場合の返済イメージを比較した表です。
| 元利均等返済 | 元金均等返済 | |
|---|---|---|
| 毎月の 返済額 | 87,510円 | 101,428円 |
| 総返 済額 | 36,754,301円 | 36,314,845円 |
借入額:3,000万円
金利:1.200%(全期間固定金利)
返済期間:35年
ボーナス払い:なし
借り入れ当初における毎月の返済額は、元金均等返済よりも元利均等返済のほうが約1万4,000円低くなります。
しかし、総返済額は元金均等返済のほうが約44万円も低いことがわかります。
元利均等返済は毎月の返済額を抑えられますが、借入条件によっては元金均等返済のほうが総返済額が低くなることを覚えておきましょう
返済期間で見る返済イメージ
住宅ローンは、返済期間の設定によっても返済額が変動します。
続いて、返済期間ごとの返済イメージを見ていきましょう。
| 返済期間 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|
| 毎月の 返済額 | 140,661円 | 115,798円 | 99,272円 | 87,510円 |
| 総返 済額 | 33,758,672円 | 34,739,401円 | 35,737,974円 | 36,754,301円 |
【試算条件】借入額:3,000万円 金利:1.200%(全期間固定金利) 返済方法:元利均等 ボーナス払い:なし
上記の表から、毎月の総返済額では最大約5万3,000円の差が、総返済額では最大約300万円の差が生じることがわかります。
返済期間が長くなるにつれて総返済額が高くなる理由は、借りている期間が長くなればなるほど支払う利子の総額が増えるためです。
返済期間20年の場合、返済期間35年と比べると毎月の返済額はかなり高くなりますが、返済期間が短くなることで利子の支払いを抑えられるため、総返済額が低くなります。
しかし、返済期間35年の場合は、毎月の返済額が低くなることで、手元に残る資金を貯金などに回しやすくなるでしょう。
返済期間ごとの返済イメージだけでなく、収入やライフプランを踏まえて、自分に合う返済期間を検討することをおすすめします。
ボーナス払いの有無で見る返済イメージ
住宅ローンの返済方法には、毎月決まった額を返済する「毎月払い」のほかに、ボーナスが支給された月は増額して返済する「ボーナス払い」があります。
ボーナス払いの有無によっても、住宅ローンの返済イメージは違います。
下記の表は、シミュレーションツールを用いて試算した、ボーナス払いあり・ボーナス払いなしの場合における返済イメージです。
| ボーナス払いあり (借入額の20%をボーナス払い) | ボーナス払いなし | |
|---|---|---|
| 毎月の返済額 | 70,008円 | 87,510円 |
| ボーナス月の返済額 | 105,223円 | 0円 |
| 総返 済額 | 36,769,019円 | 36,754,301円 |
借入額:3,000万円
金利:1.200%(全期間固定金利)
返済期間:35年
返済方法:元利均等
シミュレーション結果から、ボーナス払いありにするとボーナス月の返済額は大きくなりますが、毎月の返済額を減らすことが可能です。
しかし、ボーナス払いで多く返済する月があっても、総返済額はボーナス払いなしとあまり変わらないことがわかります。
そのため、ボーナス払いの併用により、総返済額が大幅に減るような効果は期待できません。
実際に、借入額に占めるボーナス払いの割合を増やすと、総返済額は高くなる傾向にあります。
また、会社から毎年きちんとボーナスが支給されるとは限りません。
ボーナスが減額されるときもあれば、ボーナスが出ないときもあるでしょう。
ボーナス払いを利用するかどうかは、リスクを踏まえて慎重に検討してください。
繰り上げ返済した場合の返済イメージ
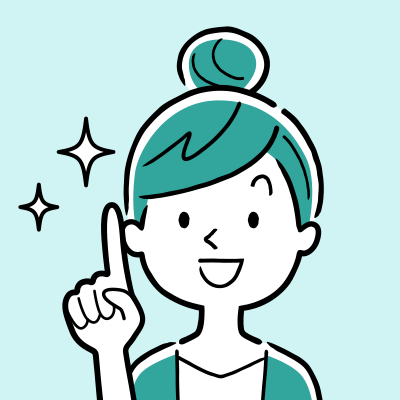
- 子どもの手が離れたからお金を返済に回したい
- 住宅ローンをできるだけ早く完済したい
など、さまざまな理由から繰り上げ返済を検討している人は少なくありません。
繰り上げ返済を行うのかどうかによっても、住宅ローンの返済イメージは変わります。
繰り上げ返済には、返済期間を短縮する「期間短縮型」と、毎月の返済額を少なくする「返済額軽減型」の2種類があります。
通常は、期間短縮型の繰り上げ返済を行うことが多いです。
そのため、今回は借り入れから10年後に期間短縮型で返済を繰り上げた場合の返済イメージを説明します。
| 繰り上げ返済を 行った場合 | 繰り上げ返済を 行わなかった場合 | |
|---|---|---|
| 繰り上げ 返済額 | 2,000,000円 | 0円 |
| 総返 済額 | 36,102,642円 | 36,754,301円 |
| 返済 期間 | 32年6か月 | 35年 |
借入額:3,000万円
金利:1.200%(全期間固定金利)
返済期間:35年
返済方法:元利均等
上記のシミュレーションに用いた試算条件において、借り入れから10年後に200万円を繰り上げ返済した場合、総返済額が約65万円も減ります。
繰り上げ返済で総返済額が減少するのは、返済期間を短縮することで、将来支払う予定だった利子を節約できるためです。
ただし、繰り上げ返済にはまとまった資金が必要なので、繰り上げ返済の金額は慎重に決めましょう。
さらに、利子の削減効果を高めるためには、繰り上げ返済のタイミングを見極めることも重要です。
繰り上げ返済は利子の削減効果が期待できますが、繰り上げ返済を行うタイミングが重要になることを理解しておきましょう。
安心して住宅ローンを借りるための3つのポイント
返済方法や返済期間、ボーナス払い・繰り上げ返済の有無など、多角的な視点から返済をイメージしても、その返済イメージが適切かどうか判断することは難しいですよね。
- 無理なく返済できる額に設定したい
- できるだけお得な方法で返済したい
など、住宅ローンを安心して借りたい人は、以下の3つのポイントを押さえましょう。
住宅ローンを安心して借りたい人のポイント
ここからは、住宅ローンを安心して借りるための3つのポイントについて詳しく解説します。
ポイント1:返済比率を収入の20%以内にする
返済比率とは「年収に占める年間の住宅ローン返済額の割合」のことです。返済負担率と呼ばれることもあります。
無理なく返済できるのかどうか判断する際は、返済比率をチェックすることも有効です。
年収によって異なりますが、それぞれの返済比率における返済イメージは下記の通りです。
| 返済比率 | 返済イメージ |
|---|---|
| ~10% | 余裕を持って返済できる |
| 11~19% | 多少のゆとりを持てる |
| 20~29% | 平均的な返済ができる |
| 30~34% | 家計の支出を見直す必要がある |
| 35%~ | 返済が家計を圧迫する |
返済比率29%までは無理なく返済できる可能性が高いと言えます。
しかし、返済比率が35%以上になると、毎月の返済額が家計の大きな負担となり、ゆとりのある生活が難しくなるかもしれません。場合によっては、住宅ローン返済を延滞してしまう可能性もあります。
住宅ローンを無理なく返済したい場合は、返済比率20%以内をひとつの目安にしましょう。
ポイント2:生活費や教育費などの支出を考慮する
住宅ローンを借りる際は、生活費や教育費といった将来の支出も考慮に入れましょう。
住宅ローンは、25年や35年といった長期にわたり返済するローンです。
住宅ローンの返済中に、収支のバランスが崩れるケースはめずらしくありません。
- 転職や退職を機に、収入が大幅に減った
- 子どもが私立の学校に通うことになり、教育費が増えた
- カーローンを利用して新車を買った
- 病気やケガで長期入院となり、治療費がかかったうえに収入も減った
など、将来の収支の増減によっては、現在の収入状況から無理のない返済額になるよう借り入れても、住宅ローンの返済が困難になる可能性もあります。
そのため、これからの生活の中で「何の支出がどれくらい増えそうなのか」をあらかじめ考えておくことは大切です。
ポイント3:金利の低い住宅ローンを選ぶ
低金利の住宅ローンを借りて、毎月の返済額を抑えることができれば、収支のバランスが崩れても対処できるでしょう。
たとえば、現状では毎月の収支が合っていたとしても、教育費などの支出が増えた途端、家計が苦しくなる恐れがあります。
しかし、毎月の返済額が少しでも減れば、収入を貯蓄に回す余裕が生まれ、万が一の事態にも対応できるようになります。
しかし、さまざまな住宅ローン商品の中から、金利の低い住宅ローンを見つけることは簡単ではないですよね。
- どの金融機関の住宅ローンなら低金利なの?
- 金利タイプごとにおすすめの住宅ローンは?
という疑問がある人は、下記の表を参考にしてください。
| 金利タイプ | 金融機関 | 金利 |
|---|---|---|
| 変動金利 | auじぶん銀行 | 年0.834%
|
| 当初固定金利 (当初20年) | SBI新生銀行 | 年2.030%
|
| 全期間固定金利 (固定35年) | ARUHI | 年1.840%
|
金利が低くなれば、毎月の返済額だけでなく総返済額も抑えられるため、
ぜひ上記で紹介した金融機関をチェックしてみてください

まとめ
住宅ローンの返済イメージを掴むためには、下記の4つの要素を押さえる必要があります。
- 返済方法
- 借入額
- 返済期間
- 金利
4つの要素によって返済イメージが変わるため、シミュレーションツールを活用し、さまざまな借入条件による返済額の違いをチェックしましょう。
また、上記以外にも「ボーナス払い」「繰り上げ返済」の有無によって、住宅ローンの返済イメージは違ってきます。
もちろん、シミュレーション結果から返済イメージを固めても、イメージ通りに住宅ローンの返済が進むとは限りません。
住宅ローンの返済中に予想外の出費が増えたり、不測の事態で収入が減ったりする可能性は十分に考えられます。
そのため、将来の支出も考慮に入れたうえで、返済比率が25%以内になる借入額を設定することが大切です。
万が一のことが起こっても安心して返済できるようにしたい場合は、低金利の住宅ローンを検討してみましょう。


千日太郎 / オフィス千日合同会社 代表社員 公認会計士
【専門家の解説】
千日太郎が住宅ローンの返済イメージとしてお伝えしている言葉が「毎月決まったお金を35年(420回)払うこと」というものです。
これに途中で挫折すると、債権者に家を取り上げられてしまいます。これだけは阻止したいですよね。
例えば、ご自身が420回ノーミスでできそうなことを想像してみてください。
縄跳びでしょうか?年賀状の宛名書きでしょうか?私ならばどちらも半分以下でミスする自信がありますが、かなり難易度のハードルを下げなければ、難しいと思います。
本文でポイントとして挙げている4つの要素、
①返済方法(「元利均等返済」と「元金均等返済」のどちらにするのか)
②借入額(住宅ローンでいくら借りるのか)、
③返済期間(どれくらいの期間をかけて返済するのか)
④金利(「変動金利」と「固定金利」のどちらにするのか)
は、420回にわたりクリアしなければならない毎月返済額のハードルの高さを決める要素でもあるのですね。
毎月返済額の安全圏は、その人の収入と住居費以外の支出によっても異なりますが、概ね手取り月収の4割を超えないようにすることをお勧めしています。
むろんボーナス払いなしです。住宅ローンを決める際の参考にしてください。
















シミュレーションツールを使って試算を出すと、住宅ローンの返済イメージが掴みやすくなりますよ