
iDeCo(イデコ)のおすすめ銘柄4選!金融機関はどこがいい?
最終更新日:
このページにはPRリンクが含まれています
また当サイトで得た収益は、サイトを訪れる皆様により役立つコンテンツを提供するために、情報の品質向上・ランキング精度の向上等に還元しております。※提携機関一覧
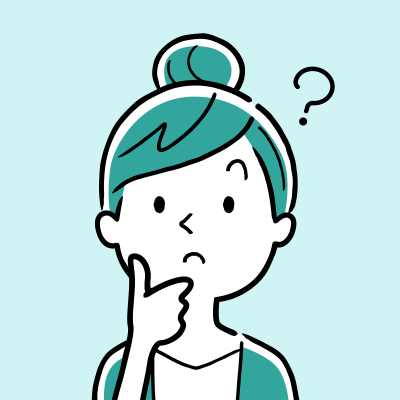
- iDeCoで運用するのにおすすめの銘柄はどれ?
- iDeCoを使うなら金融機関はどこがいいの?
iDeCo(個人型確定拠出年金)は60歳まで原則引き出し不可という特徴があるので、長期的に運用できる商品を選ぶのがおすすめです。
iDeCoのおすすめ銘柄・商品
今回は、iDeCoをこれから始めたい人のために、おすすめ商品 とiDecoのおすすめ金融機関 をまとめて紹介します。
iDeCoを始めるなら!
初心者におすすめのネット証券

- 証券口座開設数1,300万突破!
※SBIネオトレード証券、FOLIOを含むSBIグループの口座開設数 - 取扱銘柄数がトップクラス
- 充実のサポート体制
SBI証券はネット証券の中でも取扱銘柄が豊富で、初心者にも上級者にもおすすめです。
マイナンバーカード(もしくは通知カード)と本人確認書類があればスマホで口座開設ができるので、思い立ったときに申込を進めてみましょう。最短5分でフォーム入力が完了します。
公式サイトで無料口座開設・2024年12月10日時点の情報を掲載しています。
・三井住友カードのクレカ積立投資に関する注意事項は記事下部を参照ください。

スキラージャパン株式会社 代表取締役 / スキラージャパン株式会社
監修者伊藤亮太
伊藤亮太は「スキラージャパン株式会社」の取締役を務めるFP(ファイナンシャル・プランナー)。
慶應義塾大学大学院商学研究科経営学・会計学専攻を修了しており、在学中にCFP®を取得。
その後、証券会社にて営業・経営企画・社長秘書・投資銀行業務に携わる。
現在は富裕層個人の資産設計を中心としたマネー・ライフプランの提案・策定・サポート等を行う傍ら、資産運用に関連するセミナー講師や講演を多数行う。
▼書籍
7日でマスターNISA&iDeCoがおもしろいくらいわかる本
図解即戦力 金融のしくみがこれ1冊でしっかりわかる教科書
ゼロからはじめる! お金のしくみ見るだけノート
株で勝ち続けるための 上がる銘柄選び黄金ルール87
など
株式会社エイチームライフデザイン
編集者イーデス編集部
「ユーザーが信頼して利用できるWEBメディア」を目指す編集部チーム。実際のユーザーの声や業界知識の豊富な専門家の協力を得ながら、コンテンツポリシーに沿ったコンテンツを制作しています。暮らしに関するトピックを中心に、読者の「まよい」を解消し、最適な選択を支援するためのコンテンツを制作中です。
■書籍
初心者でもわかる!お金に関するアレコレの選び方BOOK
■保有資格
KTAA団体シルバー認証マーク(2023.12.20~)
■許認可
有料職業紹介事業(厚生労働大臣許可・許可番号:23-ユ-302788)
気になる内容をタップ
iDeCo(イデコ)のおすすめ銘柄・商品
iDeCoの運用商品の選び方は、「コスト(信託報酬)の安さ」「資金流入が続いていること」がポイントです。
ここでは、iDeCoで運用するのがおすすめな商品を4つ紹介します

iDeCoのおすすめ銘柄・商品
【選定基準】
以下条件を選定基準としています。
①信託報酬が、インデックスファンドの信託報酬平均0.32%(2024年10月)より安い(金融庁公式サイトより)
②直近1年で、資金流入が続いている
③SBI証券 、楽天証券 、マネックス証券 、野村證券 のいずれかで取り扱いがある
自分で銘柄を選ぶ時のポイントも後ほど紹介します!

おすすめ銘柄①SBI グローバル・バランス・ファンド

おすすめポイント
- 【特徴】国内と海外の株式と債券に分散投資できる
- 【内訳】投資商品は、米国株式と米国債券が中心
- 【傾向】月次資金流出入額が増加傾向にある
株式よりも債券の比率の方がやや多めのファンドとなっています。
そのため、積極的にリスクをとるよりも、リスクをできるだけ軽減して安定した値動きを狙いたい人におすすめです。
全世界の株式と債券を対象に、分散投資を行います。
投資比率はおよそ株式40%、債券60%であり、北米が全体のおよそ50%を占めています。
その他、日本と先進国、新興国にそれぞれ投資されています。
| 年数 | 5年 | 10年 | 20年 |
|---|---|---|---|
| 積立後の資産 | 660,000円 | 1,450,000円 | 3,630,000円 |
| 元本 | 600,000円 | 1,200,000円 | 2,400,000円 |
| 運用益 | 60,000円 | 250,000円 | 1,230,000円 |
※2024年12月10日時点の過去5年間の平均利回り(4.89%)で計算しています。(イーデス積立シミュレーションにて算出)
※本シミュレーションのいかなる内容も、将来の運用成果を予測し、保証するものではありません。
こちらの商品はSBI証券 のiDeCoで購入することができます!

主要ネット証券No.1
おすすめ銘柄②eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

おすすめポイント
- 【特徴】S&P500への連動を目指し、米国株式へ投資
- 【内訳】投資商品は米国株式が94%
- 【傾向】月次資金流出入額が増加傾向にある
米国の株価指数のひとつであるS&P500への連動を目指したファンドです。
米国株式への投資が94%を占め、アップルやマイクロソフト、アマゾンといったテック系企業を中心に構成されています。
2022年初頭からはやや不安定な動きを見せていましたが、堅調に純資産を増やし、2024年7月11日に基準価額は32,813円と過去最高値をつけた後は日米の金融政策の転換により円高と株安によって一時下落。
しかしその後、米金融大手の好決算の影響などにより、2024年12月10日時点の基準価額は33,010円とさらに上昇しています。
| 年数 | 5年 | 10年 | 20年 |
|---|---|---|---|
| 積立後の資産 | 1,130,000円 | 4,790,000円 | 55,100,000円 |
| 元本 | 600,000円 | 1,200,000円 | 2,400,000円 |
| 運用益 | 530,000円 | 3,590,000円 | 52,700,000円 |
※2024年12月10日時点の過去5年間の平均利回り(23.76%)で計算しています。(イーデス積立シミュレーションにて算出)
※本シミュレーションのいかなる内容も、将来の運用成果を予測し、保証するものではありません。
\iDeCoのおすすめ証券会社/
おすすめ銘柄③楽天・全世界株式インデックス・ファンド

おすすめポイント
- 【特徴】米国企業を中心に全世界の企業へ投資
- 【内訳】GAFAMなどの成長株を含む約9,000銘柄で構成
- 【傾向】月次資金流出入額が増加傾向にある
全世界の約9,000銘柄に投資できるバンガード・トータル・ワールドストックETF(VT)を中心とした投資ができるファンドです。
約85%を占めるVTのほか、米国市場全体を対象としたVTI、米国を除く株式市場を対象としたVXUSもそれぞれ5%以上ずつ組み入れています。
米国株を中心としながらも、一国に寄りすぎないバランスのいい分散投資ができるのが特徴です。
| 年数 | 5年 | 10年 | 20年 |
|---|---|---|---|
| 積立後の資産 | 990,000円 | 3,530,000円 | 26,980,000円 |
| 元本 | 600,000円 | 1,200,000円 | 2,400,000円 |
| 運用益 | 390,000円 | 2,330,000円 | 24,580,000円 |
※2024年12月10日時点の過去5年間の平均利回り(19.12%)で計算しています。(イーデス積立シミュレーションにて算出)
※本シミュレーションのいかなる内容も、将来の運用成果を予測し、保証するものではありません。
こちらの商品は楽天証券のiDeCoで購入することができます!

おすすめ銘柄④三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド

おすすめポイント
- 【特徴】TOPIX連動型のインデックス型投資信託
- 【内訳】ほぼ全額を日本国内の株式で運用
- 【傾向】月次資金流出入額が増加傾向にある
TOPIX(東証株価指数)への連動を目指し、国内株式で運用するファンドです。
トヨタやソニー、NTTといったTOPIXに採用されている銘柄で構成されています。
純資産総額が756億円と非常に大きく、人気がある投資信託として知られています。
TOPIXとほぼ同様の値動きをするため、今後の見通しが立てやすいのが特徴です。
| 年数 | 5年 | 10年 | 20年 |
|---|---|---|---|
| 積立後の資産 | 880,000円 | 2,710,000円 | 14,560,000円 |
| 元本 | 600,000円 | 1,200,000円 | 2,400,000円 |
| 運用益 | 280,000円 | 1,510,000円 | 12,160,000円 |
※2024年12月10日時点の過去5年間の平均利回り(14.88%)で計算しています。(イーデス積立シミュレーションにて算出)
※本シミュレーションのいかなる内容も、将来の運用成果を予測し、保証するものではありません。
こちらの商品は楽天証券のiDeCoで購入することができます!

iDeCo(イデコ)のおすすめ金融機関
iDeCoにおすすめの金融期間は以下の4社です。
iDeCoにおすすめの金融機関
【選定基準】
以下条件を選定基準としています。
①運営管理手数料が無料、もしくは、無料になる条件がある
②選べる商品数が20本以上
iDeCoを取扱っている金融機関は、現在約223社あります。
※厚生労働省|運営管理機関登録業者一覧より
金融機関によって取扱い商品・サービスに違いがあるため注意が必要です。
おすすめ金融機関①SBI証券
SBI証券のおすすめポイント
- 【商品数】投資信託は87本と主要ネット証券トップクラス
※2024年12月10日時点 - 【手数料】運営管理手数が無料
- 【特徴】SBI-iDeCoロボを使用して投資信託を選べる
SBI証券のiDeCoは、投資信託は87本と主要ネット証券の中で最も多くなっています。※2024年12月10日時点
取り扱っている商品の内訳は次の通りです。

| 投資信託 | 元本確保型商品 |
|---|---|
| 83本 | 4本 |
※2024年12月10日時点
投資信託にはコストが低いインデックファンドだけでなく、積極的な投資を行うアクティブファンドも多くそろえています。
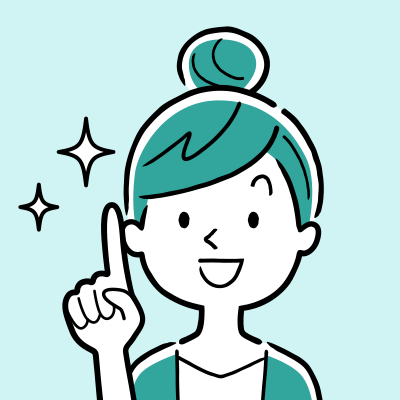
選択肢の幅が広いのは嬉しいですね!
また、SBI証券 には「SBI‐iDeCoロボ」という、ロボアドバイザーのサービス があります。
利用者の投資経験を踏まえて、最適な投資信託や元本確保型商品を提案してくれます。
投資経験が少ない人も、SBI証券 なら安心してiDeCoを始められるでしょう!

| 運営管理手数料 | 0円 | 保険有無 | なし |
|---|---|---|---|
| 投資信託 | 83 | コールセンター | 平日・土・日 ※土・日は新規の問い合せのみ |
| 元本確保型商品 | 4 | 店舗対応 |
※iDeCo取扱本数は2024年12月10日時点
NISA口座との同時開設がおすすめ!
おすすめ金融機関②マネックス証券
おすすめポイント
- 【商品数】投資信託は28本をラインナップ
※2024年12月10日時点 - 【手数料】運営管理手数が無料
- 【特徴】ロボアドや土曜でもiDeCo専用ダイヤルが利用できる
マネックス証券のiDeCoは28本の投資信託を取り扱っています。※2024年12月10日時点
取り扱っている商品の内訳は次の通りです。

| 投資信託 | 元本確保型商品 |
|---|---|
| 27本 | 1本 |
※iDeCo取扱本数は2024年12月10日時点
iDeCoで選択できる28本の投資信託は、国内外の株式や債券、REITなど、様々なタイプのラインナップとなっています。
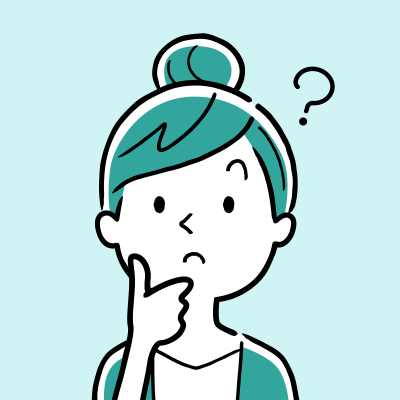
マネックス証券はロボアドが使えるの?
「iDeCoポートフォリオ診断」というロボアドが利用できます

「iDeCoポートフォリオ診断」では、簡単な質問に答えるだけで理想のポートフォリオをAIが提案してくれます。
どの銘柄に、どれくらい投資すれば良いのかわかるのは初心者には嬉しいですね。
さらに、マネックス証券は専門スタッフが対応してくれるiDeCo専用ダイヤルを土曜も利用できます。
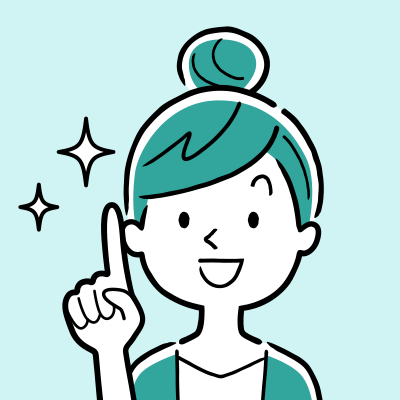
平日は仕事で忙しいので助かる…!
投資初心者で不安な人はマネックス証券 がおすすめです!

| 運営管理手数料 | 0円 | 保険有無 | なし |
|---|---|---|---|
| 投資信託 | 27 | コールセンター | 月~金 土 9~17時 ※祝日・年末年始を除く |
| 元本確保型商品 | 1 | 店舗対応 |
※iDeCo取扱本数は2024年12月10日時点
NISA口座との同時開設がおすすめ!
おすすめ金融機関③楽天証券
おすすめポイント
- 【商品数】投資信託は35本をラインナップ
※2024年12月10日時点 - 【手数料】運営管理手数が無料
- 【特徴】証券資産と年金資産を1つのIDで管理できる
楽天証券のiDeCoは、取り扱っている投資信託はSBI証券ほど本数は多くはないものの、35本ラインナップしています。※2024年12月10日時点
取り扱っている商品の内訳は次の通りです。

| 投資信託 | 元本確保型商品 |
|---|---|
| 34本 | 1本 |
※iDeCo取扱本数は2024年12月10日時点
楽天証券は国内外株式や債券、REIT、コモディティなど、幅広い種類の投資信託から選べます。
そのため、自分に合った一本を探しやすいのがメリットです。
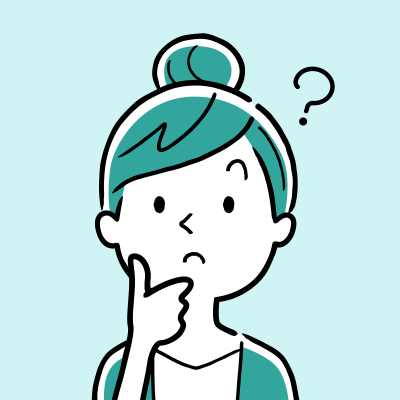
SBI証券のようにロボアドは使えるの?
楽天証券は、投資信託を選ぶ際に利用できるロボアドバイザーがありません。
ただし、iDeCoに関するセミナーを開催していて、過去の動画も公開しています。
心配な人はこれをセミナーを参考にして選びましょう

また、証券口座と同じIDでiDeCoも管理できる ため、管理が楽なのもおすすめできる理由のひとつです。
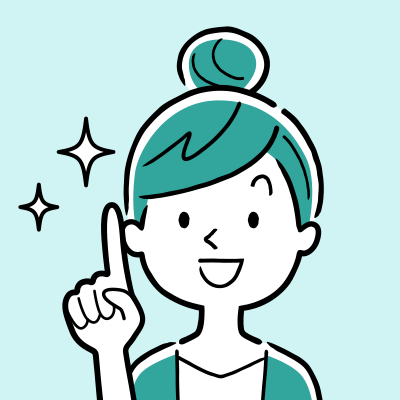
口座が一括で見られるのは便利ですね!
| 運営管理手数料 | 0円 | 保険有無 | なし |
|---|---|---|---|
| 投資信託 | 34 | コールセンター | 月~金 土・日・祝 9~17時 ※年末年始を除く |
| 元本確保型商品 | 1 | 店舗対応 |
※iDeCo取扱本数は2024年12月10日時点
NISA口座との同時開設がおすすめ!
おすすめ金融機関④野村證券
おすすめポイント
- 【商品数】投資信託は35本をラインナップ
※2024年12月10日時点 - 【手数料】運営管理手数が無料
- 【特徴】加入者向けWEBサービスやコールセンターなどフォロー体制がしっかりしている
野村證券のiDeCoでは、35本の投資信託を取り扱っています。※2024年12月10日時点
取り扱っている商品の内訳は次の通りです。

| 投資信託 | 元本確保型商品 |
|---|---|
| 34本 | 1本 |
※iDeCo取扱本数は2024年10月31日時点(2024年12月10日公式サイトより確認)
選択できる35本の投資信託の中には、現在注目されているESGやSDGs関連の投資信託も含まれています。
また、運営管理費が無料なのはもちろん、他社に移管する際の手数料も無料 です。
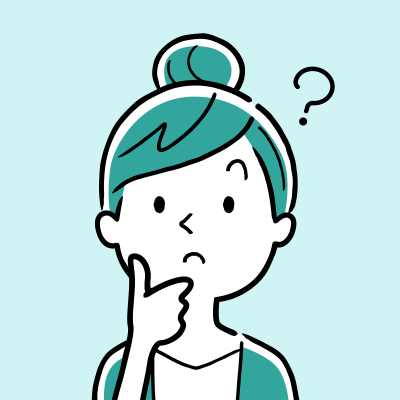
野村證券のiDeCoの特徴は何?
野村證券のiDeCoはフォローサービスが手厚いことですね!

野村證券のiDeCo加入者向けサービス「WEBサービス」は、PC・スマホから残高や損益などを確認できて便利です。
また、コールセンターでもiDeCo加入者の手続きや質問に対応しています。
コールセンターはHDI-Japanから五つ星を獲得するほど高品質なサービスとなっています

さらに情報提供として、「お取引状況のお知らせ」や市場情報などをまとめた「確定拠出年金ニュース」の定期送付を行っています。
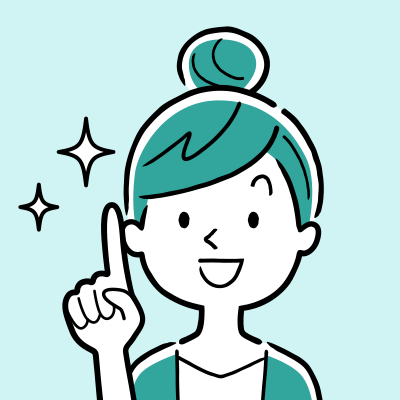
手厚いサポートを受けたい人には嬉しい体制ですね!
| 運営管理手数料 | 0円 | 保険有無 | なし |
|---|---|---|---|
| 投資信託 | 34 | コールセンター | 月~金 土・日 9~17時 ※年末年始、祝日を除く |
| 元本確保型商品 | 1 | 店舗対応 |
※iDeCo取扱本数は2024年10月31日時点(2024年12月10日公式サイトより確認)
iDeCo(イデコ)の商品・銘柄の選び方

せっかく始めるのに失敗したくない…!
iDeCoで失敗しないためにも、次の3つのポイントはしっかり押さえて銘柄を選びましょう。
iDeCoを始める前に知ってほしい3つのポイント
選び方①元本確保・リターンのどっちを狙うか
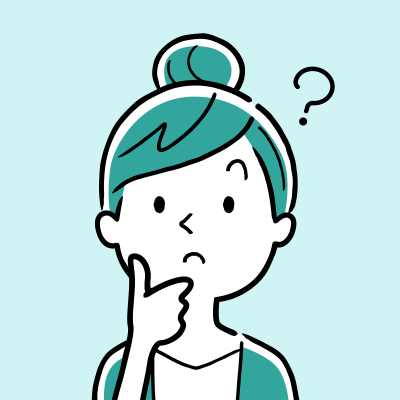
元本確保商品と投資信託は何が違うの?
2つの商品の違いをまとめました

| 元本確保商品 | 一定期間で所定の利息が上乗せされるもの |
|---|---|
| 投資信託 | 商品によってリスクやリターンが異なる |
元本確保商品には「定期預金」と「保険商品」があります。
それぞれの特徴を理解して、自分に合った商品と金融機関を見つけましょう。
元本確保商品は満期まで保有すれば元本が割れることはなく、安全に運用することができます。
一方で投資信託は元本が割れる可能性はありますが、運用が上手くいけば元本確保商品よりも高い収益 を得ることができます。
選び方②引出し時にリターンが見込めるか
iDeCoは原則として60歳まで引き出すことができません。
そのため、長期的な視点での運用を踏まえて銘柄を選ぶ必要があります。
銘柄選びの際には短期のリターンではなく3年や5年などのリターンを見るようにしましょう

選び方③金融機関で商品の取扱いや手数料はどうなっているか
iDeCoを取り扱っている金融機関は数多くあります。
ただし、金融機関によっては取扱商品数が少なかったり、手数料がかかったりと損してしまう可能性もあります。
iDeCoを始める時は銘柄選びと同様に金融機関選びも重要になってきますよ

今回紹介した金融機関は運営管理手数料が無料で取扱い商品数も多い金融機関です。
どこにすればいいか悩んでいるという人は、商品数も多く加入者数No.1のSBI証券(※)がおすすめです。
※2023年5月 SBI証券調べ
iDeCo(イデコ)の金融機関の選び方
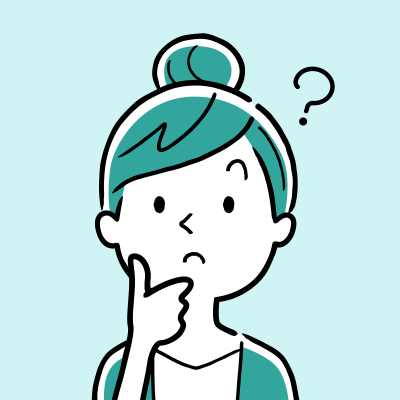
自分に合っている金融機関はどれなんだろう?
iDeCoの金融機関選びで迷う人は、次の3つのポイントを意識するのがおすすめです。

iDeCoの金融機関の選び方
iDeCoは、金融機関によって商品・手数料・サービス内容が異なります。
ここに挙げた3つのポイントを意識すれば、「運用したい商品がない」「使い勝手が悪くて金融機関を変更したい」といったことになりづらいでしょう。
選び方①投資したい商品を取扱っているか
iDeCoで運用できる商品は、金融機関によって異なります。
そのため、iDeCoの申込後に「運用したい商品の取り扱いがなかった…」ということもありえるのです。
投資信託の取扱い本数・定期預金の数など、自分がどの商品で運用したいのかをある程度決めた上で、金融機関を選択することをおすすめします。
※iDeCo取扱本数は2024年12月10日時点
選び方②運営管理手数料はいくらかかるか
iDeCoは、運営管理手数料がかかる金融機関もあります。
運用後に「思ったよりコストがかかって損した気分…」とならないためにも、手数料の額も考慮して金融機関を選びましょう。
特に銀行などでは、条件に満たない場合や選択したプランによっては、運営管理手数料がかかってしまいます。
できるだけコストを抑えたい人は、SBI証券 や楽天証券 のような運営管理手数料が無料の金融機関を検討すると良いでしょう。
※2024年12月10日時点
選び方③サービス内容は充実しているか
iDeCoのサービス内容も、金融機関によって異なります。
自分に合った使いやすい金融機関を選べば、申込後もストレスなく運用しやすい上に、便利なサービスを利用しながら運用することもできるでしょう。
例えば、ロボアドバイザーでおすすめ商品を提案してもらえたり、コールセンターの問合せが仕事終わりにできたりするなど、各社に特徴があります。
運用したい商品の取扱いや手数料を確認した上で、さらに使い勝手の良い金融機関を選びたい場合は各社のサービスも確認すると良いでしょう。
iDeCo(イデコ)のおすすめ金融機関11社比較表まとめ
5大ネット証券で比較
| 金融機関 | 運営管理手数料 | 投資信託※ | 定期預金※ | 保険有無 | コールセンター受付 | 店舗対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBI証券 | 0円 | 83 | 4 | 無 | 平日・土・日 ※土・日は新規の問い合せのみ | |
| 楽天証券 | 0円 | 34 | 1 | 無 | 月~金 10~19時 土・日・祝 9~17時 ※年末年始を除く | |
| 松井証券 | 0円 | 28 | 0 | 無 | 月~金 8時30分~17時 | |
| 三菱UFJ eスマート証券(旧:auカブコム証券) | 0円 | 26 | 1 | 無 | 月~土 ※土・日、祝日、振替休日、年末年始、メンテナンス日を除く | |
| マネックス証券 | 0円 | 27 | 1 | 無 | 月~金 9~20時 土 9~17時 |
※iDeCo取扱本数は2024年12月10日時点
大手金融機関6社で比較
| 金融機関 | 運営管理手数料 | 投資信託※ | 定期預金※ | 保険有無 | コールセンター受付※3 | 店舗対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大和証券 | 0円 | 20 | 1 | 無 | 月~金 10~18時 | |
| 野村證券 | 0円 | 34 | 1 | 無 | 月~金 土・日 9~17時 | |
| イオン銀行 | 0円 | 23 | 1 | 無 | 月~金 9~21時 土・日 9~17時 | |
| りそな銀行 | 0円 ※1 | 28 | 2 | 無 | 月~金 9~21時 土・日 9~17時 | |
| みずほ銀行 | 260円 ※2 | 33 | 1 | 無 | 月~金 9~17時 | |
| ソニー銀行 | 319円 ※2 | 31 | 0 | 無 | 月~金 9~17時 |
※iDeCo取扱本数は2024年12月11日時点
※1:りそなiDeCo(運営管理機関手数料無料型)を選択の場合。
※2:支払先はみずほ銀行。条件達成で0円。条件等の詳細についてはこちら(ソニー銀行公式サイト)。
※3:年末年始、祝日、メンテナンス日を除く。
金融機関に支払う運営管理手数料は各金融機関で異なります。
運用コストを重視する場合、無条件で0円のSBI証券や楽天証券 がおすすめです。
また、取扱商品数や種類、コールセンターの受付時間にも違いがあります。
購入したい商品があったり、連絡しやすい時間に受付対応していたりする金融機関を探しましょう。
なお、店舗対応は、ネット証券やネット銀行では店舗そのものがないので受け付けません。
iDeCoに関するよくある質問
iDeCoはおすすめしないって噂は本当?
iDeCoには以下のような注意点があります。
iDeCoの注意点
- 原則として60歳まではお金を引き出せず、途中解約もできない
- 加入可能年齢は65歳未満
- 運用できる商品の種類が限られている
- 運用商品の中に元本保証されないものがある
- 手数料がかかる
- 受取時には原則課税される
- 受け取れる年金額が事前に分からない

60歳まで引き出せずに途中解約もできないんですね…
そのため、余剰資金のない人 や短期で利益を狙いたい人 にはあまりおすすめしない制度です。

いつでもお金を引き出せるようにしておきたい人は、iDeCoではなくNISAを検討してみましょう。
NISAはiDeCoと同じく運用益に税金(20.315%)がかからない制度で、iDeCoよりも多くの商品から投資先を選ぶことができます。
ただし、掛金が所得控除の対象になるなどの税制優遇がない点には注意が必要です。
「60歳までお金を引き出せないの嫌だ」という人はNISAを、「60歳まで引き出せなくても良いから投資をしながら税制優遇も受けたい」という人はiDeCoを選ぶと良いでしょう。
どちらも捨てがたいという人は併用するとよいでしょう!

※1 楽天証券調べ
※2 2023年3月期 通期(2022年4月~2023年3月)の委託個人売買代金シェアです。SBIの数値は、SBIネオトレード証券の数値を含みます。(出所:東証統計資料、各社WEBサイトの公表資料より当社集計、各社委託個人(信用)売買代金÷{株式委託個人(信用)売買代金(二市場1,2部等)+ETF/REIT売買代金}にて算出)。
iDeCoとNISAの違いは?
iDeCoとNISAの違いは次の3点です。
iDeCoとNISAの違い
- 加入できる条件
- お金を引き出せるタイミング
- 税金の優遇措置
NISAは、18歳以上なら誰でも加入できて年齢に上限がありません。
一方で、iDeCoは、新規加入可能年齢が65歳未満です。
また、お金を引き出せるタイミングも異なります。
iDeCoはNISAのように、好きなタイミングで引き出すことはできません。
積み立てたお金を自由なタイミングで使いたい方には、NISAのつみたて投資枠を利用するのがおすすめです。

※1 楽天証券調べ
※2 2023年3月期 通期(2022年4月~2023年3月)の委託個人売買代金シェアです。SBIの数値は、SBIネオトレード証券の数値を含みます。(出所:東証統計資料、各社WEBサイトの公表資料より当社集計、各社委託個人(信用)売買代金÷{株式委託個人(信用)売買代金(二市場1,2部等)+ETF/REIT売買代金}にて算出)。
※3 カードの種類・カード年間利用金額等によりポイント付与率が異なります。くわしくはこちら(三井住友カード公式サイト)に掲載。
iDeCoがおすすめな理由は何?
iDeCoを活用して老後に向けた資産形成をすれば、次のようなメリットを享受できます。
iDeCoがおすすめな理由
- 定期預金や年金保険、投資信託を運用して利益を得ることができる
- 運用益は非課税になる
- 掛金が全額所得控除される
- 受取時に一定額が非課税になる
- 運用の手間が少ない
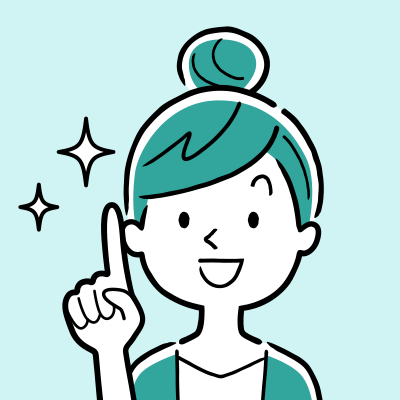
iDeCoを始めると税金周りでお得になる部分が多いんですね
NISAと同様に運用益が非課税になることも特徴的ですね

iDeCoは、老後に向けて公的年金にプラスして給付が受け取れる「自分用の年金」です。
老後のライフスタイルを充実させるためにも、若い世代から始めることをおすすめします。
公務員にもiDeCoはおすすめできる?
「公務員はiDeCoをやめたほうがいい」と言われることもありますが、公務員であってもiDeCoのメリットは十分に受けられます。
ただし、掛金の上限額は会社員等に比べると低く設定されており、税制優遇のメリットが小さくなってしまうのも事実です。
それでも月額1.2万円分は購入できるので、それ以内での掛金拠出を考えている人は問題ありません。

iDeCoの掛け金は5,000円からでも大丈夫?
iDeCoは最低掛け金の5,000円から始めたとしても十分に意味があります。
ただし、掛け金が少ないと所得控除のメリットが少なくなってしまうので注意しましょう。
iDeCoの掛け金の目安は目標積立額からの逆算がおすすめです。
まとめ
iDeCoは、老後に向けた資産形成に最適で、節税効果もあります。
掛金は全額所得控除の対象となり、運用益は非課税で、受け取る際も控除を受けられます。
しかし、60歳になるまでは原則として引き出すことができないので、無理のない範囲で掛金を決めましょう。
投資対象の商品も色々とあるので、自分で決められるよう、投資の知識も必要です。
投資商品の選定について自信がない場合は、ロボアドバイザーを利用できる証券会社などがおすすめです。
目標金額に近づけられるような資金運用ができるよう、掛金や運用商品をよく考えてiDeCoを利用しましょう。

・記事内に記載しているポイント付与率は、2024年10月10日(木)積立設定締切分(2024年11月買付分)以降のものです。対象カードごとのカード利用金額などに応じたポイント付与率となります。
・特典を受けるには一定の条件がありますので、詳細はこちら(三井住友カード公式サイト)で確認ください。
・三井住友カードつみたて投資の利用金額は、プラチナプリファードの新規入会&利用特典、継続特典の付与条件である利用金額の集計対象となりません。




















