
iDeCo(イデコ)の始め方6ステップをまとめて解説!会社員・公務員の注意点は?
最終更新日:
このページにはPRリンクが含まれています
また当サイトで得た収益は、サイトを訪れる皆様により役立つコンテンツを提供するために、情報の品質向上・ランキング精度の向上等に還元しております。※提携機関一覧
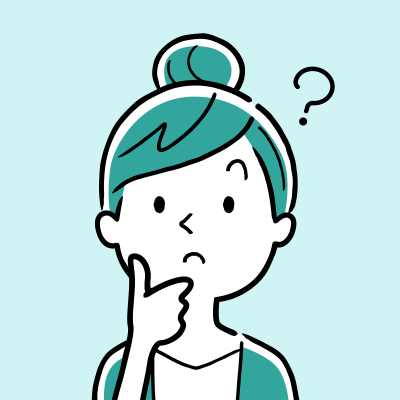
- iDeCoの始め方を知りたい!
- iDeCoを始めるにはいつ・どこで何をしないといけないか教えてほしい!
iDeCoの始め方は次の6STEPです。
iDeCoの始め方
iDeCoを始める時は、「こんなはずではなかった…」とならないように、以下の注意点を覚えておきましょう。

iDeCoを始める時の注意点
- 原則60歳まで引き出せない
- 条件によっては加入できない人もいる
- 手数料などのコストがかかる
- 受け取り方法によっては課税される場合がある
この記事では、iDeCoの始め方や、申込に必要なものを解説します。
最後まで読めば、iDeCoの始め方を理解し、手続きをスムーズに行うことができるでしょう。

主要ネット証券No.1

ファイナンシャルプランナー
監修者石原玄紀
中京大学経済学部卒業後、FP事務所に入社。2005年にはCFPを取得。
その後、トヨタファイナンシャルサービス証券(現:東海東京証券)、東海東京ウェルス・コンサルティングにて、経営企画や営業、大手税理士法人への出向、富裕層部署の相続コンサルタントとして従事。
2020年にIFA(独立系金融アドバイザー)「きわみアセットマネジメント」へ初期メンバーとして入社後、2023年に独立。
中京大学付属中京高校で資産形成に関する授業の実施経験もあり。
イーデス編集部 / 株式会社エイチームフィナジー
編集者小林 梨沙
1989年生まれ、愛媛県松山市出身。
大学卒業後、株式会社ブリッジインターナショナルに入社。外資系教育サービス会社にて、薬機法や品質マネジメントシステムのインサイドセールスを担当。その後、スーパーバイザーとして、日系大手企業のインサイドセールスプロジェクトの立ち上げを行う。
2019年に株式会社エイチームフィナジーに入社。FX、新規事業開発部を経て、イーデスの編集者に就任。
気になる内容をタップ
iDeCoの始め方
iDeCoは次の6STEPで始めることができます。
iDeCoの始め方
STEP1:加入資格の有無を確認する
| 加入資格あり | 加入資格なし | |
| 年齢 | 20歳~65歳 | 20歳未満 or 65歳以上 |
| 国民年金 保険料 | 支払いあり | 支払いなし |
| 居住地 | 日本国内 | 海外(※) |
| 農業者年金 | 加入なし | 加入あり |
| 企業型DC (企業型確定拠出年金) | なし or あるが、iDeCoの併用OK | あるが、 iDeCoの加入NG |
※国民年金に任意加入していない場合
日本国内に住む20歳~65歳で国民年金に加入していれば、ほとんどの人がiDeCoに加入できます。
国民年金保険料が未納・免除・納付猶予の場合は加入できません。
過去に未納や免除になっていても、現在そうではないという人は問題ありません。

また、原則日本国内居住者という条件もありますが、国民年金に任意加入している海外居住者は、iDeCoの加入が認められます。
なお、農業者年金に加入している人は、iDeCoに加入できません。
企業型確定拠出年金(DC)に加入している人も、iDeCoの加入が規約で認められていないケースがあるので注意しましょう。
STEP2:掛金の上限額を確認して設定額を決める
iDeCoの掛金額を決める時のポイント
- 職業毎で異なる掛金額の上限を確認
- 月々5,000円~、1,000円単位で掛金額を決める
- ライフプランを考慮する
60歳まで原則引き出しできないことを踏まえ、iDeCoの掛金は、余力が残るように決定しましょう。
掛金額は途中で変更できますが、年1回だけなので、余裕を持った金額に設定することをおすすめします。

掛金を決める時は、始めに自分の上限額を確認します。
加入者の職業によって異なるので、自分がどこに該当するかをしっかり確認しましょう。

上限が分かったら、5,000円~上限額の範囲内で、掛金額を考えます。
今の収入やライフスタイルだけでなく、退職や転職、結婚、出産など、ライフプランの変更でまとまった資金が必要になる可能性も考慮しつつ掛金額を決めましょう。
万が一の場合に支払いを止めることもできますが、即座に停止するわけではないので注意してください。

STEP3:運用商品を決める
iDeCoの掛け金を決めたら、次は、運用する金融商品を選びます。
どの運用商品を選ぶかで運用成績が変わるため、それぞれの特徴を知って、自分の希望に合ったものを選びましょう。
iDeCo(イデコ)の運用商品は、大きく分けると次の2種類があります。
| 特徴 | ||
| 定期預金 保険 | 値下がりリスクがなく安全性が高いが、低金利下での運用ではリターンに期待できない | |
| 元本 変動型 | 投資信託 | 株や債券、ETFなどに投資信託を通じて間接投資でき、大きな運用益を得られる可能性があるが、元本割れのリスクもある |
元本保証型(定期預金・保険)がおすすめな人
元本保証型(定期預金・保険)がおすすめな人
- 元本を減らしたくない人
| リスク | 特徴 | 注意点 |
| 低 | 値下がりリスクがない | 手数料負けする可能性がある |
元本保証型は、定期預金や保険など、値下がりリスクのない商品を選べるため、安全性が高いのが特徴です。
ただし、どの金融機関を利用しても、国民年金基金連合会や事務委託先金融機関への毎月の手数料が発生し、コストがかかります。
また、金融機関によっては、口座管理手数料が毎月かかるケースもあります。
そのため、値上がりによる利益が少ないと、手数料負けする可能性がある点に注意しましょう。
元本変動型(投資信託)がおすすめな人
元本変動型(投資信託)がおすすめな人
- 様々な投資商品に分散投資したい人
- 元本割れのリスクをとっても運用益を狙いたい人
iDeCoで投資信託を運用する時の商品選びでは、次の2つが重要です。
- 何に投資しているか
- どのように運用しているか
投資信託には様々な種類がありますが、その中でも代表的なものを下図にまとめました。

投資信託は、投資対象、運用方法で分類でき、特徴やリスクが異なります。
株式に投資する投資信託は、国内外ともに値動きが大きくなりやすい傾向です。
特に海外株式は、価格変動に加えて為替変動も発生するため、ハイリスク・ハイリターンと言えるでしょう。

一方、国内債券や海外債券は、株式よりも値動きが緩やかで比較的安全な資産と言えます。
ただし、海外債券は、為替変動の影響を受けるため、国内債券よりも値動きが大きくなる可能性があります。
投資信託には、国内外の株式や債券、REITなど複数の金融商品を組み合わせた「バランス型」と呼ばれるものもあります。
世界中の金融商品に投資できるため、バランスよく投資できてリスク低減も図れます。
中には比較的値動きが大きいものもあるので気をつけましょう。

STEP4:口座開設する金融機関を決める
金融機関を決めるチェックポイント
- 投資したい商品を取扱っているか
- サービス内容は充実しているか
- 運営管理手数料はいくらかかるか
一口にiDeCoといっても、金融機関によって、投資信託の取扱本数や定期預金の数、保険の有無などに違いがあります。
投資する商品を考えた上で、取扱いの有無を金融機関で確認しましょう。
また、店舗対応があるかどうかや、コールセンターの受付時間などの違いも気にしておいた方が良いでしょう。
忙しくて日中に電話するのが難しい人は、なるべく遅くまで受け付けている金融機関を選ぶと使い勝手が良いです。

iDeCoは、金融機関によって、運営管理手数料がかかるところもあるため、手数料の額も考慮して選びましょう。
主な金融機関の特徴は、以下の表にまとめています。
| 金融機関 | 運営管理 手数料 | 投資信託 | 定期預金 | 保険有無 | コールセンター受付 | 店舗対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBI証券 (セレクトプラン) | 0円 | 37 | 1 | 有 | 月~金: 8~17時 | |
| 楽天証券 | 0円 | 31 | 1 | 無 | 月~金: 10~19時 土: 9~17時 | |
| 松井証券 | 0円 | 39 | 1 | 無 | 月~金: 8時30分~17時 | |
| 三菱UFJ eスマート証券(旧:auカブコム証券) | 0円 | 26 | 1 | 無 | 月~金: 9~20時 土: 9~17時 | |
| マネックス証券 | 0円 | 26 | 1 | 無 | 月~金: 9~20時 土: 9~17時 |
| 金融機関 | 運営管理手数料 | 投資信託 | 定期預金 | 保険有無 | コールセンター受付 | 店舗対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大和証券 | 0円 | 21 | 1 | 無 | 月~土: 10~18時 | |
| 野村證券 | 0円 | 31 | 1 | 無 | 月~金: 9~20時 土: 9~17時 | |
| イオン銀行 | 0円 | 23 | 1 | 無 | 月~金: 9~21時 土・日・祝: 9~17時 | |
| りそな銀行 | 年 3,864円 ※1 | 27 | 2 | 無 | 月~金: 9~21時 土・日: 9~17時 | |
| みずほ銀行 | 260円 ※2 | 30 | 1 | 無 | 月~金: 9~21時 土・日・祝:9~17時 | |
| ソニー銀行 | 319円 ※2 | 28 | 0 | 無 | 月~金: 9~20時 土・日: 9~17時 |
※1:加入後2年間無料
※2:条件達成で0円
※iDeCoの取扱商品は2023年10月24日時点
金融機関選びで迷う人には、3つのポイントに当てはまる以下のような証券会社をおすすめします。

以下条件を選定基準としています。
①運営管理手数料が無料、もしくは、無料になる条件がある
②選べる商品数が20本以上
STEP5:口座開設を申込む
| 所要時間 | 始め方 | |
|---|---|---|
STEP1 | 5分 | 口座開設したい金融機関に必要書類を請求 |
STEP2 | 7日 | 受け取った必要書類に必要事項を記入 |
STEP3 | 1日 | 必要書類を金融機関に提出 |
STEP4 | 1~2ヶ月 | 口座開設完了のお知らせが届く |
会社員や公務員は、勤務先に依頼して「事業主証明書」という書類を発行してもらう必要があります。
また、勤め先によっては、年金手帳を会社に預けるケースもあるため、手元にない場合は、あわせて申請し、基礎年金番号も確認しておきましょう。
なお、iDeCoの申し込みをすると、国民年金基金連合会の審査を受けるので、申請書類に不備や間違いがないようにしてください。
以下では、楽天証券とSBI証券のiDeCoの始め方を紹介します。

楽天証券のiDeCoの始め方
| 所要時間 | 始め方 | |
|---|---|---|
STEP1 | 5~10分 | 楽天証券iDeCoの公式サイトで加入者情報を入力して資料請求 |
STEP2 | 4~5日 | 資料を受け取り、申込書類を確認 |
STEP3 | 5分 | [事業所登録申請書 兼 |
STEP4 | 7分 | 個人型年金加入申出書や預金口座振替依頼書などの書類に記入 |
STEP5 | 30日 | 申込書類を郵送し、口座開設完了 |
楽天会員は、氏名や性別、生年月日、住所、電話番号、メールアドレスなどの入力を省略できます。
最初に、楽天証券口座や楽天会員について選択するので、間違いがないようにしましょう。
掛金の納付方法は、銀行引き落としと会社経由での納付を選ぶことができます。
申出書には、最初から基本情報などが印字されているため、記入する項目が少なくて済みます。
SBI証券のiDeCoの始め方
| 所要時間 | 始め方 | |
|---|---|---|
STEP1 | 3分 | WEBサイトで加入者情報を入力して資料請求 |
STEP2 | 14~23日 | 届いた資料を確認して資料に必要事項を記入 |
STEP3 | 1日 | [事業所登録申請書 兼 |
STEP4 | 10分 | 「個人型年金加入申出書」や |
STEP5 | 5分 | 「本人確認書類」のコピーを用意して貼付 |
STEP6 | 1~2ヶ月 | 申込書類を郵送し、口座開設完了 |
SBI証券でiDeCo口座を開設する場合、まずは公式ホームページから資料を請求してください。
その際に、チェックを入れておくと、申込書類にある程度の項目を印字してもらうことも可能です。
資料が届くまで2~3週間程かかるので、必要書類などはその間に準備しましょう。
掛金配分設定届もあるので、よく考えて記入してください。
初心者~上級者まで幅広い層におすすめ
公式サイトはこちら
STEP6:初回掛金が引き落とされる
iDeCo口座の開設を申し込むと、加入審査が行われて個人型年金加入確認通知書が届きます。
通知が届くことで加入完了となり、到着した月の26日に初回引き落としが行われます。
申込日が早ければ初回引き落としは1か月分ですが、月末になった場合などは2か月分となります。
引き落とし日と引き落とし額は、通知書同封の引き落としのお知らせで確認できます。
iDeCoの初回掛金の引き落としはいつから始まる?
- 初回引き落とし日は、個人型年金加入確認通知書が届いた月の26日
- 申込日が月末の場合などは、初回に2か月分引き落とされることもあるので注意
iDeCoでは、原則として毎月の掛け金を翌月26日に銀行等の預金口座から振替で納付します。
※26日が休業日であれば、振替は翌営業日です。
iDeCoの口座を開設したのがどの金融機関であっても、初回の掛け金の引き落とし日は26日です。
原則として、加入月は加入申出書を受け付けた金融機関の受付月です。
申出書を提出してから加入審査が行われ、基本的には1か月後の26日に初回の掛金が引き落とされます。
そのため、例えば4月1日に受け付けた場合の加入月は4月で、初回の引き落とし日は5月26日となります。
iDeCoを始める時の注意点
iDeCoを始める時の注意点
- 原則60歳まで引き出せない
- 条件によっては加入できない人もいる
- 手数料などのコストがかかる
- 受け取り方法によっては課税される場合がある
iDeCoは、勤務先を退職しても原則60歳までは引き出すことができません。
脱退して一時金を受け取ることは可能ですが、条件のハードルが高く難しいので、急に大きな支出があった時に備えて別途貯金等をしておく必要があります。
また、iDeCoは誰でも加入できるわけではないので、加入条件をよく確認しましょう。
税制優遇があるためお得なイメージがあるものの、手数料や維持費などのコストがかかることにも注意が必要です。
iDeCoは積立額を一時金として受け取る場合や年金で受け取る際に、課税されることがあります。
特に、退職金と一緒に一時金を受け取る場合は、控除額がiDeCoとの合算になるので、注意してください。

会社員がiDeCoを始める時の注意点
- 会社で企業型確定拠出年金に加入していると、iDeCoに加入できないことがある
- 企業年金制度によって、掛金の上限額が異なる
企業型確定拠出年金の規約によっては、iDeCoとの同時加入を認めていないものもあります。
iDeCoの加入を検討している場合は、加入している企業型確定拠出年金の規約を確認しましょう。
企業型確定拠出年金の規約に関するルールは、2022年10月以降に緩和されることが決まっています。
緩和後は、企業型DCに加入している方も、原則、iDeCoに加入できるようになります。ただし、企業型DCにて加入者掛金を拠出(マッチング拠出)している場合などには、iDeCoに加入できません。
また、会社が導入している企業年金制度によって、iDeCoの掛金上限額が異なります。
企業年金なしの場合は月額2.3万円が上限ですが、企業年金制度への加入状況によって、月額2.0万円や1.2万円が上限になります。
公務員がiDeCoを始める時の注意点
- 公務員は掛金の上限額が低い
- 所得控除による税負担の軽減効果が少ない
公務員がiDeCoに加入した場合、掛金の上限額は月額1.2万円と決まっています。
企業年金がない会社員なら月額2.3万円、自営業者なら月額6.8万円が上限なので、掛金の上限はかなり低いといえるでしょう。
公務員は、一般的な会社員よりも、年金制度や退職金などの面で優遇が大きいため、iDeCoの掛金の上限は低く設定されています。

また、iDeCoを利用すると、税負担の軽減効果に期待できますが、公務員はそもそもの掛金が少ないため、税負担の軽減効果にもあまり期待できません。
資産を普通預金に預け入れるよりはメリットが大きいものの、他の制度などとよく比較検討したほうがいいでしょう。
専業主婦がiDeCoを始める時の注意点
- 収入がないと所得税や住民税の節税ができない
- 配偶者とのバランスを考える必要がある
iDeCoは、掛金に応じた所得控除と、所得税や住民税の軽減が大きなメリットです。
しかし、収入がないので所得税がかからず、住民税も非課税である専業主婦は、メリットを十分に享受できません。
運用益は、非課税になるので、まったくメリットがないというわけではないのですが、会社員などと比べると、節税効果は小さくなるでしょう。
また、配偶者と共にiDeCoに加入するのであれば、バランスを考えなくてはいけません。
商品や運用時期の選択次第では、2人とも運用益がマイナスになる可能性があるので、リスクが分散できるように、種類やタイプを分けて運用したほうがいいでしょう。
学生がiDeCoを始める時の注意点
- 被保険者として国民年金を納めている必要がある
- 社会人になってから、年金資産移換手続きが必要になる可能性がある
学生納付特例制度の申請をして納付の猶予を受けている学生は、iDeCoに加入できません。
iDeCoに加入するには、国民年金に加入して保険料を納める必要があります。
※学生が年金を納める場合は、国民年金第1号被保険者として扱われるので、iDeCoの掛金上限額は自営業者と同じく、月6.8万円です。
社会人になってからのiDeCoの扱いにも注意が必要で、企業型確定拠出年金制度を導入している会社の場合、iDeCoと同時加入ができないものもあります。
その場合、年金資産移換手続きをする必要があり、その分手間がかかります。
iDeCoの始め方に関するよくある質問
Q.iDeCoは何月に始めるのがおすすめ?
A.思い立ったらすぐ始めましょう。
iDeCoは、なるべく早く始めたほうが効果が高くなるため、本来なら思い立ったらすぐに始めるべきです。
年末調整のことも考慮すると、7月までに始めるのがおすすめです。
iDeCoの掛金の払込証明書は10月以降に郵送で送付され、そこに記載される掛金は9月までに支払った分となります。
そのため、9月に初回の引き落としを終えてその年の年末調整で申告するには、7月までに申し込んだほうがいいのです。
Q.iDeCoはどこで始められるの?
A.銀行や証券会社、信用金庫、保険会社、労働金庫など、様々な金融機関で始められます。
金融機関ごとに特徴があり、商品のラインナップや手数料などは異なっています。
どこの金融機関がいいのか、比較検討しながら決めましょう。
Q.iDeCoを会社に知られたくないけどバレないやり方はある?
A.会社にバレない方法はありません。
厚生年金や共済組合などに加入している人がiDeCoに加入する場合、事業主の証明が必要なので、会社には必ずバレます。
しかし、制度変更により、2024年12月以降を目途に事業主証明書が廃止されるので、それ以降なら、会社にバレずに加入できるでしょう。
まとめ
ideCoの始め方は、加入条件を確認後、商品や金融機関を決め、申し込み方法に従って手続きをします。

加入条件を満たしていれば、加入することは問題ありません。
しかし、加入方法は金融機関によって若干異なる点があるので注意してください。
また、加入者によって注意点もあるので、考慮したうえで加入の手続きを始めましょう。













