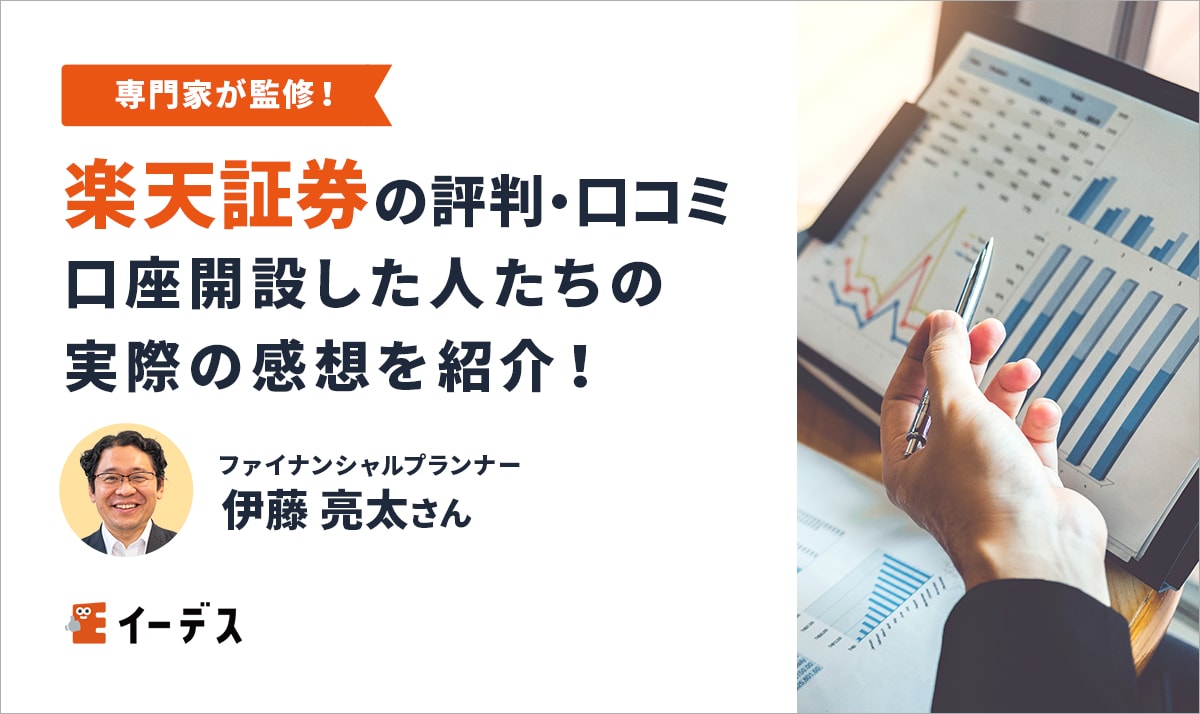「お金のことはできるだけ考えたくない派」の私が始めた、資産運用と投資の話
最終更新日:
このページにはPRリンクが含まれています
また当サイトで得た収益は、サイトを訪れる皆様により役立つコンテンツを提供するために、情報の品質向上・ランキング精度の向上等に還元しております。※提携機関一覧
将来のお金に関する漠然とした不安から、資産運用に興味はあるものの「何から始めればいいのか分からない」と感じている人は多いのではないでしょうか。
特に「投資」は複雑で難しそうな印象から、一歩を踏み出せないという人も少なくなさそうです。
今回寄稿いただいたエンジニアのSongmuさんも、投資に対し手続きや運用に手間がかかりそう、と長らく投資を始めてこなかったと語ります。
そんなSongmuさんは、検討を経て手間と時間がかからないものを選び、iDeCo(イデコ)やつみたてNISAから投資をスタート。
実際に運用を開始する前と後で感じたことや、検討し「やらなかったこと」など振り返っていただきました。
Songmuです。ソフトウェアエンジニアをしています。
40代前半で、東京郊外のマンションに妻と小学校低学年の子供二人と住んでいます。
筆者は、40歳を超えてライフステージが変化する中で、資産形成を意識するようになりました。
とはいえ労力やリスクが高い投資は避けたい。
そのため、iDeCoやつみたてNISAを始めるという無難な選択肢に落ち着きましたが、いつかやらなきゃと後回しにしていた人生のタスクが片付いてスッキリしました。
また、少しは金融リテラシーも身に付け、なんとなく安心感も得られるようになり、将来のお金について気にすることも減りました。本記事はその経緯をまとめたものです。
筆者が実施したことは、もちろん投資で大儲けを狙うような内容では決してありません。ただ、
- 特に投資などはおこなっていないが漠然と資産形成の必要性を感じている
- 銀行預金がそれなりの金額にはなっている
- 月に数万円程度であれば無理なく積み立てられる収入がある
上記のような方は、数年前の私に近い状況であり、この記事が参考になる部分があるかもしれません。

ソフトウェアエンジニア
監修者Songmu
都内企業で働くソフトウェアエンジニア。GoやPerl(いずれもプログラミング言語)を中心に200個以上のツールやモジュールをオープンソースソフトウェアとしてGitHub上に公開している。自身のブログやSNS等でも技術に関する話題をはじめ、日常の雑感などを含め定期的に更新している。著書に『みんなのGo言語 [現場で使える実践テクニック]』(共著)等。

株式会社エイチームライフデザイン
編集者イーデス編集部
「ユーザーが信頼して利用できるWEBメディア」を目指す編集部チーム。実際のユーザーの声や業界知識の豊富な専門家の協力を得ながら、コンテンツポリシーに沿ったコンテンツを制作しています。暮らしに関するトピックを中心に、読者の「まよい」を解消し、最適な選択を支援するためのコンテンツを制作中です。
■書籍
初心者でもわかる!お金に関するアレコレの選び方BOOK
■保有資格
KTAA団体シルバー認証マーク(2023.12.20~)
■許認可
有料職業紹介事業(厚生労働大臣許可・許可番号:23-ユ-302788)
気になる内容をタップ
資産運用を本格的に見直す前にしていたこと
筆者はお金にあまり興味がありません。
逆に興味がないからこそ、それについて考えずとも、お金に煩わされることなく、今や将来の生活で不自由したくはない、という贅沢な考えを持っています。
つまり、仕事以外でお金について手間をかけたり考えたりする時間を最小にして、資産運用をしたいのです。
ただ、これまでやっていたこととしてはメイン口座に必要以上にお金を入れておく事による無駄遣い防止のため、別口座に自動送金したり、保険に加入したりしていた程度。資産運用とも言えないレベルです。
保険については2015年に子供が生まれた頃、妻に言われるまま学資保険に加入し、2016年のマンション購入時に団信(団体信用生命保険)に加えて貯蓄型の生命保険に加入しました。
「保険は貯蓄」とはよく言われる売り文句であり、時には否定的な意味合いで使われることも承知していましたが、この点については受け入れていました。
実際、それで自分に急な不幸が降り掛かっても、家族が路頭に迷うことはないだろうという安心感は得られていたためです。
ただ資産として考えた場合、保険や、タンス預金さながら利子もほとんどつかない銀行預金だけということに関しては、薄々課題意識は感じていましたが棚上げにしていました。
またこの頃、自分が投資に対して感じていた懸念には以下のようなものがありました。
- 投資銘柄選定の面倒臭さ
- 元本割れ等のリスク懸念
- 利益に対する課税、確定申告などの手続き
- 資産が分散することによる管理の煩雑さ
今思えば大したことではないですが、これらの懸念もあったため、当時所属していた企業には企業型DC(企業型確定拠出年金)があり、iDeCoやNISAなどの話を聞くこともありましたが、手が出せませんでした。
資産を見直し、投資を始めようと思うまで
資産運用の見直しや投資自体を億劫に感じ長らく棚上げにしていましたが、2019年頃、いわゆる「老後資金2000万円問題」が公表されたのが話題になり、世の資産形成に関する情報を耳にすることが増えました。
同世代のエンジニア仲間の間でも関心が高まっており、友人が「エンジニアのための自分で始めるファイナンシャルプランニング 」という勉強会を開催し、それに参加したのを覚えています。
2020年になると、私が普段情報収集に使っているはてなブックマークでも、ソフトウェアエンジニアの方が書かれた「普通の人が資産運用で 99 点をとる方法とその考え方」という記事が話題になり(私も言ってしまえば、この記事の内容をほぼなぞって実践していますので、この記事は必読と言えます)、それからすぐに新型コロナウイルス感染症の世界的流行が始まりました。
コロナ禍をきっかけに、将来への不安を多くの人が感じるようになったのではないでしょうか。
私個人的にも、40歳の節目や、転職をして一時スタートアップの経営層となったこと、親族の不幸を期に自分の死に方も考えるようになったこと、子供の将来の可能性などを意識し、老後や少し先の生活を見据えた資産形成を以前よりも考えるようになりました。在宅勤務で時間ができたことにより、それらについて考える時間ができたというのもあります。
とはいえ、冒頭に述べたような懸念があり、手間が増えたり、リスクを気にしたりするなど、お金について気を取られる時間が増えることには不安がありました。
しかし、友人と情報交換したり、上記に挙げたようなネット記事や本を何冊か読む中で、それらの懸念はほとんど払拭されました。
あまり多くの本を読んだわけではありませんが『元財務官僚が5つの失敗をしてたどり着いた これからの投資の思考法』(柴山和久)という本は、「長期・積立・分散」という投資の基本的な考え方について書かれていて、読みやすくおすすめです。
特にiDeCoやNISAに関してはリスクや手間が少なく設計されていることが分かりました。
冒頭の懸念に対応する形でまとめると以下のようなことです。
投資銘柄選定の面倒臭さ
- 定番の銘柄を選んで設定すればいい
- 一度設定すれば後は基本放置でも良いし、むしろ放置が得策
- 初心者や手間をかけたくない方に優しい制度になっている
元本割れ等のリスク懸念
- リスクは少なく、リスクが少ない範囲でやれば良い
- iDeCoやつみたてNISAはリスクを軽減する「長期・積立・分散投資」がしやすい仕組み
- 当座の現金は確保したうえで、無理のない範囲で投資を行うでも十分
利益に対する課税、それに伴う確定申告の手続き
- iDeCoやNISAは運用益が非課税
- つみたてNISAは基本確定申告不要。iDeCoも会社員の場合は年末調整での申告で対応できるケースが多い
資産が分散することによる管理の煩雑さ
- 「分散投資」は必須。円だけを持っておくこともリスクと言える
- その上で「ネット経済圏」を意識して利用サービスを寄せれば煩雑ではない
実際に始めたこと、やらなかったこと
検討を踏まえ、実際にやったことは以下です。
同じことをされている人も多いかと思いますが、とにかく資産運用にかける手間と時間をかけずにできるもの、という視点で選択しました。
やったこと
- iDeCoを始め、上限まで積み立て
- つみたてNISAを始め、上限まで積み立て
- 現金預金の一部で投資信託を購入
購入する銘柄はいずれもインデックスファンドという、長期的に見ると世界の市場全体の経済成長率に合わせた利回りが期待できる投資信託に絞っています。
投資信託は、運用会社が株式や債券など複数の様々な資産に分散投資してくれる金融商品なので、資産運用において重要とされる考え方の一つとされる分散の原則を満たせます。
これらは、最初に手続きや銘柄指定は必要ですが、一度設定してしまえば後は放置です。
筆者の場合、年に一回年末年始に銘柄の見直しをしていますが、組み替えたことは今のところはありません。
(ただし転職をした場合、iDeCoについては必ず手続きが必要になるので注意)
ちなみにこのときやった皮算用として、つみたてNISAは年間40万で20年間積立できるため、年利3%という悲観的な利回りだとしても20年後には1,000万円を超える、というのがありました。
夫婦でそれぞれ20年間手を付けずに放置しておけばそれだけで老後2,000万円問題をクリアできるという寸法です。
このあたりは新NISAで変わる部分もありますが、大きく下ぶれすることは考えにくいでしょう。

続いては、検討したけれどやらなかったこと、やめたことです。
いずれも「手間や時間をかけたくない」を重視した結果、自分には合わないと感じたものがほとんどです。
やらなかったこと、やめたこと
- ドル・外貨積立
- ロボアドバイザー(人工知能を使ったAI投資の一種。金融商品や資産配分の調整提案を行い、自分で対応するものから、その後の運用まで自動で行ってくれるタイプのものもある)
- 個別株投資
ドルや外貨積み立ては分散投資の観点からも有効だと思いますが、税金計算が煩雑になりそうなのでやめました。
ロボアドバイザーについては、確かにこの領域でのAI活用は今後も進んでいくでしょうし、期待もしています。ただ、手数料が高めなことと、証券口座をさらに増やしたくないというのもあり、見送りました。
個別株投資は元々積極的にやっていたわけではありませんが、ストックオプションで取得した以前の職場の株式があり、この大半を売却しました。
ストックオプションで取得した株式も結局のところ個別株でしかないため、その上下に一喜一憂してメンタルシェアを奪われるよりかは、別のところに資産を割り当てた方が良いと考えたからです。少し寂しい気もしたので、応援の意味も込めて一部はまだ所持しています。
実際に運用をしてみて
当初資産を分散させていくことで見るべきサイトや口座が増え管理が煩雑になるのを懸念していましたが、これについては、利用するネット経済圏を寄せるようにしました。
筆者の場合、元々住信SBIネット銀行がメインバンクで、住宅ローン返済に使っていたこともあり、証券口座やiDeCoはSBI証券を選びました。
いわゆる「SBI経済圏」ですが、筆者の周りだと「楽天経済圏」に寄せている人も多く見られます。
運用状況は家計簿アプリのマネーフォワード ME上で証券口座との連携設定をしており、そこで大まかに確認しています。ただし細かくは追いかけていません。長期で見れば大体右肩上がりなので良し、と考えるようにしています。
ちなみに、マネーフォワード MEは連携数の制限がなくなる有料プランを契約し、その上で支払いもキャッシュレスに寄せ、可能な限り口座やサービス連携をしています。
これにより、資産の増減が半自動的に情報更新され、分散している資産を一望できる状況となりました。
つまり、基本は放置で、運用状況の把握はマネーフォワード MEを眺めておくだけです。資産が自然と分散されているのを眺めておくことにより、なんとなく資産形成ができているという安心感が得られるようになりました。

この状況を作り出すための最初の手続きや作業も、やる前は億劫に感じましたが、やってみれば大したことはありませんでした。
途中で待ち時間が発生することはありますが、作業自体は合わせて丸一日程度で、ちょっと気合いを入れた大掃除くらいのものでした。
もちろん、どれくらい積み立てるか、投資するかはそれぞれの経済状況や考え方によって変わってくるでしょう。
あまり現金を持たず、いざとなれば投資信託や株式などを売却して現金を確保すればいいという考え方もあるでしょうが、個人的には手続きなどの手間をできるだけかけたくないこともあり、ある程度の現金は確保しておくようにしています。
インデックスファンド過信に対する批判もありますが、分散投資の観点からしても、資産が日本円の現金や預貯金だけであることはもはやリスクであると考えます。
今後日本円の価値が劇的に上がることは残念ながら考えづらいため、投資信託ではなくとも、日本円以外の資産を持つことは検討した方がいいはずです。
身構え過ぎず、無理のない範囲でやっていく
iDeCoやつみたてNISAを始めてから数年たちましたが、その後の変化や現在の状況について書いてこの記事を締めようと思います。
まず、iDeCoやつみたてNISAについては、年に一回、年末年始に念のため見直しをしていますが、これまで銘柄の変更などの組み換えは実施していません。
コロナ初期に多くの米国の主要IT銘柄の株価が上昇したことこともあり評価額の推移は好調です。
これについては始めたタイミングがよく、運がよかったとは思いますが、今後なんらかの恐慌で一時的に大幅に下がる可能性はありますし、そういったことが起こっても気にせずに長期目線で考えたいと思っています。
今回紹介した項目については、あくまで筆者が感じたことや体験となります。
必ずしも全員に当てはまることではないですが、投資に興味や課題意識はありつつも手をこまねいている人には、「情報収集や事前検討をしっかりおこなった上で始めよう」と考えるより、まずは、つみたてNISAやiDeCoから気軽に始めてみるのをオススメしたいです。
これらは、国が個人の金融投資を促すためにも、リスクや手間が少ないパッケージとして提供してくれているので、活用しない手はありませんし、投資初心者にとっても優しい制度です。
私自身も、これらを始めて継続してからの経験や学習を通して資産運用に対する理解が深まりました。
その結果、追加で他の金融投資にも興味を持てる精神的な余力も生まれてきたのです。
最近では、分散投資の一環として暗号通貨の積み立てを始めました。ソフトウェアエンジニアとして押さえておいた方がいい分野だとも思ったので、毎月少額ですがビットコインとイーサリアムを買い付けています。
これらは売却時に運用益に対して税金がかかりますが、積み立てているだけであれば課税はされないため、今後売却が必要になった場合に手続きについて調べようと思っています。
ちなみに、2024年から新NISAが始まるようですが、枠が増える以外はまだ何も把握していません。これも早めにキャッチアップするつもりです。
このように、自分の負担にならず、興味を持てる範囲で金融ポートフォリオ(金融商品の組み合わせ)を充実させていこうと思います。
本記事が皆様の参考になれば幸いです。
編集:はてな編集部
※画像はイメージです
※本記事に記載の情報は、著者の当時の体験をもとにした情報となります。細心の注意を払って情報を掲載していますが、最新の情報と異なる場合や、正解を示すものではない点についてご了承ください。