
株式投資の配当金とは?利回りって何?貰う方法や銘柄選びのポイントも
最終更新日:
このページにはPRリンクが含まれています
また当サイトで得た収益は、サイトを訪れる皆様により役立つコンテンツを提供するために、情報の品質向上・ランキング精度の向上等に還元しております。※提携機関一覧
配当金とは、株を保有していることで得られる利益のことです。
配当金を狙って株を買う場合は、以下の4つのポイントを確認しましょう。
配当金狙いで株を選ぶときの4つのポイント
配当金を受け取るには、その会社が決めた期日までに、株を保有している必要があります。
「配当金を受け取れなかった…」ということにならないように、この記事では配当金の受け取り方や、いつまでに買えば配当金がもらえるかを詳しく解説します。
気になる内容をタップ
株の配当金って何?
株式投資における配当金は、「株」という資産を保有することで得られる利益です。
イメージとしては、不動産を保有している人が、それを貸し出すことで得られる家賃収入と似たようなものです。
会社の株主になったことで、会社がその利益の一部を分配するのが配当金です。
ただ保有しているだけで、何もしなくても利益を得ることができるため、不労所得と考えてもいいでしょう。
メリット
配当金のメリット
- 預金に比べて利回りが高い
- 配当だけでなく、株主優待も受け取れる銘柄がある
- 不労所得を得られる
- 株式比例方式で受け取れば、NISA口座で保有する配当が非課税になる
株を保有しているだけでもらえる配当金は、銀行にお金を預けるだけでもらえる「金利」と似ています。
利回りでいうと、配当金の方が預金金利に比べてかなり高いので、預金代わりに株を買って配当金を狙うという選択肢もあるでしょう。
また、魅力的な株主優待をもらえる銘柄もあるので、配当と株主優待の両方とも欲しいという場合、気になるものがあれば狙ってみてはいかがでしょうか。
また、NISA口座を利用すれば利益に対して税金がかかりません。
しかし、配当金に関しては非課税にするための条件があり、株式比例方式で受け取る必要があります。
デメリット
デメリット
- 元本が減る可能性がある
- 減配や無配となる可能性がある
- 購入のタイミングによっては配当がもらえない
銀行の預金とは違い、株の場合は株価が常に変動します。
そのため、株価が上がれば元本が増え、下がってしまうと元本が減る可能性もあります。
また、配当は確実に出るとは限りません。
会社の利益が減ったり、会社の方針によって、配当が減らされたりする可能性もあります。
もっと悪いケースでは、配当が全く出ないこともあり得ます。
さらに、株の配当をもらうには権利確定日に株を所有していなければいけません。
しかも、株は買ったその日に自分のものになるわけではなく、買った日(約定日)から起算して3営業日目に自分のものになります。
つまり、権利確定日の2営業日前には株を保有していなければ、配当をもらえません。
そのため、配当金を目的として株を買う際は必ず、権利確定日を確認してから買う必要があります。
配当金はいくらもらえる?
配当金の算出は簡単で、以下の計算式になります。
配当金=1株あたりの配当金額×保有株数
支払った配当金の金額は各企業によって異なりますが、2019年3月期については、日本の上場企業は総額9.8兆円もの配当金を支払っています。
(出典:東京証券取引所 2019年3月期決算短信集計【連結】《合計》(市場第一部・市場第二部・マザーズ・J))
なんと、配当金の金額は10年前の約2倍にも増えていて、企業側が株主還元に力を入れるようになったことが理由としてあげられます。
また、配当利回り(株の購入価格に対し、1年間でどれくらいの配当がもらえるのか、ということを表す数値)の平均は、2020年3月20日時点で、東証一部上場全銘柄が2.28%、東証2部全銘柄が2.42%、ジャスダックが2.09%となっています。
(出典:日本経済新聞社)
例として、日本道路(1884)が2019年3月期に出した配当を挙げて考えてみましょう。
例:日本道路(1884)の株を買った場合
- 条件
購入金額:1株6,000円
口数:1単元(100株)
2019年3月期の配当:1株当たり200円00銭
(内訳:普通配当が190円00銭、特別配当が10円00銭)
- 計算式
単元株の購入に必要な資金は、1株6,000円×100株=60万円
配当金は、1株当たり200円なので200円×100株=2万円を受け取ることができる
↓
20,000÷600,000≒0.33で、60万円の元手で「3.3%」の利益を得られたことになる
※この得られた3.3%の利益を「配当利回り」という
もしも100株ではなく1,000株保有する場合は、1株6,000円×1,000株で必要な資金は600万円、配当金は200円×1,000株で20万円になります。
このように、保有する株が多ければ多いほど、配当金は、比例して高くなるのです。
株の配当金をもらうには?
権利確定日と権利落ち日について
株の配当金がもらえるのは、「会社が決めた期日に株を保有している人」です。
この期日のことを「権利確定日」といい、基本的には月末に設定されています。
例
- 3月に配当が出る企業の場合、権利確定日は「3月31日」
- ただし、月末が土日祝日の場合は、その前営業日が期日になる
しかし、すでに書いたとおり、権利確定日に株を買っても、実は手遅れです。
権利確定日は、配当を受け取る株主の権利が確定する日なのですが、その判定は株主名簿で行われます。
そして、その株主名簿は、権利確定日の2営業日前の時点で作成されてしまうのです。
そのため、権利確定日の2営業日前のことを権利付最終日といい、その翌日のことを権利落ち日といいます。
配当金をもらうには、権利確定日ではなく権利付最終日、つまり2営業日前までに株を買う必要があるのです。
株の配当金はどこに入る?
株の配当金を受け取る方法は次の4つがあります。
- 株式数比例配分方式
保有しているすべての銘柄の配当金が、証券会社の口座に入金される方法。
同一の銘柄を複数の証券会社で保有している場合は、それぞれの保有株式数に応じた配当金が各証券会社の口座に入金される
※NISA口座で購入した株の配当金は、「株式数比例配分方式」で受け取らないと非課税にならないので注意 - 登録配当金受領口座方式
保有しているすべての銘柄の配当金を、銀行口座に振り込んでもらう方 - 配当金受領証方式
自宅に配当金領収書を郵送してもらい、郵便局などに持参して直接配当金を受け取る方 - 個別銘柄指定方式
保有する銘柄ごとに配当金振込指定書を提出して、銀行口座に振り込んでもらう方法
上記の4つの中で、一番手軽な方法は「登録配当金受領口座方式」です。
「配当金受領証方式」はオーソドックスな方法ですが、郵便局や銀行まで足を運ぶ必要があり、そういう意味では少々手間がかかります。
ただ、窓口で配当金を現金で受け取ることができるので、「配当をもらった」と実感することができるのは、配当金受領証方式ならではと言えるでしょう。
配当金狙いで株を選ぶ4つのポイント

配当金狙いで株を選ぶときのポイントは次の4つがあります。
これらのポイントを具体例をあげて説明するので、ぜひ参考にしてください。
配当利回りをチェックする
配当利回りとは、株価に対してどのくらいの配当金をもらうことができるかを示したものです。
配当金の金額が同じなら、株価が安い株の方が配当利回りは高い、ということになるので、銘柄選びの際はチェックしましょう。
配当利回りの計算式は以下のとおりです。
配当利回り(%)=1株あたりの配当金÷現在の株価
例:株の購入価格が1株1,000円、年間配当が1株20円の場合
配当金が1回当たり1株10円で年2回の場合、年間配当は1株当たり20円となる。
この株の配当利回りは、20円÷1,000円=0.02で「2%」ということになる。
ただし、配当金は企業の業績によって変化することがあるため、購入時の配当利回りがずっと続くとは限りません。
当初予定されていた金額から引き上げられたり、引き下げられたりすることもあります。
また、配当金の変動だけでなく、株価が変動した場合も配当利回りは変化します。
配当利回りは、株価が上がると低くなり、株価が下がると高くなるので、株価の動きにも注目しておく必要があります。
なぜ配当利回りをチェックすべきなのか?
配当利回りは、同じ投資金額でどれだけの配当金をもらうことができるか比較するのに役立ちます。
配当金を目的として投資するなら、同じ投資金額でもより多くの配当金をもらえる会社を選ぶべきでしょう。
例えば、株価も保有株数も全く同じで、配当利回りが異なるA社とB社があったケースを考えてみましょう。


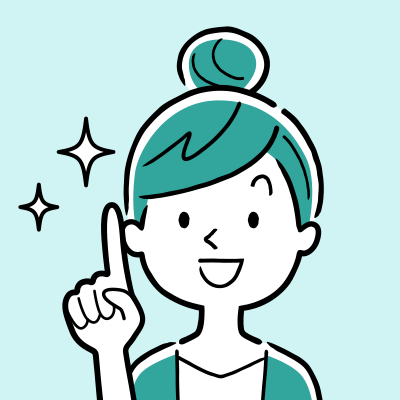
同じ資金100万円に対し、もらえる配当金はB社の方が75,000円も多くなるんですね。
このように、A社とB社の配当利回りを比較することで、どちらが好条件な銘柄かを判断することが可能になるのです。
連続増配株を選ぶ

配当が増えていくだけでなく、株価が底堅く推移する傾向があるため、配当狙いの場合は、連続増配株を選ぶと良いでしょう。
そもそも連続増配株とは、増配を続けている株のことです。
1度に増える配当は、それほど大きくなくても構いません。
毎年少しずつ配当を増やしている会社は、株主還元を重視している、ということになります。
株主還元を重視しているということは、株主を大切に考えているということでもあります。
その姿勢が投資家から評価され、株価の下落時にも売る人が極端に増えることは少ないのです。
また、連続して増配できるということはそれだけ経営が安定していて、成長しているということを意味します。
つまり、収益力が高く、経営上手である、ということになるのです。
このような理由から、連続増配株は不況時にも買う人が多く、また、手放す人も少ないという傾向があります。
どちらかというと、相場下落時には割安になることから買い増そうとする投資家が多いでしょう。
つまり、買い支えが入るということになります。
そのため、連続増配株はディフェンシブな株としてとらえられ、相場が下落している局面に株価が下がることはあっても、暴落することは少ないのです。
キャッシュリッチ企業かどうかチェックする

配当金を考える上で、キャッシュリッチ企業かどうかというのは重要です。
キャッシュリッチ企業というのは、資金が潤沢な企業のことです。
実質無借金経営をしていて、現金や預金などが豊富な企業のことをいいます。
なお、実質無借金とは、借金が全くない、あるいは有利子負債があっても、それ以上の資金を保有していることを意味します。
キャッシュリッチ企業は、企業として活用していない資金が豊富にあります。
そのため、配当が継続して行われる可能性が高く、増配にも期待できるのです。
そのため、配当金狙いの投資にはおすすめです。
配当性向をチェックする

会社が株主還元をどれくらい重視しているか分かるため、配当性向を必ずチェックしましょう。
配当性向とは、会社の利益のうちどのくらいの割合を配当として支払っているかを示したもので株主還元の割合を示しています。
配当性向の計算式は以下のとおりです。
配当性向=年間配当金÷1株当たりの当期純利益×100(%)
※1株あたり当期純損失となった場合(赤字となった場合)は、配当性向は算出されません
会社が配当性向をこれまでより上げる方針を掲げているのであれば、その会社は株主還元に力を入れている会社ということになり、今後の配当に期待ができます。
ただし、配当性向が高いと株主を大切にしていることになるのですが、高すぎるのは要注意です。
なぜなら、会社の貯えを減らして配当を出すなど、無理して配当を支払っている可能性が考えられるからです。
例:年間配当金が1株あたり30円のA社とB社の場合
- A社の1株あたりの純利益:20円
- B社の1株あたりの純利益:300円
↓
配当性向を計算すると…
- A社の配当性向:30円÷20円×100=150%
- B社の配当性向:30円÷300円×100=10%
↓
数字だけ見れば、A社の方がB社に比べて配当性向が高く、良い会社のように思うが、100%を超えているので注意が必要だと分かる!
配当性向の計算式にある1株あたり当期純利益とは、会社の売上から諸々のコストや税金などを差し引き、最後に残った金額になります。
1株あたり当期純利益から配当が出るのですが、その金額以上に配当を出すということは、その会社は事業拡大のためにお金を少しも貯めないどころか、これまでに蓄えたお金を削って投資家に配当を出すことになるからです。
先程書いたキャッシュリッチな会社であれば、そういうケースがあっても不思議ではないのですが(キャッシュが多すぎるとM&Aの対象として目をつけられることがあるため、積極的に配当を行うことがある)、そうでない会社の場合は、無理をして配当を出している可能性があります。
そのため、配当性向は高すぎず低すぎず、適正な範囲の会社を選びましょう。
POINT:これからの成長を期待するような会社には高配当を要求してはいけない?
アマゾン、アップル、マイクロソフトなどは、無配でありながらも株価の上昇が続いてきた企業であります。
これらは、会社の利益を配当金として還元するのではなく、事業に投資することで成長を続けてきました。
実は、配当金を十分に払うのは、「既存ビジネスが成熟していて成長余地は限られています」と言っているようなものとも考えられます。
これからの成長を期待するような会社には、得た利益を事業に投資することを期待し、高配当を要求するのはナンセンスかもしれません。
まとめ
株における配当金は、比較的安全で確実に得られる利益です。
とはいっても、株には価格変動による元本の下落リスクもあるため、配当金の高さだけで銘柄を選ぶことはおすすめしません。
さらに、配当金は受け取れるまでに時間がかかることも覚えておきましょう。
値上がり益と比較すれば、1回あたりの配当金はあまり高くはないため、軽視する人もいるかもしれません。
しかし、値上がり益を狙った投資と比べて、利益を得られる可能性がかなり高く、初心者にはおすすめです。
配当金狙いの投資は、値上がり益を狙った投資と銘柄の選び方が異なります。
この記事を参考にして、配当狙いに向いている銘柄を探してみてください。
























最後まで読めば、配当金の仕組みや特徴を理解した上で、配当金狙いの株取引を行えるでしょう。