
住宅ローンの火災保険とは?契約期間・保険料から選び方まで徹底解説
最終更新日:
このページにはPRリンクが含まれています
また当サイトで得た収益は、サイトを訪れる皆様により役立つコンテンツを提供するために、情報の品質向上・ランキング精度の向上等に還元しております。※提携機関一覧
火災保険は住宅ローンを契約する際に関わる保険の一つです。
火災保険とは名前の通り、火災によって建物や家財が被害にあった場合に、その損害が補償される保険のことです。
また、「火災」という名前がついているものの、商品によっては水災や盗難なども補償対象になる場合もあります。
火災保険の加入は必須ではなく任意ですが、住宅ローンを借りるときの条件として火災保険の加入を義務付けている銀行がほとんどのため、一般的には住宅ローンと同時、あるいは事前に火災保険の加入契約を結びます。
住宅ローンを借りる人の多くは、25年~35年もの長い年月をかけてローンを返済しますが、その間に住宅が火事や災害による損害を絶対に受けることはないとは言い切れません。
今回は、火災保険の契約期間から火災保険の保険料まで、詳しく説明します。
火災保険を選ぶポイントも解説しているため、住宅ローン借入時の火災保険について理解を深めたい人はぜひ参考にしてください。

株式会社エイチームライフデザイン
編集者イーデス編集部
「ユーザーが信頼して利用できるWEBメディア」を目指す編集部チーム。実際のユーザーの声や業界知識の豊富な専門家の協力を得ながら、コンテンツポリシーに沿ったコンテンツを制作しています。暮らしに関するトピックを中心に、読者の「まよい」を解消し、最適な選択を支援するためのコンテンツを制作中です。
■書籍
初心者でもわかる!お金に関するアレコレの選び方BOOK
■保有資格
KTAA団体シルバー認証マーク(2023.12.20~)
■許認可
有料職業紹介事業(厚生労働大臣許可・許可番号:23-ユ-302788)
気になる内容をタップ
住宅ローン契約の際に必要となる火災保険とは
火災保険とは、火災によって建物や家財が被害にあった場合に、その損害が補償される保険のことです。
冒頭で説明した通り、住宅ローンの契約の際にはほとんどの銀行が火災保険への加入を義務付けています。
火災保険という名前ですが、地震や水害にも対応している保険もあり、加入することで災害へのリスクに備えられます。
また、住宅購入時や住宅ローン借入時に、銀行や不動産会社から特定の火災保険を勧められる事がありますが、銀行や不動産会社から提案された火災保険に必ず加入する必要はありません。
加入する火災保険は自身で選ぶことができるので、内容と保険料を比較し検討しましょう。
火災保険の補償対象は基本的に「建物」のみ
火災保険の補償対象は基本的に「建物」のみとなっており、家具や車といった「家財」は補償対象外です。
これらも補償対象にしたい場合は、保険料を上乗せする必要があります。
火災で自宅に被害を受けた場合、室内に置いている家具や電化製品なども失ってしまうため、買い戻すには多くの費用が必要です。
家財保険にも加入しているとそれらの費用も保険料で賄うことができます。
万が一の場合に備えるためには、家財も補償対象に含めるようにした方が良いでしょう。
地震や津波被害への補償は地震保険の加入が必要
火災保険は火災や水害、風災といった自然災害への補償を受けることができますが、地震や噴火、津波による被害は補償外となっています。
以下は火災保険と地震保険の補償範囲をまとめた表です。火災保険は災害全てに対応できる訳ではないので注意しましょう。
| 火災保険の補償内容 | 地震保険の補償内容 |
|---|---|
| ●火災 ●落雷 ●風災・ひょう災・雪災 ●破裂・爆発 ●建物外部からの物体の衝突・落下・飛来 ●水濡れ ●騒じょう・集団行動などに伴う暴力行為 ●盗難 ●不測かつ突発的な事故 | ●地震や噴火、 津波による火災 ●地震や噴火、 津波による破損 ●地震や噴火、 津波による埋没 |
※火災保険の補償内容は契約する保険によって異なる。
近年多発している台風については風災に含まれるため、火災保険でカバーすることが可能です。
台風によって屋根の被害を受けた場合は火災保険を利用することで、実質無料で修理を受けることができます。
詳しくはファインドプロの「屋根の修理には火災保険が適用できる!適用条件と注意点について解説」で紹介しているので、参考にしてくださいね。
最近は火災保険の質権設定を行わない場合が多い

質権設定とは、火災保険金の受け取り先を契約者以外に設定することです。
質権設定をしていると火災が起こり、住宅ローンを支払えない状況になっても火災保険の保険金から住宅ローンの残債が返済されます。
今まで火災保険に加入する際には、銀行を質権設定の対象にすることを求められる場合もありました。
しかし、最近では銀行側での質権の管理コスト削減、予定していた利息を受けられないという理由から、質権設定を行わない場合も増えています。
その場合、火災保険金を契約者が受け取り、住宅ローンの返済に充てる必要があります。
火災保険の契約期間は最長10年間
火災保険の契約期間は、1年から最長10年まで選ぶことが可能です。
火災保険に1年契約で加入する場合と、10年などの長期契約で加入する場合においては、それぞれ下記のようなメリット・デメリットがあります。
| 契約期間 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 1年契約 | ・保険料の一括払いによる金銭的な負担が軽い ・更新時に補償内容を見直せる | ・保険料の総支払額が割高になる ・毎年更新する手間がかかる |
| 長期契約 | ・保険料の総支払額を抑えられる ・更新する手間がかからない | ・保険料の一括払いによる金銭的な負担が重い ・補償内容を見直す機会が少ない |
住宅ローンを借りる際に加入する火災保険は、基本的に保険料は一括払いとなることがほとんどです。
そのため、火災保険の契約期間が長くなるほど、一括で支払う保険料は高額になります。
1年契約であれば、一年ごとに保険料を支払うため保険料の負担感を抑えられる上に、更新手続きのたびに補償内容を見直せるので、そのときのライフスタイルに合わせた保険の内容に変えることができます。
その一方で長期契約は一括支払い時に、まとまった出費が必要となりますが、火災保険の契約期間が長期になるほど火災保険料の割引率は大きくなりますよ。
詳しくは後述の「保険期間は長期がお得」で解説しているのでチェックしてください。
自動継続の特約を付帯できる
契約期間についても、多くの銀行では借入条件で、住宅ローンの返済期間と同じ期間で火災保険に加入するように定めています。
火災保険の契約期間は最長でも10年のため、住宅ローンの返済期間が10年を超える場合は「火災保険の自動継続の特約」を付けましょう。
- 火災保険の契約期間満了後、自動的に契約が更新される特約のこと
- 契約内容はそのまま引き継がれるため、補償の切れ目が生じない
火災保険の自動継続の特約を付帯しておけば、

火災保険の契約手続きをうっかり忘れていて補償を受けることができなかった
という事態を避けることが可能です。
しかし、自動継続にしている火災保険に新しい補償を追加したい場合は一度解約し、火災保険の契約期間を変更して再度加入手続きをしなければいけない場合もあります。
途中解約すると未経過分は返金される
火災保険は契約期間にかかわらず、いつでも解約することができます。
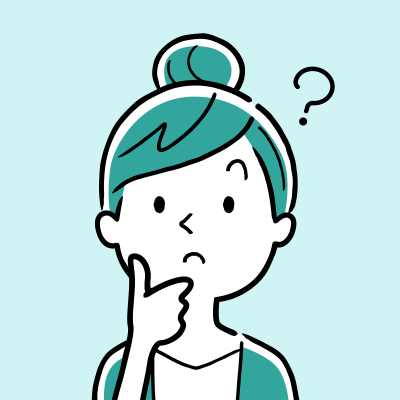
契約期間が満期を迎えていないのに解約すると、すでに火災保険の保険料を一括で支払っているので損をするのでは?
と思うかもしれませんが、契約期間が満了するまでに残った期間(未経過期間)があれば保険料は返金されます。
保険の契約に伴い戻ってくる保険料のことを「解約返戻金」と言います。
火災保険の解約時にどれくらいの解約返戻金があるのかを知りたいときは、下記の計算式で解約返戻金の金額を算出することが可能です。
解約返戻金の計算式
解約返戻金 =
一括払保険料 × 返戻率(未経過料率)
以下に、10年契約で一時払保険料が30万円(1年あたり3万円)の火災保険を解約した場合の解約返戻金を示します。
| 解約時期 | 返戻率 | 解約返戻金 | 1年あたりの保険料 |
|---|---|---|---|
| 10年契約で 1年経過後に解約 | 約88% | 約264,000円 | 約36,000円 |
| 10年契約で 5年経過後に解約 | 約49% | 約147,000円 | 約30,600円 |
| 10年契約で 8年経過後に解約 | 約19% | 約57,000円 | 約30,370円 |
※上記の表における返戻率・保険料はあくまでも目安であり概算です。
返戻率(未経過料率)は保険会社により異なりますが、加入後の経過期間とともに返戻率(未経過料率)は下がっていくため、当然のことながら経過期間に応じて解約返戻金は減っていきます
ただし、1年あたりの保険料は契約後の期間が経過するほど割安になってくることがわかります。
解約返戻金を計算する際の未経過料率については、契約した火災保険の契約約款などで確認して計算することができます。
- 保険会社のホームページなどに返戻率が載っていない
- 実際の解約返戻金を明確に把握したい
という場合は、加入している保険会社や代理店に直接問い合わせてください。
火災保険の保険料をシミュレーション
火災保険の加入時に最も気になるのが「保険料」ではないでしょうか。
先述の「火災保険の契約期間は最長10年間」でも触れたとおり、基本的に火災保険の保険料は一括で支払う必要があるため、住宅購入に伴い資金計画を立てる際は物件の代金だけでなく、火災保険料も考慮しなければなりません。
しかし、建物の所在地・建物の構造・補償内容などのさまざまな要素によって火災保険料は異なるため、前提条件が異なる中で一律に保険料を比較することは困難です。
火災保険料を比較する際には、保険料算出の前提条件をある程度揃えておく必要があります。
それらを踏まえた上でここからは、シミュレーションツールで計算した戸建てとマンションの火災保険料を紹介します。
戸建てとマンションの火災保険の保険料を比較
今回は、下記を共通の条件として火災保険料のシミュレーションを行いました。
| 物件の所在地 | 東京都 |
|---|---|
| 保険会社 | 楽天損保 |
| プラン名 | オールリスクプラン |
| 物件の築年数 | 新築 |
| 保険金額 | 1,500万円 |
| 保険期間 | 10年間 |
上記で示した共通の条件のもと、戸建てとマンションにおける火災保険料のシミュレーション結果は以下のとおりです。
| 建物の タイプ | 建物の構造 | 保険料 |
|---|---|---|
| 戸建て | H構造 (木造などの非耐火構造) | 136,800円 |
| T構造 (コンクリート・ 鉄骨造などの耐火構造) | 66,150円 | |
| マン ション | M構造 (コンクリート造の 共同住宅) | 39,900円 |
※2019年11月時点の情報を基にシミュレーション
シミュレーション結果を見ると、コンクリートなどの耐火性能の高い建物は火災保険料が安く、それらに比べて耐火性能が劣る木造の場合は火災保険料が高くなることがわかります。
基本的に「M構造→T構造→H構造」の順番に火災保険料は上がるため、住宅購入の資金計画を立てるときは建物の構造によっても火災保険料が大きく異なるということも知っておきましょう。
なお、今回のシミュレーションにて試算した楽天損保のオールリスクプランには下記の補償がすべて含まれています。
補償内容については、一般的にどの保険会社でもこれと同等の補償内容を設定することが可能です。
| 補償 | 内容 |
|---|---|
| 火災 | 失火やもらい火による火災の損害を補償 |
| 落雷 | 落雷による損害を補償 |
| 風災・ひょう災・雪災 | 台風による強風や豪雪による雪災などの損害を補償 |
| 破裂・爆発 | ガス漏れによる破裂・爆発などの損害を補償 |
| 水災 | 台風や豪雨による洪水被害などを補償 |
| 建物外部からの物体の衝突・落下・飛来 | 自動車が住宅に衝突することによる損害などを補償 |
| 水濡れ | 給排水設備の故障などの水濡れによる損害を補償 |
| 騒じょう・集団行動などに伴う暴力行為 | 暴動などに伴う暴力・破壊行為による損害を補償 |
| 盗難 | 盗難による損傷・汚損といった損害を補償 |
| 不測かつ突発的な事故 | 日々の暮らしの中で生じた破損・汚損による損害を補償 |
基本補償となる火災や落雷などの補償は外せない場合もありますが、火災保険の商品によっては不要な補償を外すことが可能です。
火災保険の保険料は補償内容によって変動します。補償範囲を拡大すれば、当然保険料は高くなります。
そのため、保険の対象となる建物の構造や所在地、補償範囲などに応じて、火災保険の保険料は異なることを理解しておきましょう。
火災保険を選ぶにあたっての3つのポイント
火災保険の補償内容は手厚くした分、保険料も高くなるため大きな負担を感じることもあるでしょう。
ただし、補償内容が十分でなければ、大きな災害などで建物に大きな損害が出てしまった場合には、自費で修理しなければいけなくなるケースもあります。
その場合、住宅ローンの返済と併せると家計に大きな負担がかかってしまいます。
そのため、自身のニーズに合う保険料・補償内容の火災保険をよく吟味しましょう。
最後に、火災保険を選ぶにあたっての3つのポイントを紹介します。
火災保険を選ぶにあたっての3つのポイント
選ぶポイント①住宅環境に合わせて必要な補償だけを選択する
火災保険の保険料を抑えたい人は、住宅環境を踏まえてあまり必要のない補償は外すことをおすすめします。
たとえば、マンションの高層階や高台にある戸建てに住む場合で、洪水・豪雨・高潮による床上浸水の被害に遭う可能性が極めて低い場合には、水災の補償を外してもよいかもしれません。
このように、住宅を取り巻く環境によって必要になる補償は異なってきます。
何度も言うように補償範囲を広げれば幅広いリスクに備えられますが、その分火災保険料も高くなります。
なるべく保険料の負担を抑えるためにも、火災保険に加入する際には、ハザードマップなども確認して、住宅の立地や周辺環境から起こりうるリスクを考慮し、必要な補償をしっかりと判断してニーズに合った補償プランで火災保険に加入するようにしましょう。
選ぶポイント②保険期間は長期がお得
先述の「火災保険の契約期間は最長10年間」で紹介したとおり、火災保険の保険料は長期契約にすると割安となります。
| 火災保険の契約年数 | 割引率 |
|---|---|
| 2年 | 約7.5% |
| 3年 | 約10.0% |
| 4年 | 約12.5% |
| 5年 | 約14.0% |
| 6年 | 約15.0% |
| 7年 | 約15.5% |
| 8年 | 約16.0% |
| 9年 | 約17.0% |
| 10年 | 約18.0% |
※上記の割引率はあくまでも一例であり、すべての保険会社で同一ではありません。
※2019年11月現在における1年契約と比べた場合の割引率です。
保険会社により上記の割引率は異なりますが、いずれにしても1年契約と比べると、10年契約の場合は火災保険料の大幅な割引を受けることができます。
では、「1年契約」「5年契約」「10年契約」において、実際に火災保険料はどれくらい変わるのでしょうか。
下記は、年間の火災保険料が3万円の場合における保険料の違いを示した表です。
| 契約年数 | 10年分の 保険料 | 1年あたりの 保険料 |
|---|---|---|
| 1年契約 | 約30万円 | 約3万円 |
| 5年契約 | 約26万円 | 約2万6,000円 |
| 10年契約 | 約25万円 | 約2万4,000円 |
※保険料はあくまでも概算です。
※長期契約の保険料は2019年11月現在の割引率で算出しています。
一方で、火災保険の保険料は一括で支払う必要があるため、保険料の支払い負担は大きくなることに注意が必要です。
これらのことを考慮した上で保険料の支払総額を抑えたいという人は10年契約で加入するとよいでしょう。
選ぶポイント③契約にあたっては複数の見積もりをもらう
保険料や補償内容をよく把握していないまま、銀行や不動産会社からすすめられた火災保険に加入することはおすすめできません。
その理由は、銀行や不動産会社が提携している保険会社が自身のニーズに必ず合致するとは限らないからです。
- 銀行や不動産会社がすすめる火災保険の保険料が他社よりも割高だった
- 火災が起こったときに補償対象となるのは建物のみで、家財は含まれていなかった
- 台風の被害に遭って保険金請求したら免責の設定があり保険金が出なかった
- 火災保険の補償内容が他の保険と重複しており、保険料が無駄になっていた
など、加入する火災保険を銀行や不動産会社の「お任せ」にしてしまうと、無意味に保険料が高くなったり補償内容が不足したりする場合があります。
最近では各保険会社が取り扱っている火災保険の保険料や補償内容を、ネット上で簡単に比較することができます。
災害に遭ってから後悔しないために、火災保険に加入する際には複数の保険会社に火災保険の見積もりを依頼して、保険料や補償内容をしっかりと比較検討しましょう。
火災保険についてはイーデス保険の「火災保険とは? 補償内容や選び方、タイプ別(戸建て・マンション・賃貸物件)の必要性を分かりやすく解説」でも紹介しています。ぜひ参考にしてくださいね。
まとめ
火災保険は、ほとんどの銀行で住宅ローンの借入条件として加入が求められる保険です。
火災保険の契約期間は最長10年となっていますが、住宅ローンの返済期間中は火災保険の加入も義務付けられているため、多くの人は20年や30年といった長期にわたり火災保険に加入することとなります。
だからこそ、火災保険に加入する際は保険料や補償内容をきちんと把握しなければなりません。
火災保険の補償内容は、各保険会社から販売されている保険商品によっても若干異なります。
また、火災保険の保険料は建物の所在地・構造や補償範囲によっても変わります。
火災保険を選ぶ際は、まず複数の保険会社から見積もりを出してもらいましょう。

住宅環境に合わせて不要な補償は外し、自身の資金計画を踏まえて適切な火災保険の契約期間を決めることが、納得のいく火災保険選びにつながるはずです。

















そのため、火災保険に加入して火事や災害のリスクに備えることは非常に大切です。