
仮想通貨の積立投資は意味ない?メリット・デメリットやおすすめ取引所を紹介
最終更新日:
このページにはPRリンクが含まれています
また当サイトで得た収益は、サイトを訪れる皆様により役立つコンテンツを提供するために、情報の品質向上・ランキング精度の向上等に還元しております。※提携機関一覧
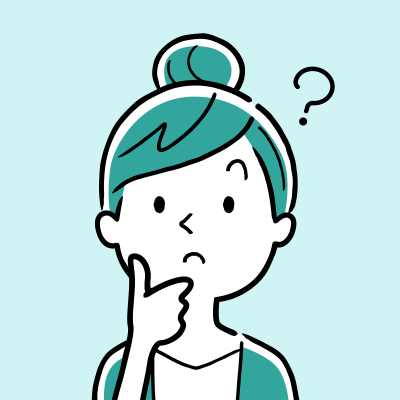
- 仮想通貨の積立投資ってアリなの?意味ないって本当?
- ビットコインを積み立てるメリットやデメリットを知りたい!
暗号資産の積立投資は、複数の仮想通貨取引所で用意されているサービスで、「リスクを低減したい人」や「少額投資から始めたい人」に向いている投資方法です。
仮想通貨の積立投資を行う際の主なメリット・デメリットは以下の通りです。
仮想通貨の積立投資を始めるなら、以下の仮想通貨取引所がおすすめです。
仮想通貨の積立投資におすすめの仮想通貨取引所(サービス)
仮想通貨の積立投資のメリットやデメリットを詳しく知ったうえで、あなたに合った積立サービス・取引所を選びましょう。
2023年10月12日時点の情報を掲載しています。
サービスの都合上「仮想通貨」「暗号資産」という言葉を併用する場合がありますが、どちらも同じ意味です。
本記事では、以下の一覧に記載されている、金融庁・財務局から暗号資産交換業者として登録を受けている業者のみ紹介します。
暗号資産交換業者一覧

スキラージャパン株式会社 代表取締役 / スキラージャパン株式会社
監修者伊藤亮太
伊藤亮太は「スキラージャパン株式会社」の取締役を務めるFP(ファイナンシャル・プランナー)。
慶應義塾大学大学院商学研究科経営学・会計学専攻を修了しており、在学中にCFP®を取得。
その後、証券会社にて営業・経営企画・社長秘書・投資銀行業務に携わる。
現在は富裕層個人の資産設計を中心としたマネー・ライフプランの提案・策定・サポート等を行う傍ら、資産運用に関連するセミナー講師や講演を多数行う。
▼書籍
7日でマスターNISA&iDeCoがおもしろいくらいわかる本
図解即戦力 金融のしくみがこれ1冊でしっかりわかる教科書
ゼロからはじめる! お金のしくみ見るだけノート
株で勝ち続けるための 上がる銘柄選び黄金ルール87
など
株式会社エイチームライフデザイン
編集者イーデス編集部
「ユーザーが信頼して利用できるWEBメディア」を目指す編集部チーム。実際のユーザーの声や業界知識の豊富な専門家の協力を得ながら、コンテンツポリシーに沿ったコンテンツを制作しています。暮らしに関するトピックを中心に、読者の「まよい」を解消し、最適な選択を支援するためのコンテンツを制作中です。
■書籍
初心者でもわかる!お金に関するアレコレの選び方BOOK
■保有資格
KTAA団体シルバー認証マーク(2023.12.20~)
■許認可
有料職業紹介事業(厚生労働大臣許可・許可番号:23-ユ-302788)
気になる内容をタップ
仮想通貨の積立投資とは?こんな人におすすめ!
仮想通貨の積立投資とは、毎日や毎月など決まったタイミングで仮想通貨を自動で買い付けていくサービスです。
仮想通貨取引所では積立投資のサービスを取り扱っているところも多く、あらかじめ積み立てる銘柄や金額を指定しておけば、あとは自動で買い付けを行ってくれます。
仮想通貨の積立投資には、「少額で始められる」「投資のタイミングを分散できる」といった特徴があるため、下記のような人におすすめです。
仮想通貨の積立投資はこんな人におすすめ!
- 少額投資から始めたい人
- リスクを低減したい人
- 初めて仮想通貨に投資する人
- 購入のタイミングに悩んでいる人
仮想通貨と聞くと「まとまった資金を投資する」というイメージがあるかもしれませんが、少額をコツコツと積み立てていく積立投資も立派な投資手法のひとつです。
仮想通貨の積立投資の主なメリット3つ
仮想通貨の積立投資には、主に次のようなメリットがあります。
仮想通貨の積立投資の主なメリット
それぞれ詳しく解説していきましょう。
投資のタイミングを分散できる
仮想通貨に一括投資する場合、「価格が高いところで購入してしまった」という高値掴みをしてしまうケースも少なくありません。
特に、仮想通貨は値動きが大きいうえに市場の流れを読みにくいことから、「購入直後に一気に価格が下落してしまった」という例も多く見られます。
積立投資では毎日や毎月など一定のタイミングで購入を行うため、価格が高いときは少なく、価格が低いときは多くの仮想通貨を購入できる仕組みとなっています。
結果的に購入価格が平準されるメリットがあり、損失を被るリスクを低減しやすくなります。
少額投資から始められる
少額投資から始められることも、仮想通貨の積立投資の特徴です。
最低積立金額は取引所によって異なりますが、中には1円から申し込める取引所もあります。
仮想通貨はまだ「新しい金融商品」というイメージも強く、いきなり大きな金額を投資することに抵抗がある人も多いかもしれません。
値動きが大きな金融商品にまとまった資金を投資するのは勇気がいるものですが、少額での投資ならチャレンジしやすいのではないでしょうか。
「なかなか一歩が踏み出せない」という人は、まずは積立投資で少額ずつ購入してみて、慣れてきたら取引金額を大きくしていくのもひとつの方法です。
購入のタイミングを悩む必要がない
仮想通貨の取引で難しいことのひとつが「購入のタイミングを決断すること」です。
値動きを予測しにくい仮想通貨では、「高値掴みになってしまうのでは」「これからもっと下落するかも」という不安から、なかなか投資を決断できないことも多くあります。
悩むあまりに「投資のタイミングを逃してしまった」という機会損失につながる可能性もあるでしょう。
その点、積立投資ではあらかじめ決まったタイミングで投資を続けていくことから、自ら投資のタイミングを計る必要がありません。
感情に振り回されずにコツコツと積立を続けていけるので、「購入するタイミングが分からない」という人は積立投資から始めてみるとよいでしょう。
仮想通貨の積立投資の主なデメリット3つ
さまざまなメリットがある仮想通貨の積立投資ですが、一方で次のようなデメリットもあります。
仮想通貨の積立投資の主なデメリット
それぞれ詳しく確認していきましょう。
短期間でまとまった利益を得にくい
積立投資は少額での投資となるため、短期間でまとまった利益を得にくいのは事実です。
しかし、積立投資の目的は「短期でまとまった利益を得ること」ではなく、「長期投資でリスクを分散すること」です。
いきなり大きな利益を得ることは困難ですが、長期的に投資を続ける目的として取り組むとよいでしょう。
取引コストがかさみやすい
仮想通貨の取引には「取引所形式」と「販売所形式」の2種類がありますが、積立投資では販売所形式が適用されることが一般的です。
販売所形式とは、運営事業者を相手に売買する仕組みのことで、ユーザー同士で売買を行う取引所形式に比べてコストが高くなる傾向にあります。
そのため、積立投資は取引所形式で都度購入する場合に比べて、コストがかさみやすいデメリットがあります。
「よりコストをおさえて投資したい」という人は、不便を感じる面もあるかもしれません。
元本割れのリスクは避けられない
積立投資は購入のタイミングを分散してリスクを低減する効果がありますが、「元本割れのリスクがゼロになる」というわけではありません。
当然、価格が下落すれば積み立てた元本が割れることも想定されるため、あらかじめリスクをきちんと理解しておくことが大切です。
積立投資を始める際は、損失を負っても日常生活に支障がない金額の範囲内で取り組むようにしましょう。
仮想通貨の積立投資を始める方法
仮想通貨の積立投資を始める際の流れ
- 仮想通貨取引所で口座開設を行う
- 積立投資の申し込みを行う
- 積み立てたい銘柄や金額を入力する
- 積立投資がスタート
仮想通貨の積立投資を始める際は、まず積立投資のサービスを取り扱う取引所で口座開設を行います。即日〜数日など比較的早く口座開設できるのが一般的です。
取引所によって最低積立金額や積立投資の対象となる銘柄、取引コストなどが異なるため、複数の取引所を比較して利用先を選定するのがおすすめです。
口座開設時には本人確認が必要になるため、マイナンバーカードや運転免許証などを手元に用意しましょう。
口座開設が完了したら、マイページにログインして積立投資の申し込みを行います。積み立てたい銘柄や金額を入力すれば、後は自動で積立投資がスタートします。
仮想通貨の積立投資サービスを選ぶときのポイント
積立投資サービスは多くの仮想通貨取引所が取り扱っています。利用先を選定する際は、次の4つのポイントを比較してみましょう。
仮想通貨の積立投資サービス選びのポイント
少額から積立できるか
積立投資サービスは、取引所によって最低積立金額が異なります。
「まずは少額投資から始めたい」という場合は、最低積立金額がより低く設定されている取引所がおすすめです。
積立金額は後から変更ができるので、仮想通貨の投資に慣れてきたら徐々に金額を大きくしていくのもよいでしょう。
取引コストが抑えられるか
仮想通貨の積立投資は「取引手数料無料」としている取引所が多いものの、実際は「スプレッド」と呼ばれるコストがかかります。
スプレッドとは「売値と買値の差額」のことで、投資家が実質的に負担している手数料のようなものです。
スプレッドの幅は取引所によって異なるため、取引コストを抑えるためには、複数の取引所を比較してよりスプレッドが狭い取引所を選定するようにしましょう。
積立対象の仮想通貨が豊富か
積立投資を始める際は、取引所の取扱銘柄も比較したいポイントです。
特に気をつけたいのが「通常の取扱銘柄」と「積立投資の対象銘柄」の違いについてです。
通常の売買では30種類の銘柄を取り扱っている取引所でも、「積立投資で対象となるのはそのうち10種類のみ」ということも珍しくありません。
ビットコインなどのメジャーコインは多くの取引所が取り扱っていますが、マイナーコインでの積立を検討している場合は、積立投資の対象銘柄を事前に確認しておきましょう。
通常取引のコストが低いか
取引所を選定するときは、スプレッドによるコストだけでなく、取引所形式での取引手数料もチェックすることが大切です。
積立投資で仮想通貨の取引に慣れてきたら、いずれ取引所形式での売買にチャレンジすることもあるかもしれません。
積立投資で積み立てた保有分を取引所形式で売却することもあるでしょう。
その際に取引コストが高ければ、せっかく積み上げてきた利益が削られてしまいます。
積立投資を始める際は、積立投資にかかるコストだけでなく、取引所形式の手数料や入出金手数料など通常の取引にかかるコストも確認しておくと安心です。
積立投資サービスがあるおすすめの仮想通貨取引所3選
仮想通貨の積立投資サービスを取り扱っている、おすすめの取引所は次の3つです。
積立投資サービスがあるおすすめの仮想通貨取引所
※最低積立金額の低さ、手数料無料など、積立投資サービスを選ぶ観点から選定
GMOコイン(つみたて暗号資産)
GMOコインの「つみたて暗号資産」には「毎日プラン」と「毎月プラン」の2種類があり、積立頻度を選択できます。
「毎日コツコツ積み立てたい」という人は毎日プラン、「毎月決まった日に積み立てたい」という人は毎月プランを選びましょう。
また、GMOコインでは積立投資の対象銘柄が21種類と多いことも特徴です。
ビットコインやイーサリアムなどのメジャーコインだけでなくマイナーコインも多く取り扱っているため、「アルトコインをメインに投資したい」という人にも便利でしょう。
GMOコインの公式サイトはこちら
SBI VCトレード(積立暗号資産)
SBI VCトレードの「積立暗号資産」では、積立頻度を「毎日」「毎週」「毎月」の中から選択でき、銘柄ごとに積立頻度を変えることも可能です。
たとえば、「ライトコインは毎日、ビットコインは毎月投資する」というように銘柄別に設定できるため、市況に合わせて積立頻度を変更するのもよいでしょう。
また、入出金手数料が無料である点も大きなメリットです。
積立投資では、引き落とし日までに口座に入金しておく必要があります。その際も入金手数料がかからないので、全体の取引コストをおさえて投資が可能です。
SBI VCトレードの公式サイトはこちら
bitFlyer(かんたん積立)
bitFlyerの「かんたん積立」では、1円から積立投資を始められます。
仮想通貨の取引では、まだ認知度が低いマイナーコインには「まとまった金額を投資しにくい」と感じるかもしれませんが、1円からの積立であれば購入しやすいのではないでしょうか。
「500円ずつ複数の銘柄に投資する」といった使い方をするのもよいでしょう。
また、bitFlyerでは積立頻度を「毎日」「毎週」「毎月1回」「毎月2回」の4種類の中から選べます。
豊富なバリエーションがあるため、ぜひ自分の投資意向に合った積立頻度を見つけてみましょう。
bitFlyerの公式サイトはこちら
よくある質問
仮想通貨の積立は毎日と毎月どっちがいい?
積立頻度による運用成果にはあまり大きな違いがありません。
長期投資では、毎日積立と毎月積立による運用成果はそれほど大きな差がないでしょう。
ただし、毎日積立の方がより分散投資されるため、購入単価を平準化しやすいといえます。
仮想通貨の積立投資の利益に税金はかかりますか?
仮想通貨で得た利益は「雑所得」となり、総合課税の対象です。
確定申告が必要となる水準は人によって異なりますが、年末調整をしている会社員の場合は給与以外の収入が年間20万円を超えると確定申告をしなければなりません。
積立投資をやめたくなったらどうすればいいですか?
積立投資はいつでも中止の申し込みが可能です。
積立投資をやめたくなった際は、利用している取引所のホームページから中止申し込みを行ってください。
あわせて保有資産を売却したい際は、別途売却手続きが必要となります。
まとめ
仮想通貨の積立投資は、少額から申し込める点や投資のタイミングを悩まなくてよい点から、初心者でもチャレンジしやすい投資方法です。
仮想通貨の積立投資はこんな人におすすめ!
- 少額投資から始めたい人
- リスクを低減したい人
- 初めて仮想通貨に投資する人
- 購入のタイミングに悩んでいる人
投資のタイミングを分散することで、元本割れのリスクが低減できる点も嬉しいポイントでしょう。
積立投資のサービスは取引所によって対象銘柄や手数料が異なるため、ぜひこの記事で紹介した取引所を参考に利用先を選定してみてください。










