
豪ドルはやばい?今後の見通しや豪ドル/円取引のポイントを解説
最終更新日:
このページにはPRリンクが含まれています
また当サイトで得た収益は、サイトを訪れる皆様により役立つコンテンツを提供するために、情報の品質向上・ランキング精度の向上等に還元しております。※提携機関一覧
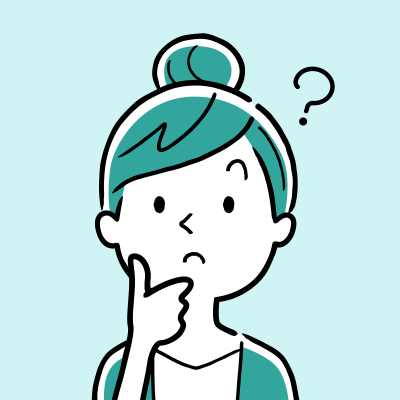
- 豪ドルはやばいって聞いたけど、実際はどうなの?
- 豪ドル/円の今後の見通しは?5年後や10年後はどうなる?
豪ドル/円は人気通貨ペアとして知られており、金融先物取引業協会が発表する店頭FX取引金額で毎月上位に位置しています。
豪ドル/円の5年後・10年後の見通し
どちらに転ぶ可能性もあるため、値動きのパターンを知らずに取引すると損してしまうかもしれません。
豪ドル/円の買い時は世界的な危機等が発生する場面に多く、比較的判断がしやすいと言えます。
当記事で豪ドル/円の特徴や買い時を知って、より良いトレードをしましょう。
筆者が損したことのないトレード手法を紹介しますので、ぜひ参考にしてください!
ゆったり為替
豪ドル/円取引におすすめのFX会社
2024年4月7日時点の情報を掲載しています。
本記事では、以下の一覧に記載されている、金融庁・財務局から金融商品取引業者として登録を受けている業者のみ紹介します。
金融商品取引業者一覧
執筆者のプロフィール
ゆったり為替/FX・仮想通貨トレーダー
早稲田大学政治経済学部政治学科卒。独立行政法人職員を経て独立。中長期トレードを主戦場とし、仮想通貨・アンティークコインにも投資を行う。執筆業では正直かつ正確な情報提供に努めて執筆することを心がけている。

株式会社エイチームライフデザイン
編集者イーデス編集部
「ユーザーが信頼して利用できるWEBメディア」を目指す編集部チーム。実際のユーザーの声や業界知識の豊富な専門家の協力を得ながら、コンテンツポリシーに沿ったコンテンツを制作しています。暮らしに関するトピックを中心に、読者の「まよい」を解消し、最適な選択を支援するためのコンテンツを制作中です。
■書籍
初心者でもわかる!お金に関するアレコレの選び方BOOK
■保有資格
KTAA団体シルバー認証マーク(2023.12.20~)
■許認可
有料職業紹介事業(厚生労働大臣許可・許可番号:23-ユ-302788)
気になる内容をタップ
豪ドルはやばいって本当?特徴を解説
豪ドル/円や豪州(オーストラリア)には、以下の特徴があります。
豪ドルや豪州の特徴
30年以上もレンジ相場で推移
豪ドル/円は長期的にレンジ相場(値動きが特定の範囲で推移すること)を形成しており、30年以上も継続しています。
1990年代始めから継続的に同じ範囲を行ったり来たりしており、チャートを見ると独特な値動きがよくわかります。

OANDA証券のMT5から筆者引用
比較として同じ期間の米ドル/円チャートを確認すると、値動きの規則性はないように見えます。
大きく円安になったと思えば70円台まで円高になった時期もあり、当記事執筆時点では直近30年間の円安記録を更新し続ける勢いです。

OANDA証券のMT5から筆者引用
30年以上も同じ範囲で動き続けており、特徴的だという意味でも豪ドル/円は「やばい」通貨ペアだといえるでしょう。
ゆったり為替
豪州は政策金利が高い
豪州は政策金利が高いことでも有名です。豪ドル/円を買い持ちするとスワップポイントが大きくなります。
1995年以降について、政策金利の推移を確認しましょう。

各国中央銀行の公開データなどをもとに作成〈FRB(米国) /ヒストリカルデータ /RBA(豪州) /日銀(資料1)(資料2) /全国銀行協会 /外為どっとコム 〉
日本の政策金利はゼロ付近に張り付いている一方、豪州は高い水準を維持してきました。
参考までに米国の政策金利も掲載すると、米国と比べても豪州の高さが際立っています。
直近の政策金利は豪州よりも米国のほうが高いものの、過去と同じ推移になるなら、豪州が米国よりも再び高くなると想定できるでしょう。
長期間にわたってレンジ相場で推移し、スワップポイントはプラスでしたので、豪ドル/円を買って持ち続けるだけで財産を築けた可能性があります。
ポジションを持って放置するだけで稼げたのですから、豪ドルはある意味「やばい」かもしれません。
ゆったり為替
経済面で中国との結びつきが強い
豪州は中国と経済的な結びつきが強いといわれており、中国の経済指標発表などを受けて豪ドル/円が動くこともあります。
豪州と中国の結びつきを知る方法として、TWIという指標があるので、推移を確認しましょう。
TWI(Trade Weighted Index)
TWIは豪ドルの強さを測るための指標で、豪州準備銀行(中央銀行)が公開しています。
豪州と各国の貿易シェアを使って各国通貨の重要度(ウェイト)を決定しており、各国通貨のウェイトを見れば、豪州と各国の経済的な結びつきの強さがわかります。

豪州準備銀行の公開データをもとに作成
2001年以降の推移を見ると、中国人民元だけが右肩上がりで推移し、米ドルなどは重要度を落としていることがわかります。
豪州と中国の経済的な緊密化を示しており、中国人民元のシェアは最大で36%台後半にまで上昇しました。
中国の経済活動が豪州の景気にも影響するので、豪ドル/円でトレードする際は中国の経済指標や要人発言等にも注意を払う必要があります。
2021年を頂点にして中国人民元の割合が減少しており、今後の推移に注目です。
ゆったり為替
なお、豪州は安全保障の枠組み「AUKUS(オーカス)」に参加しています。AUKUSは米英豪の3か国で作られ、対中国を念頭に行動しています。
一方では中国との経済関係が緊密化し、他方では対中国を念頭に安全保障協力の枠組みを強化しており、豪州と中国の関係は「やばい」といえるでしょう。
資源価格の値動きとの相関関係は弱い
豪州は鉱物資源が豊富なことでも有名で、特に金(ゴールド)の埋蔵量では全世界の19%を占めています。

Geoscience Australiaの公開データをもとに作成
その一方、豪州の産業構成を見ると、第二次産業(鉱工業)は26%ほどであり、鉱業は10%にすぎません。大半は第三次産業(サービス業など)が占めています。

外務省の公開データをもとに作成
豪州経済に占める鉱業の割合は特に大きいというわけではなく、金など鉱物資源価格が上昇しても豪ドル/円が円安になるとは限らないので、注意が必要です。
鉱物資源価格に注目しすぎると、値動きを理解しにくくなるかもしれないので注意しましょう。
下は2007年以降の豪ドル/円とゴールド/米ドルの価格推移を示しており、両者の間に強い相関関係はないように見えます。
豪ドル/円

OANDA証券のMT5から筆者引用
ゴールド/米ドル

OANDA証券のMT5から筆者引用
今までの価格推移から見る豪ドルの買い時
豪ドル/円の長期チャートは値動きが独特であり、買い時が比較的わかりやすいのが特徴です。
安値をつけた際にはイベントが発生していますので、内容を確認しつつ豪ドル/円の買い時を考察しましょう。
豪ドル/円が安値をつけた際の出来事
豪ドル/円が安値をつけた時期の出来事

OANDA証券のMT5から筆者引用
1995年1月|阪神・淡路大震災
チャート内の①の部分は、阪神・淡路大震災後の円高を示しています。
地震発生後はしばらく円安気味での推移でしたが、2月以降に本格的に円高が進みました。
5月下旬に58円台を記録しており、これは当時の円高記録です。
阪神・淡路大震災
1995年1月17日に淡路島北部で発生した地震です。最大震度は7、死者・行方不明者は合計で6,400名以上でした。
2001年|インターネットバブル崩壊
②はインターネットバブルの崩壊です。
円高そのものは1997年5月以降から継続しており、インターネットバブル崩壊は最後のダメ押しでした。
2000年に55円台を記録してから円安に戻した後、翌年には56円付近まで円高が進んでいます。
インターネットバブル
米国を中心にインターネット関連企業の株価が高騰し、合理的に説明できない水準にまで価格が上昇した出来事を指します。
インターネットの発達で従来の経済は大変革を迎えると評価され、「ニューエコノミー」などともてはやされました。
2008年|リーマンショック等
2008年9月にリーマン・ブラザーズが経営破綻し、豪ドル/円は翌10月にかけて大きく円高が進みました。
円高自体は2007年のサブプライムローン問題をきっかけに始まっており、世界中が不景気になりました。円安に戻り始めたのは、2009年3月以降です。
リーマンショック
米国の投資銀行リーマン・ブラザーズの経営破綻を指します。金融危機と不況が急速に進んだことで知られています。
サブプライムローン問題
サブプライムローンとは、信用力がやや劣る人向けのローンを指します。米国でサブプライムローンの延滞率が上昇し、影響が各方面に波及して世界的な不況に結びつきました。
2020年3月|新型コロナウイルス問題
新型コロナウイルス問題を受けて、豪ドル/円は2020年2月以降に下げ足を速め、3月には60円をわずかに下回る水準まで急落しました。
円高自体は2014年から徐々に進んでおり、新型コロナウイルス問題が追い打ちをかけた形です。
新型コロナウイルス問題
2019年に中国で原因不明のウィルス性肺炎が発生し、急速に全世界に広がりました。日本では数次にわたって緊急事態宣言が出されています。
豪ドル/円の買い時
過去4回の暴落と反発の間には少なくとも4つの特徴があり、似たような状況が再現したら買い時だといえそうです。
過去4回の暴落と反発の特徴
- 暴落時に大きなイベントが発生している
- イベントは日本や豪州での発生に限定されない
- 安値はいずれも50円台
- 安値をつけた後に大幅円安が実現
豪ドル/円は豪ドルと円の組み合わせですから、豪州や日本の経済指標等を反映して動きます。
しかし、暴落で歴史的安値をつけた場面では、日豪両国以外のイベントが発端となっています。例外は1995年の阪神・淡路大震災のみです。
世界的な危機等が発生する場面で、円高が進む可能性に留意しましょう。
ゆったり為替
値動きにも特徴があり、4回とも安値は50円台でした。将来的に同じような暴落が発生する場合、50円台を最安値の目途として考えられるでしょう。
暴落を記録した後は上昇し、レンジ相場の上限付近まで進んだのも特徴的です。
55円~59円付近で底を打って100円前後まで円安が進みますから、その差は最大で45円(4,500pips)という巨大さです。
将来も必ず同じ動きになるとは限りませんから、リスク管理を万全にして取引しましょう。
ゆったり為替
今までの価格推移から見る豪ドルの売り時
豪ドル/円の売り時は、買い時に比べると判断が困難です。高値をつけた部分で何があったか、確認しましょう。
豪ドル/円が高値をつけた際の出来事
豪ドル/円が高値をつけた時期の出来事

OANDA証券のMT5から筆者引用
1997年5月|大蔵省(現財務省)高官の発言
1997年5月に豪ドル/円が急落したのは、大蔵省(現財務省)高官による発言がきっかけとされています。
しかし、買い時に関して紹介したような明確なイベントは見当たりません。
急落に至る背景がいくつか指摘されており、同年後半のアジア経済危機などを受けて円高が大きく進みました。
アジア経済危機
1997年7月以降、東南アジア諸国や韓国で通貨価値が暴落し、経済危機が発生しました。
2007年|サブプライムローン問題
サブプライムローン問題を受けて、相場が大きく上下動しています。
当時はサブプライムローン問題の適切な評価が難しく、過小評価も多く見られました。
2008年後半以降、事態の深刻さは誰の目にも明らかとなり、豪ドル/円の暴落も発生しています。
2013年|豪準備銀行による利下げ
豪ドル/円が頂点をつけたのは2013年4月であり、大きなイベントを確認できません。
翌月に豪準備銀行(中央銀行)が利下げしており、下落のきっかけは利下げの可能性があります。
頂点に達した後も、豪ドル/円は数年にわたって価格を維持しています。
豪ドル/円の売り時
豪ドル/円の売り時は、買い時に比べて判断が困難です。
暴落時に比べてイベントの規模が小さく、将来的に同じイベントが発生するときに下落のきっかけとして利用できるかどうか、判断しにくいといえます。
為替レート水準に注目すると、豪ドル/円の頂点はいずれも100円台でした。
100円到達後は下落に注意すべきといえそうですが、2013年の下落はやや小さく、2014年後半に再び高値を目指す展開でした。
売り時については、明確なポイントを挙げるのは難しいといえるでしょう。
豪ドル/円を売ると日々のスワップ損が大きく、買いに比べて売りは難易度が高いと想定できます。
ゆったり為替
豪ドル/円は5年後・10年後どうなる?今後の見通し
月足チャートや各種イベントの考察をもとに、豪ドル/円の5年後・10年後の見通しを考察します。
豪ドル/円の5年後・10年後の見通し
50円台を再び目指す可能性
過去の動きが繰り返されるなら、危機が発生して再び50円台を記録する可能性があるでしょう。
豪ドル/円が50円台の安値をつけた当時のイベントは、どれも避けたいものばかりです。
日豪が発端でない危機でも、豪ドル/円が急落している点に要注意です。
豪ドル/円が安値をつけた時期の出来事
豪ドル/円が安値を記録する間隔も重要で、ある安値から次の安値まで6年から12年ほどです。
次の危機は5年後か10年後か不明ですが、暴落が再現しても不思議はありません。
日本の短期金利と危機の関係
日本の短期金利の推移をグラフ化すると、危機の発生時期をある程度予測できるかもしれません。
下は日本の短期金利(無担保コールレート)をグラフ化したもので、縦線の位置で大きなイベントが発生しています。

日銀の公開データをもとに作成
短期金利の推移とイベントの発生
- 1991年|バブル崩壊
- 2001年|インターネットバブル崩壊
- 2008年|リーマンショック
短期金利が上昇した後に、イベントが発生してきました。金利水準や上昇幅はそれぞれ異なるものの、上昇後の危機発生という点では一致しています。
当記事執筆時点で、日銀は大規模金融緩和政策を転換し、政策金利の引き上げに転じています。
日本の物価上昇が日銀の期待通りに進むなら、短期金利も徐々に上昇するでしょう。
短期金利が上昇した後に世界的な危機が来るのか来ないのか、執筆時点で予見することはできません。
しかし、3回続けば4度目もありうると考え、準備しておく価値はあります。
短期金利上昇後にイベントが発生しない場合、多くの人々が平穏に過ごせるので素晴らしいことです。一方でイベントが発生した場合には、暴落に備えて準備し、大きな利食いを狙えます。
どちらに転んでも大丈夫なように、日ごろから備えましょう。
ゆったり為替
100円を明確に超えて円安が進む可能性
豪ドル/円が100円を大幅に超えて円安が進む可能性もあるでしょう。
米ドル/円を見ると、当記事執筆時点で150円台を記録しており、1990年以来の円安水準です。
今後の推移は不明ですが、円安がさらに進む可能性を捨てきれません。米ドル/円だけでなく、円は主要通貨に対して弱い動きです。
豪ドル/円でも円がさらに弱くなれば、レンジを上抜ける可能性があります。
1980年代、豪ドル/円は200円台を記録しています。今後の日本経済が豪州と比べて大きく後れを取るなら、再度200円が実現するかもしれません。
豪ドル/円取引におすすめのFX会社
豪ドル/円取引のポイント・注意点
豪ドル/円取引のポイントや注意点は、以下の通りです。
豪ドル/円取引のポイントや注意点
基本はレンジ相場
豪ドル/円は30年以上にわたってレンジ相場を形成しており、今後もしばらく続く可能性があります。
レンジ相場に適したトレード手法の採用が、取引のポイントになるでしょう。
レンジ相場が続くなら、安値の目途は50円台半ばだと想定できます。安値の目途がない場合と比べると、準備すべき証拠金額の把握が容易で、取引しやすいです。
55円の再現への準備
直近30年で豪ドル/円が100円に到達した回数は4回であり、過去3回はその後に大きな円高に転じています。
当記事執筆時点は4回目にあたり、過去と同様の動きをするなら円高が大きく進行します。
90円台や100円台で長期保有の買いポジションを持つと、将来的に含み損が大きくなるかもしれないので要注意です。
レンジを外れる動きも想定
レンジ相場が30年以上続いているとはいえ、永遠に継続すると考えるのは適切でありません。
レンジ相場はいつか終わるものであり、終了時の備えも必要です。
当記事執筆時点で豪ドル/円は90円台後半に位置しており、レンジ相場の上限を超える円安に注意する必要があるでしょう。
豪ドル/円以外の通貨ペアの取引も検討している方は下記の記事も参考にしてください。
豪ドル/円取引におすすめのFX会社3選
豪ドル/円で注目したいポイントごとに、おすすめのFX会社を紹介します。
おすすめのFX会社はこの3つです!
ゆったり為替
豪ドル/円取引におすすめのFX会社3選
スワップポイント狙いなら:LIGHT FX
LIGHT FXはスワップポイントの大きさに定評があり、複数の通貨ペアで業界最高水準のスワップポイントを提示しています。
各FX会社のスワップポイントを比較してみましょう。
各FX会社公式サイトの公開情報をもとに筆者作成
調査日:2024年3月30日
豪ドル/円の暴落時に買う場合、保有期間は年単位になる可能性があるので、スワップポイントの大きさが重要になります。
高金利通貨ペアのスワップポイントについて、LIGHT FXは特に大きな数字を提示します。
ゆったり為替
公式サイトはこちら
スキャルピングをしたいなら:ヒロセ通商
短い時間で売買を繰り返すスキャルピングをするには、スプレッドの狭さに加えて、FX会社がスキャルピングを認めていることが大切です。
スキャルピングを事実上禁止するFX会社が多い中、ヒロセ通商はスキャルピングを歓迎しています。
スキャルピング禁止のFX口座でスキャルピングをすると、口座が凍結されるかもしれないので要注意です。
ゆったり為替
公式サイトはこちら
スプレッド重視なら:マネーパートナーズ【FX nano口座】
スプレッドの狭さを求めるなら、マネーパートナーズ【FX nano口座】です。
午前9時から翌日午前3時までの時間帯で、1万通貨以内で取引すると、豪ドル/円のスプレッドは0銭(※)です。
スプレッド0銭(※)とは取引コストが不要という意味ですから、顧客にとって大変有利だといえます。
※スプレッドは原則固定(例外あり)。
マネーパートナーズの公式サイトはこちら
現役トレーダーによる豪ドル/円の取引経験談
筆者が実際に取引した手法・取引しようとした手法について、経験談を紹介します。
豪ドル/円のトレード手法
レンジ相場を活かしたリピート系注文
リピート系注文とは特定の為替レートで何度も売買を繰り返す手法で、レンジ相場に強いとされています。
トラリピやループイフダンなどが有名で、数多くのFX会社で利用可能です。
豪ドル/円は30年以上もレンジ相場で推移しており、長期のリピート系注文におすすめの通貨ペアです。
しかし、豪ドル/円=100円付近で買った後に55円付近まで円高が進むと、含み損が大変な大きさになります。
下のチャートで示した枠の範囲を目途に取引することで、含み損の問題を緩和できます。

OANDA証券のMT5から筆者引用
長期リピート系注文で重要なポイントの一つに、証拠金額があります。
証拠金不足で取引を始めると、為替レートの急落時に強制ロスカットされる可能性があるので注意しましょう。
実際の取引では、豪ドル/円=55円を下回っても大丈夫な金額を用意し、主にトライオートFXの自動売買で取引してきました。
筆者は長期間にわたって取引を継続した結果、今までに少なくとも数百回の利食いをしているはずです。
為替レートは55円を下回ったことがないので、損で終わったことはありません。
当記事執筆時点の為替レートは90円台であり、長期リピート系注文をお休みしています。
ゆったり為替
豪ドル/円の暴落で買って長期保有
安値がわかりやすい豪ドル/円の性質を使って、筆者はチャート内の☆印の部分でトレードを画策しました。
トレードそのものは成功しなかったものの、紹介しましょう。

OANDA証券のMT5から筆者引用
☆印の下落は2020年3月で、新型コロナウイルス問題が世界中に広がっていた時期です。相場は荒れて、豪ドル/円が急落しました。
一般的に急落は怖いはずですが、当時の私は期待に胸を膨らませていました。過去の最安値は54円台で、その他の安値も50円台後半に集まっていると知っていたからです。
トレードに際して、以下のプランを作りました。
- 59円から買い下がり、50円まで買う
- 買ったポジションは長期保有し、85円を超えたら少しずつ決済する
- 95円付近ですべてのポジションを決済する
過去の最安値は54円台ですが、今回はどこまで円高が進むか不明です。
そこで、円高記録を更新しても対応できるよう、50円まで買い下がることにしました。
しかし、実際には60円ちょうどまで急落した直後に反転上昇してしまい、買えませんでした。
過去と同様に動くなら、少なくとも59円の買い注文は約定するだろうと考えていたのですが、正解は60円台からの買い下がりでした。
反転上昇後の値動きについてはチャートの通りで、2024年3月に100円を超える水準に到達しています。残念ですが、相場ですから仕方ありません。
重要なポイントは、「あらかじめ安値を想定できていた」という点です。
多くの人が下落に恐怖していた時期に、私はトレードチャンス到来を期待しており、心理的な差は明らかです。
他人と少し違う視点を持つだけで、大きな成功を手に入れられるかもしれません。
まとめ
豪州は中国との経済的結びつきが強い一方、安全保障面では対立しており「やばい」関係といえるでしょう。
値動きを見ると、豪ドル/円は30年以上レンジで推移しており、この間の豪州の政策金利は常に日本を上回っています。レンジと金利差の特徴を狙ったトレードが可能です。
長期的な視野でトレードする場合には、安値で買う方法や巨大な範囲でのリピート系注文を検討できるでしょう。短期でも取引可能で、スプレッド0銭でのデイトレードもできます。
お好みに沿ってさまざまトレード手法が可能なので、いろいろなトレードを検討してみましょう。
豪ドル/円取引におすすめのFX会社





