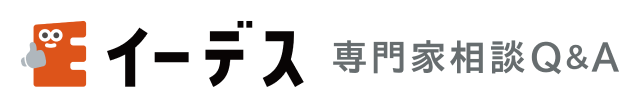教育資金の貯め方について
女性34歳既婚/子供あり
相談内容:教育資金・学費の見直し
子どもの教育資金の貯め方で、学資保険がいいのか投資等で増やして行く方がいいのか悩ましい。ただ投資といっても何をどうしたらいいかわからない。
回答一覧
こんにちは。教育資金の貯め方についてのお悩みですね。 「教育資金を貯める」というと、一般的には大学進学用のお金をさします。ご相談さんのお子様がまだ未就学児であれば、教育資金を使うのは10年以上先なので、ただ貯金するのではなく、できるだけお金が増える方法で貯めていくと良いでしょう。 学資保険と投資(ここでは、つみたてNISAを使ってできる株式インデックス投資信託を想定します)は、リスクと期待できるリターンの大きさが違います。2つの方法のリスクとリターンのイメージは、次の通りです。 ■学資保険 主なリスク・・・途中解約しなければ元本割れしない商品が多い 期待リターン…お子様が0歳の時に契約して18歳の時に受け取る契約で、返礼率105%前後が最大 イメージ例:総額100万円支払って、合計105万円受け取る 同時に、万一保険料を支払っている途中で契約者が亡くなったときには、その後の保険料の支払いが不要になる「保障」が付いていたり、生命保険料控除という「節税効果」が得られたりします。 ■株式インデックス投資信託(つみたてNISA制度などを使ってできる方法) リスク・・・日々価格が変動する。1年で2~3割上下することが珍しくなく、ときには一時的に半分ほどまで値下がりすることもある 期待リターン・・・海外株式の投資信託なら直近20年ほどの実績では平均年間6~7%前後の利回り イメージ例:価格が最大5割くらいまで前後するが、20年後には資産が2倍などに増える可能性がある 時期によって価格変動が激しく、今後上がるかどうかは誰にも読めません。教育資金は使う時期がほぼ決まっているため、株式インデックス投資信託に全額投資することは避けて、一部にしておくのがおすすめです。 お金を増やしたいお気持ちがあるなら、ぜひ、それそれの方法について詳しく学んで理解を深めてください。インターネット上の情報だけだと得られる情報の内容や質にばらつきがでやすいので、定評のある書籍を読んだり、信頼できる専門家へ相談するといった方法で学ぶのもおすすめです。 なお、もし勉強するのが苦手であれば、無理に難しい方法に取り組まなくても良いと思います。資産運用で増やさなくても、働いて稼いだり、節約して支出を下げたりすれば、貯められる教育資金は増やすことができます。ぜひ、ご自身に合った方法を選んでください。
お子さまの教育資金の貯め方についてのご相談ですね。 まずは、お子様の教育プランについてご家庭で考えてみましょう。 文部科学省の「平成30年度子どもの学習費調査」によりますと、 お子さま1人に係る教育費は、 幼稚園 公立の場合 年間約22万円 私立の場合 年間約53万円 小学校 公立の場合 年間約32万円 私立の場合 年間約160万円 中学校 公立の場合 年間約49万円 私立の場合 年間約141万円 高等学校 公立の場合 年間約46万円 私立の場合 年間約97万円 上記のようになっています。 あくまでも平均的な数字ですので、もしも中学受験を考えるとなれば、小学校の高学年から学習塾の費用がかかってきます。 高校までの学費はなるべく家計の範囲で捻出したいところです。 そのうえでお子様の教育プランを考えていきましょう。 さらに、大学進学を考えるとなると、お子様が小さい時からコツコツ貯蓄を積み立てることが大切です。 国公立大学の4年間にかかる費用はは学費だけで約242万円 私立文系の4年間にかかる費用は学費だけで約400万円です。 また、自宅通学できない地域へ進学となるとさらに仕送りの費用も必要になります。 お子さまの教育費が一番かかる18歳を目標にお金を貯めていくようにしましょう。 例えば、児童手当を使わずに貯蓄していくと15年間で約198万円貯めることができます。 さらに、毎月1万円を貯蓄すると、18年間で約216万円貯まります。 そうしますと、18歳までに約400万円を貯蓄できます。 これは一例ですが、お子様が18歳になるまでいくら貯めるか目標額を決め、そのためには毎月いくら貯めたらいいかを逆算して毎月の貯蓄額を決めましょう。 お金を貯める方法としては、 ①積立預金 ・メリット 元本割れのリスクがない。引き出しがいつでもできる。 ・デメリット 金利が低いので増えない ②学資保険 ・メリット 保険の機能があるので契約者が亡くなった場合でも教育費を準備できる ・デメリット 途中で解約すると元本割れする ③つみたてNISAなどの資産運用 ・メリット 運用次第で資金を増やすことができる。増えた金額に対して税金がかからない。 ・デメリット 運用結果によっては元本割れすることもある それぞれのメリット、デメリットに合った貯め方を選ぶようにしましょう。 例えばですが、 家計の中心者が亡くなった時にお金を貯める資金がなくなる場合は、学資保険を検討しましょう。 家計の中心者が亡くなった場合でも、貯めるための資金の心配がない場合は預貯金やつみたてNISAなどの資産運用で貯めてもいいかと思います。 つみたてNISAを始める場合は、証券会社で口座を開き、毎月積み立てる金額と商品を決めます。初心者の方は、手数料の安いインデックスファンドを選ぶといいです。 もしも、お子様の教育費が不足する場合は、国の奨学金や民間の奨学金などの制度もあります。 国や民間の奨学金には、返す必要がない給付型の奨学金と返す必要がある貸与型の奨学金があります。 そのような制度も視野に入れつつ、お子様の教育プランを考えてあげましょう。 お役に立ちましたら嬉しいです。
関連質問
教育資金・学費2024-04-11
20年間で教育資金を効率良く貯めれる投資信託は?
3
1
教育資金・学費2022-12-12
これからのライフプランについて相談させてください。
2
0
解決
教育資金・学費2022-12-12
塾なども含めた教育資金について
2
0
解決